丵
___________________________________________________________________丵
屲挊 僽儘僌乽愮擭偺岆撉乿丂岞奐拞 _____________________________
丂
巐挊乽堦恾偱傢偐傞擔杮屆戙巎乿岞奐拞 _____________________________
丂
丂
丂
婑峞暥乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿乮2017乯 丂丂丂丂
丂
弶挊乽榒崙捠巎乿婛姧丒
丂
俫俷俵俤 丂 擭昞丒抧恾 丂 嶲峫暥專 _____________________
丂
丂
丂
婑峞暥乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿丂夝戣
捛壛丂2024.01
壗擭偐慜丄昅幰偼偁傞妛弍帍偺曇廤幰偐傜婑峞埶棅傪庴偗偨丅婫姧帍乽桞暔榑尋媶乿偺妘擭摿廤崋乽拞娫憤妵丂巗柉偺擔杮屆戙巎尋媶乿偱偁傞丅偙偺婫姧帍偼巚憐揑娤揰偐傜乽楌巎乿丒乽嬨廈墹挬愢乿傕尋媶懳徾偲偟丄悢擭偵堦搙乽嬨廈墹挬愢偺尋媶恑捇傪憤妵偡傞摿廤崋乿傪婇夋丄鐱乆偨傞榑幰偵婑峞偺応傪採嫙偟偰偄偨偺偱偁傞丅偦偺榑幰偺堦恖偑昅幰傪曇廤幰偵悇慐偟偨偲暦偔丅
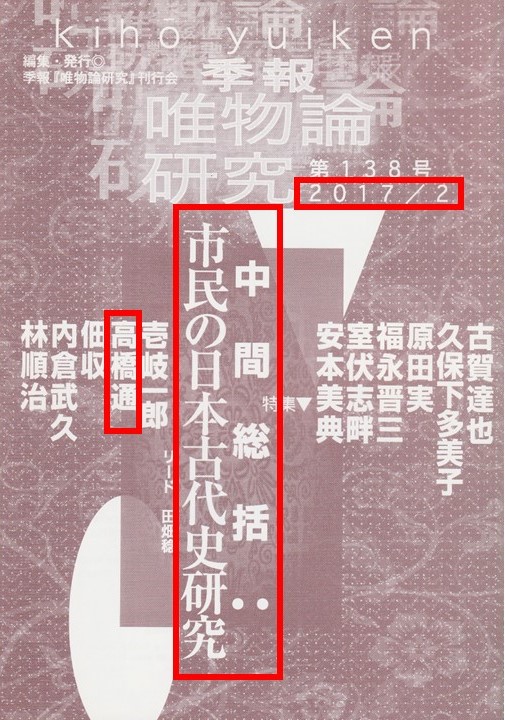
摿廤崋昞巻
偙偺摿廤崋偺榑幰偵怗傟傛偆丅
屆夑払栫乮昅摢榑幰乯丗乽屆揷晲旻偺惓摑宲彸幰乿傪帺擟偟偰丄暘楐屻偺乽屆揷巎妛偺夛乿戙昞偱偁傞丅
暉塱怶嶰丗乮媽乯屆揷夛偺姴帠傪偟偰偄偨偑丄帺愢偱屆揷偲傇偮偐傝攋栧偝傟偨偲偟偰偄傞丅暉塱偑偦偺屻奐偄偨寧堦尋媶夛偵昅幰傕偟偽傜偔嶲壛偟偨偙偲偑偁傝丄屆揷巎妛偺尋媶僗僞僀儖傪奯娫尒偨偺偼嶲峫偵側偭偨丅崱偱傕尋媶夛偺埬撪傪捀偄偰偄傞丅
幒暁巙斎丗尪帇巎妛偲徧偡傞捈姶揑壖愢乽撿慏杒攏愢乿乮奀梞搉棃宯榒恖偲杒曽婻攏柉懓枛遽偺榒恖偲偺偣傔偓偁偄愢乯偺榑徹傪彞偊偰偄傞丅峀偄恖柆偐傜撈憂揑屒棫榑幰傪巟墖偟偨傝乮戝幣塸梇側偳乯丄偙偺摿廤崋偺傑偲傔栶偱傕偁傞丅崱偱傕帺榑嶜巕傪掕婜揑偵捀偄偰偄傞丅
埨杮旤揟丗嬨廈墹挬愢偲偼嫍棧傪抲偔掕愢攈乮傛傝偼捠愢攈乯偲偟偰懡偔偺撉傒暔傪採嫙偟偰挊柤偱偁傞丅屆揷晲旻傪寖偟偔榑擄偟偨偙偲偱傕抦傜傟傞丅
捪澗丗嬨廈墹挬愢傪鉱枾偵榑徹偟偨戝晹乮乽屆戙巎偺暅尦乿幍嶜乯傪傕偺偟偰偄傞丅撈帺偺戝嬊揑攃埇乮懡尦揑墹挬岎戙乯側偳偵昅幰偼巀摨偟側偄偑丄懡偔偺榑徹偼嶲峫偵側傝丄懡偔傪堷梡偝偣偰捀偄偰偄傞丅
嫶捠丗 乽榒崙捠巎乿偱拲栚傪摼丄偦偺堦晹偑捪澗偺媣棷暷戝妛島墘偺嶲峫帒椏偲偟偰徯夘偝傟傞側偳偟偨丅

摿廤崋栚師
丂丂昅幰偑偙偺僒僀僩偱偙偺婑峞暥偵怗傟偨偙偲偼柍偄丅側偤側傜丄偙偺婑峞暥偼師挊乽崅揤尨偲擔杮偺尮棳乿偺愭嬱揑峫嶡暥乮壖愢乯偱偁偭偰丄師挊偑傛傝徻嵶偵丄傛傝惓偟偔榑徹偟偨偺偱丄廳暋傪旔偗偨偺偱偁傞丅
丂丂偨偩丄昅幰偵偲偭偰偼巣奅偺鐱乆偨傞榑幰偵暲傫偱帺愢傪斺鄉偱偒偨婰擮偡傋偒応偱偁傝丄彫榑乮12暸乯側偺偱夵傔偰偙偙偵揮嵹偝偣偰偄偨偩偔傕偺偱偁傞丅
婫曬桞暔榑尋媶摿廤崋丂乽拞娫憤妵丂巗柉偺擔杮屆戙巎尋媶乿丂2017丏02
榒崙偲戝榓墹尃偺壦偗嫶乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿
墳恄丒宲懱丒忋媨墹丒揤晲偺弌帺傪夝偔
崅嫶丂捠丂岺妛攷巑丂丂丂丂丂
昅幰嬤嫷棑丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
慜挊乽榒崙捠巎乿偵柍偄怴撪梕偱弌峞丅婰婭偺恄榖偲奀奜巎彂偑堦抳偡傞怴夝庍両
岺妛攷巑偺乽岺乿偲偼乽擇乮揤偲抧乯偺娫傪偮側偖掕婯傪帩偮恖乿偺堄偲偄偆丅乽恄榖偲巎幚乿傪偮側偖恖偵側傝偨偄傕偺偱偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂
偼偠傔偵
昅幰偼慜挊乽榒崙捠巎乿[拲1]偱乽榒崙偲戝榓墹尃偺摨柨揑娭學乿乽戝榓墹尃偑嬨廈偵廳揰傪堏偟偨帪婜偑偁偭偨乮埨娬乣槷柧乯乿乽擔杮彂婭偺榒崙晄婰嵹偺攚宨乿乽墳恄丒宲懱丒忋媨墹丒揤晲偺弌帺偺晄徻揰乿側偳傪栤偆偨丅杮彫榑偱偼偙偺嵟屻偺乽晄徻揰乿偑乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偲偄偆僐儞僙僾僩偵傛偭偰憡摉掱搙夝徚偡傞偙偲丄偦偺夝庍偵傛偭偰丄側偤壗搙傕墹摑偑棎傟側偑傜丄戝榓墹尃偑嬋傝側傝偵乽枩悽堦宯乿傪庡挘偟摼偨偐傪榑偠偨偄丅
仠丂戝榓墹尃偲娭栧奀嫭偺娭學
恄晲乣揤晲傑偱偺戝榓墹尃偼乽娭栧奀嫭堟乿偵摿暿偺娭怱偲娭學傪帵偟偰偄傞丅懄偪丄恄晲偑偙偺抧偐傜搶惇偵弌棫偟乮恄晲婭乯丄宨峴乣拠垼偑偙偺抧堟偺寠栧乮挿栧乯偵媨傪抲偒乮拠垼婭乯丄墳恄丒恗摽偑偙偺抧乮擄攇亖娭栧奀嫭堟乣朙崙丄屻弎乯傪偁傞帪婜椞桳偟丄埨娬乣槷柧偑朙崙偵幏拝傪帵偟偰偄傞乮埨娬婭乣槷柧婭乯丅偦偟偰丄揤晲揤峜偼乽壓娭旴揷弌恎偲巚傢傟傞垻楃乿傪屇傃弌偟乽屆帠婰乮戝榓墹尃偺婰榐乯乿傪揱鎢偝偣偨丅
側偤戝榓墹尃偼乽榒崙偑巟攝偟偰偄偨娭栧奀嫭堟乿偵偦傟掱偙偩傢傞偺偐丅偙偺撲夝偒偑庱戣偺夝柧偺巺岥偲側傞丅傑偢丄恄榖偐傜巒傔傞昁梫偑偁傞丅
仠丂僀僓僫僊偲娭栧奀嫭
慜愡偺乽娭學乿偼戝榓墹尃偺慶僀僓僫僊丒僀僓僫儈偵巒傑傞偙偲偑屆帠婰偺乽搰惗傒恄榖乿偐傜撉傒庢傟傞丅偦偺恄榖偼嶰抜偐傜惉傝丄乽僆僲僑儘僕儅惗傒乿乽戝敧搰乮偍偍傗偟傑乯惗傒乿乽乮僆僲僑儘僕儅偵乯娨傝傑偡帪惗傔傞榋搰乮媑旛帣搰丒彫摛乮偁偢偒乯搰側偳榋搰乯乿偱偁傞丅偙偺乽榋搰乿鏉偼擔杮彂婭偵偼柍偄丅
偙偺乽榋搰乿偼乽娭栧奀嫭杒惣偺搰乆乿偵斾掕偱偒傞丅榋搰偡傋偰偺搰柤偑尰嵼柤偲惍崌偡傞揰傪帩偪丄慡懱偲偟偰悢丒搰柤丒抧宍丒弴彉偑嫟偵惍崌偡傞丅恄榖偲偟偰偼婬側椺丄傓偟傠巎揑夝庍偲偟偰乽斾掕抧榑徹乿偲偡傞偵懌傞儗儀儖偲峫偊傞乮斾掕寢壥偼[拲2]丄嶲峫暥專偼[拲3]乵拲5乶丄榑徹偼[拲1]憹曗斉嶲徠乯丅懄偪乽僀僓僫僊丒僀僓僫儈偑僆僲僑儘僕儅偵娨傞帪惗傫偩榋搰乿偲偼乽娭栧奀嫭傪婲揰偵杒惣曽岦偵暲傇榋搰乿偵斾掕偱偒傞丅巎幚偐偳偆偐偼偝偰慬偒丄屆帠婰偼偦偺傛偆偵撉傔傞婰弎傪偟偰偄傞丅
仠丂僆僲僑儘僕儅偼廆憸壂僲搰
慜愡偺乽娭栧奀嫭榋搰乿傪塺傫偩壧偑偁傞丅墳恄婭偺乽擄攇戝嬿媨偺壧偲屻懕暥乿偵乽偁偼偫偟傑乿乽偁偢偒偟傑乿乽扺楬搰乿乽擄攇偺惣乿乽媑旛乿偺抧柤偑偁傝丄恗摽婰偺乽扺摴搰偱傛傔傞壧偲慜屻暥乿偵乽側偵偼乿乽偍偺偛傠偟傑傒備乿乽媑旛乿偲偁傞丅慜愡媦傃乽偍偺偛傠偟傑傒備乿乮慜愡榋搰偺愭乯丒乽偁偢偒偟傑乿乮慜愡榋搰偺堦偮乯偑帇栰偵擖偭偰偄傞偐傜丄擇偮偺壧偺帇揰偼傎傏摨偠偱乽娭栧奀嫭乿偱偁傞乮奀嫭搶偲惣丄娽慜偐斲偐偺庒姳偺堘偄偼偁傞乯丅廬偭偰丄偦偺帇揰偺撪偵偁傞嫟捠抧柤乽偁偼偫偟傑乮扺楬搰丒扺摴搱乯丒側偵偼乮擄攇乯丒媑旛乿偼乽娭栧奀嫭惣乿偵斾掕偱偒傞乮徻嵶丄暲傃偵屻擭偺抧柤堏怉偵偮偄偰偼[拲1]憹曗斉嶲徠乯丅
枖丄慜愡偺斾掕偐傜丄娭栧奀嫭杒惣榋搰偺愭丄恗摽偺壧乽僆僲僑儘僕儅尒備乿偼乽廆憸壂僲搰乿偵斾掕偱偒傞丅帠幚丄娭栧奀嫭偐傜揤婥偑椙偗傟偽壂僲搰偑尒偊傞丅
峏偵丄乽僀僓僫僊偺弌敪抧崅揤尨 仺 僆僲僑儘僕儅乮壂僲搰乯 仺 榋搰乮娭栧奀嫭杒惣榋搰乯乿傪媡偵扝傞偲丄乽僀僓僫僊偺崅揤尨偼懳攏乿偑帵嵈偝傟偰偄傞丅
仠丂僀僓僫僊偺乽彫屗乿偼乽壓娭旻搰乿
慜愡偑朤徹偲側偭偰丄師偺斾掕偑壜擻偲側傞丅僀僓僫僊偼僀僓僫儈偺巰屻丄釹乮傒偦偓乯傪偟丄嶰婱恄乮傾儅僥儔僗丒僣僋儓儈丒僗僒僲儝乯傪惗傓丅偦偺抧偵偮偄偰婭恄戙屲抜堦彂榋丒摨堦彂廫偵彂偐傟偰偄傞尵梩偵乽彫屗乿乽彫栧乿乽埦栧乮偁偼偲乯乿乽懍媧柤栧乿乽挭乿乽棳傟乿乽悾乿乽擇栧乿乽拀巼乿偑偁傞丅乽拀巼乿偑偁傞偐傜丄嬨廈嬤偔偺暋悢偺奀嫭柤偲峫偊傜傟傞丅偦偺撪乽懍媧柤栧乿偼恄晲搶惇偱嵟弶偵捠偭偨奀嫭乽懍媧栧乿乮婰乯偱乽娭栧奀嫭乿偲峫偊傜傟偰偄傞丅乽埦栧乿傕乽挭乿偲偁傞偐傜奀嫭偱偁傞丅乽擇栧乿偲偁傞偐傜暿偺奀嫭偱偁傞丅乽娭栧奀嫭乿晅嬤偵偼懠偵偼尰乽彫栧乮偍偳乯奀嫭乿偟偐側偄丅偙傟偼壓娭偲旻搰偲傪妘偮4km掱偺愳偺條側奀嫭丄娭栧奀嫭懁偵嫹偄岥乮乣30m丄棳傟偑懍偄乯偲擔杮奀懁偵峀偄岥乮乣300m丄棳傟偑庛偄乯傪帩偮丅忋宖偺婰丒婭乮堦彂乯偺婰弎偵堦抳偡傞丅乽僀僓僫僊偺彫屗乿偼奀嫭偲偟偰偼乽壓娭彫栧奀嫭乿偵丄抧柤偲偟偰偼乽旻搰彫屗乮尰彫屗岞墍側偳乯乿偵斾掕偱偒傞乮惣堜寬堦榊愢[拲3]傪婎偵専徹乯丅
埲忋偐傜丄屆帠婰偺搰惗傒鏉傪巎揑夝庍偡傟偽乽僀僓僫僊偼懳攏乮崅揤尨乯傪弌偰丄壂僲搰乮僆僲僑儘僕儅乯偱崙惗傒婩婅乮乽搰惗傒乿偺杮嫃愰挿夝庍乯傪偟偨屻丄娭栧奀嫭傪嫆揰偲偟偰妉摼偟丄壂僲搰乮僆僲僑儘僕儅乯偵娨傝丄嵞傃娭栧奀嫭旻搰偺彫屗偵栠偭偰嵳帠乮釹乯傪偟偨乿偲夝庍偡傞偙偲偑偱偒傞丅慜擇愡偲崌傢偣丄僀僓僫僊傪慶偲偡傞戝榓墹尃偑娭栧奀嫭偵偙偩傢傞棟桼偺戞堦偱偁傞丅
仠丂僀僓僫僊偺乽拀巼偺擔岦乿偼乽娭栧奀嫭拀巼懁乿
僀僓僫僊偺彫屗偼乽拀巼偺擔岦偺彫屗乿乮屆帠婰乯偲偁傞丅彫屗旻搰愢偵偼乽旻搰偼拀巼偱側偄乿偲偄偆媈栤偑偁偭偨丅偟偐偟丄娭栧奀嫭偼椉娸傪巟攝偟偰弶傔偰梫徴偺堄枴傪帩偮丅搰偲偟偰偼暿偩偑丄擔岦偲旻搰傪梫徴偲偟偰乽摨堦椞堟乿偲尒傞偙偲傕偱偒傞丅椺偊偽拠垼婭偵乽娭栧奀嫭偺寠栧乮嶳岥乯偐傜塅嵅傪搶栧偲偡乿側偳丄乽奀嫭椉娸傪摨堦椞堟乿偲尒傞椺偑偁傞丅偦偺棟夝偱丄乽擔岦偼娭栧奀嫭拀巼懁丄懳娸偺旻搰彫屗傕擔岦偺摨堦椞堟乿偲棟夝偡傟偽丄乽拀巼偺擔岦偺彫屗乿偼惉傝棫偮丅
摨堦椞堟偩偐傜墦曽偱偼側偄丅旻搰偺懳娸丄椺偊偽乽栧巌乿偑擔岦偺斾掕岓曗偲偟偰嫇偘傜傟傞丅偙偙偱偼斾掕弴傪乽彫屗 仺 擔岦乿偲偟偨乮嬨廈墹挬愢偲媡乯丅偨偩丄僀僓僫僊娭楢偺乽擔岦乿偼忋婰悢暥帤偩偗偱丄乽摨堦椞堟乿側偳偺夝庍偼弌偰偙側偄丅堦曽丄僯僯僊偺乽拀巼偺擔岦乿偵偼巟攝椞堟丒摨堦椞堟帇偺堄枴偑偁傞乮師愡乯丅偦偙偱丄僯僯僊帪戙傪婰弎偡傞嵺偵乽拀巼偺擔岦偺乮堦晹偱偁傞乯彫屗乿偲偄偆姷梡昞尰偑偁偭偰丄偙傟傪乽僀僓僫僊婰帠傊慿媦巊梡乿偟偨偲傕峫偊傜傟傞丅偙偙偱偼僀僓僫僊偺乽拀巼偺擔岦乿偼乽栧巌乿丄傪斾掕岓曗偲偟偰嫇偘傞偵棷傔丄師愡偱専徹偡傞丅
仠丂僯僯僊偺乽拀巼偺擔岦乿偼乽栧巌乿
僯僯僊偼乽埊尨拞偮崙傪巟攝偡傞堊偵丄拀巼偺擔岦偺崅愮曚曯偵揤崀傝偟偨乿偲偄偆乮婰婭乯丅
栧巌乮擔岦偺斾掕岓曗乯偺椬偵彫憅乮偙偔傜乯偑偁傞丅彫憅拞怱晹偵乽懌尨乮偁偟偼傜乯乿乽拞捗岥乮側偐偮偔偪乯乿偲偄偆抧柤偑椬傝崌偭偰尰懚偡傞丅埊尨拞偮崙乮偁偟偼傜側偐偮偔偵乯乿偺斾掕抧岓曗偲側傝摼傞乮[拲5]丄偨偩偟抧柤偺帪戙峫徹偼梫傞乯丅崌傢偣傞偲乽埊尨拞偮崙乮彫憅乯傪巟攝偡傞堊偵丄擔岦乮栧巌乯偵揤崀傝偟偨乿偲偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙傟傪乽拀巼偺擔岦偼栧巌乿偺斾掕榑嫆偺戞堦偲偟偨偄丅
偨偩丄彫憅傕旻搰偺懳娸偩偐傜丄彫憅傕乽擔岦乿偺戞擇岓曗丄偁傞偄偼乽栧巌偲彫憅椉幰崌傢偣偰擔岦乿偺壜擻惈傕偁傞丅埲壓偺乽栧巌乿偼偦偺壜擻惈傕崬傔偰乽栧巌乮乣彫憅乯乿偺堄枴偱巊偆丅
仠丂僯僯僊偺乽拀巼偺擔岦偺崅愮曚曯乿偼乽栧巌偺曯乿
僯僯僊偺乽擔岦偼栧巌乿乮慜愡乯偱偁傞側傜乽擔岦偺崅愮曚曯偼栧巌偺曯乿偲側傞丅偙傟傪専徹偡傞丅屆帠婰偵偼崅愮曚傪昡偟偨僯僯僊偺徺偑偁傞丅乽乮僯僯僊偼乯幈巼擔岦偺崅愮曚偺媣巑晍棳懡焼乮偔偟傆傞偩偗乯偵揤崀傝傑偡丄丄丄崯偺抧偼娯崙乮偐傜偔偵乯偵岦傂丄妢嵐乮偐偝偝乯偺屼慜乮傒偝偒乯偵恀棃乮傑偒乯捠傝丄挬擔偺捈乮偨偩乯巋偡崙丄梉擔偺擔徠傞崙側傝丄偐傟丄崯抧乮偙偙乯偼偄偲媑乮傛乯偒抧乮偲偙傠乯偲徺偡丄丄丄乿偲偁傞丅
偙偙偱乽挬擔偺捈巋偡乮偨偩偝偡乯崙乿偲偁傞偺偼偨偩偺挬擔偱偼側偄丅偨偩偺挬擔側傜偳偙偱傕嵎偡丅乽捈乮偨偩乯巋偡乿偲偼乽奀偐傜摢傪弌偟偨挬擔偺嵟弶偺岝偑捈偪偵巋偡乿偺堄枴偱偼側偄偐丅栧巌偺嬤偔偺庡曯乮椺偊偽屗僲忋嶳518m丄傑偨偼懌棫嶳597倣乯偵搊傞偲悾屗撪奀偑尒偊丄恀搶100km埲撪偵嶳傗搰偑柍偄丅偙傟傜栧巌偺曯偼乽奀偐傜徃傞挬擔傪攓傔傞杒嬨廈偱桞堦偺応強乿偱偁傞丅偙傟傪乽擔岦偼栧巌乿偺斾掕榑嫆偺戞擇偲偡傞丅攷懡廃曈偱偼曯偵搊偭偰傕挬擔偼奀偐傜偱側偔嶳偺抂偐傜弌傞丅
峏偵丄乽梉擔偺擔徠傞崙乿偺梉擔偼偨偩偺梉擔偱偼側偄丅乽奀偐傜弌偨擔偑奀偵栠傞傑偱徠傜偟偰偔傟傞抧丄嵟傕挿偔擔徠傞崙丄揤徠偡崙偵傆偝傢偟偄抧乿偲朖傔徧偊偨丄偲夝庍偱偒傞丅栧巌偺曯偐傜恀惣偺曽岦偼100km埲撪偵傛傝崅偄嶳傗搰偑側偔丄奀偵捑傓梉擔偑攓傔傞丅栧巌偺曯偼乽奀偐傜弌傞挬擔偲奀偵捑傓梉擔乿偺椉曽傪尒傜傟傞杒嬨廈桞堦偺応強偱偁傞丅乽擔岦偼栧巌乿偺斾掕榑嫆偺戞嶰偲偡傞丅
峏偵丄乽娯崙乮偐傜偔偵乯乿偼堦斒揑側娯崙偱偼側偄丅椙偄娭學偺娯崙丄偲傝傢偗揝側偳偺庡偨傞岎堈憡庤嬥姱崙乮屻偺壘栯乯側偳偱偁傠偆丅栧巌偼嬥奀巗乮嬥姱崙丄姌嶳惣乯偵捈愙岦偒崌偄丄攚屻偵揝偺悾屗撪奀巗応傪帩偪岎堈婎抧偲偟偰傕塰偊傞偩傠偆乽偄偲媑乮傛乯偒抧乮偲偙傠乯乿側偺偱偁傞丅斾掕榑嫆偺戞巐偲偡傞丅攷懡廃曈偱偼嬥奀巗偺娫偵偼懳攏偑墶偨傢傝捈愙岦偒崌偭偰偄側偄丅
僯僯僊帺恎偑擔岦傪崅偔昡壙偟偰偄傞彅揰偵偙傟掱崌抳偡傞抧偼懠偵側偄丅僯僯僊偺乽擔岦偺崅愮曚乿偼乽栧巌偺曯乿丄廬偭偰乽擔岦乿偼乽栧巌乿偲斾掕偱偒傞丅
仠丂乽妢嵐偺傒偝偒乿偼妢偺宍偺乽懳攏恄嶈乿
峏偵丄乽妢嵐偺屼慜乮傒偝偒乯乿傪埲忋偲摨條偺乽帇奅偺壥偰乿偺100km埲墦偵扵偡偲乽懳攏撿抂偵妢偺宍傪偟偨嶳乮恄嶳乯偐傜惉傞枽丄恄嶈乮偙偆偞偒乯乿偑偁傝丄斾掕抧岓曗偲偱偒傞丅
妢嵐偼乽僯僯僊偑揤崀傝偺搑拞乮宱桼抧乯偱僒儖僞僸僐偺弌寎偊偲擔岦傑偱偺悘峴傪庴偗偨抧乿乮婰婭乯丅偦偺僒儖僞僸僐偼乽崅揤尨偐傜埊尨拞偮崙傑偱傪徠傜偡崙恄乿乮婭乯偲偁傞偐傜榘巙榒恖揱偵乽洈攏殸偼愨搰丄丄丄椙揷柍偔丄丄丄慏偵忔傝偰撿杒偵巗怡乮偟偰偒丄岎堈乯偡乿偲偁傞乽懳攏偺奀尨榒恖乿偱偁傠偆丅摨彂偼偙偺乽撿杒乿傪杒嬨廈偲敿搰撿偺堄枴偱巊偭偰偄傞乮乽丄丄丄乿偼拞棯偺堄乯丅乽宱桼抧妢嵐偼懳攏乿偲惍崌偡傞丅
乽恀棃捠傝偰乿傪乽婲揰乮崅揤尨乯偲懳攏乮宱桼抧丄妢嵐乯偲廔揰栧巌乮擔岦乯傪捈慄偱寢傫偱恀偭偡偖棃偨乮恀棃捠傞乯乿偲夝庍偡傞偲丄偦偺媡傪偨偳偭偰婲揰傪媮傔傞偲乽敿搰撿丄懳攏偺搶170km曈傝乿偲偄偆偙偲偵側傞乮師愡乯丅懄偪乽僯僯僊偺崅揤尨乿偼乽敿搰撿乿偵斾掕偱偒傞壜擻惈偑偁傞丅乽懳攏恄嶈乿偼偦偺傎傏拞娫偲側傝丄偦偺嶳梕乮妢宍乯偲崌傢偣偰乽宱桼抧妢嵐乿偵憡墳偟偄斾掕抧偲側傞丅
乽敿搰撿 仺 懳攏撿抂 仺 栧巌乿偼乽懳攏奀棳偺忋棳 仺 壓棳乿偱偁傝丄巎幚乽奀乮偁傑乯壓傝乿傪恄榖揑昞尰偟偨偺偑乽揤崀傝乿偲夝庍偡傟偽忋婰慡偰偲惍崌偡傞丅
埲忋偐傜乽妢嵐偼懳攏撿抂恄嶈乿偵斾掕偱偒傞丅
仠丂乽崅揤尨乿偼撿娯乽崅嫽敿搰乿丂撪奜巎椏偑惍崌
敿搰偵傕榒恖偑偄偰丄晹棊崙壠孮偑偁偭偨乮娍彂抧棟巙丄婭尦慜1悽婭乯丅偟偩偄偵摑崌偟偰榒崙偲側偭偨乮屻娍彂榒揱107擭乯丅偦傟偼敿搰撿増娸晹偵傕峀偑偭偰偄偨乮屻娍彂娯揱乯丅偦偺拞怱偼乽懡攌撨崙偺撿惣愮棦乮80km乯乿偲偁傞乮嶰崙巎婰乽扙夝墹愢榖乿乯丅昅幰偼慜挊偱偙偺抧傪傎傏摿掕偟偰恾帵偟偨丅偦傟偼尰娯崙慡梾撿摴崅嫽乮僐僼儞乯孲偺乽崅嫽敿搰乿偱偁傞丅偙偺抧偼乽懳攏廃曈偺椙揷乮榘巙榒恖揱偺梡岅乯揔抧乿偲偟偰偼嫲傜偔峀偝巐斣栚乮 攷懡廃曈 亜 彫憅廃曈亜姌嶳廃曈亜崅嫽廃曈 乯偱偁傞丅娍偺朿挘偵墴偝傟偰敿搰惣傪撿壓偟偨娯恖偼攏娯乮昐嵪乯偺峀戝側椙揷揔抧偵棷傑傝丄堦曽敿搰拞墰晹傪撿壓偟偨娯恖丒濊乮傢偄乯恖乮僣儞僌乕僗宯丠乯丒柃栲乮傑偭偐偮乯恖乮崅嬪楉偲摨宯乯偼戞嶰偺姌嶳乛嬥奀偺椙揷揔抧偵棷傑傝丄偦傟傜偺拞娫偺戞巐偺崅嫽偼撿壓偡傞敿搰恖偺嬻敀抧懷偲峫偊傜傟傞丅戞堦偺攷懡偲戞擇偺彫憅偼僗僒僲儝宯偑愭偵墴偝偊偨偐傜乮婰婭乯丄崅嫽偼懳攏傾儅僥儔僗堦懓乮僀僓僫僊偺屻遽乯偺怉柉揔抧偲偟偰桞堦巆偝傟偨抧偱偁傞丅撿壓娯恖偵墴偝傟偨敿搰惣増娸偺堫嶌榒恖偺棳擖傪壛偊偰乮偁傞偄偼偦偪傜偑庡乯崅嫽廃曈偺榒崙偼擾峩偑惙傫偩偭偨偲巚傢傟傞丅婰婭偺傾儅僥儔僗崅揤尨偺婰弎偲惍崌偡傞丅慜愡偲崌傢偣乽傾儅僥儔僗偲僯僯僊偺崅揤尨偼敿搰撿丄摿偵崅嫽乿偵斾掕偱偒傞丅
偦偺屻乽娯丒濊乮傢偄乯偺峏側傞撿壓乿乮屻娍彂娯揱乯傕偁偭偰嵟屻偼乽敿搰榒崙偺徚柵乿(240擭榘巊捠夁帪揰埲慜丄慜挊偱榑徹偟偨)偲側傞丅偦傟偵愭棫偪傾儅僥儔僗偼堦懓彅彨傪楍搰偵揤崀傝偝偣乮怉柉乣怤棯乯丄揤懛儂傾僇儕乮孼乯偼僗僒僲儝宯偐傜乽崙忳傝乿傪彑偪庢傝丄攷懡廃曈乮戞堦偺椙揷揔抧乯傪婛偵帯傔偨乮師愡乯丅偙傟偼乽榒崙戝棎廂廍乿(斱栱屇偺180擭崰丄屻娍彂乯偵懳墳偡傞偲尵偊傞丅揤懛僯僯僊乮掜乯偼200擭崰乮抶偔傕240擭埲慜乯偵彫憅廃曈乮戞擇偺椙揷揔抧乯傪帯傔傞堊偵乽僒儖僞僸僐偺搉奀慏抍偱崅嫽敿搰乮傾儅僥儔僗偺崅揤尨乯傪弌敪偟丄懳攏撿抂乮妢嵐乯偱懳攏榒恖乮僒儖僞僸僐乯偺弌寎偊偲悘峴傪庴偗丄奀楬栧巌乮擔岦乯偵恀捈偖棃偨乮恀棃捠傝偰揤崀傝偟偨乯乿偲夝庍偱偒傞丅僀僓僫僊丒僯僯僊傪慶偲偡傞戝榓墹尃偑娭栧奀嫭堟偵偙偩傢傞棟桼偺戞擇偱偁傞丅
晅尵偡傟偽丄乽崅揤尨乿偺堄枴偵嶰抜奒偁偭偨偙偲偼慜挊偱傕巜揈偟偨丅乽尨弶偺恄榖崅揤尨偼揤乿偱偁傠偆丅乽僀僓僫僊偺崅揤尨偼屘抧懳攏偺壜擻惈乿傪慜弎偟偨丅偙偙偱偼乽傾儅僥儔僗偺崅揤尨偼屘抧偺敿搰榒崙乿偲偟偨丅嫲傜偔丄巎揑偵偼偦傟偧傟偺柤慜偑偁傝丄恄榖偵墴偟崬傑傟傞偲奆尨弶偲摨偠乽崅揤尨乿偲偝傟偨偺偱偁傠偆丅乽傾儅僥儔僗乿傕摨偠宱夁偑峫偊傜傟傞丅
仠丂 嵳帠墹僯僯僊偼乽嵳帠榒崙墹斱栱屇乿傪宲偖傋偔揤崀偭偨
堷偒懕偒丄乽戝榓墹尃偲娭栧奀嫭偺娭學乿偺専徹傪懕偗傞丅
榘巙榒恖揱偵乽榒崙偼嵳惌擇廳峔憿偱偁偭偨乿偲偁傞丅懄偪乽彅惌帠墹偑嵳帠乮婼摴乯傪峴偆斱栱屇傪嫟棫偟偰榒崙墹偲偟偨乿乮榘巙榒恖揱乯丅乽嵳乿偑忋偱偁傞丅
偱偼丄乽巟攝幰僯僯僊乿偼乽惌帠墹乿偱偁傠偆偐乽嵳帠墹乿偱偁傠偆偐丅偦傟偼廬恇傪傒傟偽夝傞丅揤懛僯僯僊偵嫙曭偟偨屲晹恄偼揤帣壆柦乮偁傑偺偙傗偹偺傒偙偲丄拞恇巵偺慶乯傪昅摢偲偟偨嵳帠丒恄媉巌偱偁傞乮婭恄戙幍抜杮暥乯丅堦曽丄乽崙忳傝乿傪彑偪庢偭偨偲巚傢傟傞傾儅僥儔僗偺揤懛儂傾僇儕乮僯僯僊偺孼乯偵嫙曭偟偨屲晹恄偼揤捗杻椙乮偁傑偮傑傜丄暔晹巵偺慶乯傪昅摢偲偟偨惌帠丒孯帠巌偑庡偱偁傞乮愭戙媽帠杮婭丄摨彂偼乽儂傾僇儕偼僯僊僴儎僸偲摨堦乿偲偡傞偑丄昅幰偼嵦傜側偄丄慜挊乯丅僯僯僊偼嵳帠墹丄儂傾僇儕偼惌帠墹偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
廬偭偰乽僯僯僊偼嵳帠墹斱栱屇偵戙傢偭偰師偺嵳帠墹丄懄偪榒崙墹偲側傞傋偔揤崀偭偨乿偲夝庍偱偒傞丅揤崀傝愭乽拀巼偺擔岦乿偼嵳帠墹僯僯僊偵偲偭偰乽戞擇偺椙揷揔抧彫憅乿偲乽僗僒僲儝宯偲偺娚徴抧懷偱偁傝梫徴偺娭栧奀嫭乿偲乽僀僓僫僊宯偺惞抧彫屗乿傪傑偲傔偰帯傔傞嵳帠墹偵憡墳偟偄抧偩丅堦曽丄惌帠墹儂傾僇儕偼彫憅埲搶偼僯僯僊偵埾偹丄帺恎偼攷懡廃曈乮戞堦偺椙揷揔抧乯傪帯傔偰丄惣曽丒撿曽偺榒彅崙惌帠墹偲側偍攅傪嫞偭偰偄偨偲巚傢傟傞丅乽僯僯僊偺擔岦乿傪乽儂傾僇儕偺攷懡廃曈乿偵斾掕偡傞柧妋側棟桼偼柍偄丅
仠丂僯僯僊偼榒崙墹偵側傟偢撿惇傊
偲偙傠偑丄斱栱屇偐傜僯僯僊傊偺嵳帠墹乮廬偭偰榒崙墹乯偺忳埵丒岎戙偼幚尰偟側偐偭偨丅傑偩丄戝棎偼姰慡偵偼廂傑偭偰偄側偐偭偨偐傜偩丅嵳帠墹偲偼尵偊丄僯僯僊偼嵟戝惌帠惃椡乮儂傾僇儕乯懁偱偁偭偰丄拞棫揑拠嵸婡擻偺斱栱屇偵戙傢傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅寢壥揑偵僯僯僊堦懓偼懳嬬搝崙愴側偳偱儂傾僇儕孯偺堦梼傪扴偄丄偦偺堦晹傪嶱壓偵壛偊偰惌帠墹揑側惈奿偑嫮傑偭偨丅
偦偺崻嫆偼恄晲搶惇鏉偺乽崅憅壓乮偨偐偔傜偠乯偺愴婰乿乮恄晲婭乯偵偁傞丅愭戙媽帠杮婭偵傕摨堦撪梕偱婰偝傟丄椉巎椏偲傕乽崅憅壓側傞幰偑柌偵摫偐傟偰尒偮偗偨寱乮崙忳傝愴偱巊傢傟偨乯傪恄晲偵曭偭偨乿偲偁傞丅愭戙媽帠杮婭偱偼峏偵乽崅憅壓偼揤崄嶳柦乮偁傑偺偐偖傗傑偺傒偙偲丄埲壓僇僌儎儅乯偺屻偺柤偱偁傝丄懄偪儂傾僇儕偺巕丄旜挘暔晹巵偺慶偱偁傞乿偲偟偰偄傞丅偟偐偟丄儂傾僇儕偺巕僇僌儎儅偼僯僯僊偲摨帪戙偲峫偊傜傟丄乽崅憅壓愴婰乿偼杮棃僯僯僊孯丒僇僌儎儅孯偱嫟桳偝傟偨愴婰丄偦傟傪恄晲婭偵擖傟偨偺偼恄晲傪徧梘偡傞堊偱丄僯僯僊乮乣僼僉傾僄僘乯偺惉壥傪恄晲婭偵傑偲傔偨偲峫偊傞丅婰婭偵僯僯僊乣僼僉傾僄僘偺愴婰偑柍偄偐傜偩丅墳恄丒恗摽偺惉壥乮怴梾惇愴乯傪拠垼婭丒恄岟婭偵傑偲傔偨偲摨偠庤朄丄偲尵偊傞丅楌戙偺堦懓偺惉壥傪屻戙乮偁傞偄偼愭戙乯偵廤栺偟偰岅傞偙偲偼曇幰偺嵸検偺斖埻偱偁傠偆丅漵憿丒搻嶌偵偼摉偨傜側偄丅恄晲搶惇鏉偵嬨廈揱彸偑懡偔娷傑傟偰偄傞偲偄偆専徹曬崘傕懡偄丅摨偠棟桼偱偼側偄偐丅
丂埲忋丄僯僯僊堦懓偼僇僌儎儅孯傪嶱壓偵壛偊偰儂傾僇儕孯偺堦梼傪扴偄丄嵳帠偩偗偱側偔丄孯帠椡偲偟偰嬬搝崙愴傗撿曽惇愴偵実傢偭偨偲峫偊傜傟傞丅
仠丂僯僯僊乣恄晲偺撿惇偲抧柤堏怉丂
僯僯僊乣恄晲偼嬬搝崙愴側偳偱撿嬨廈偵墦惇偟丄搶増娸偺峀斖偺抧偵忋弎偺乽悈暯慄偐傜徃傞挬擔傪攓傔傞応強乿偑偁傞偙偲傪抦傝丄偦偙傕乽擔岦乿偲柤晅偗偨乮抧柤堏怉乯丅乽擔岦崙乿偺桼棃偱偁傠偆丅慿偭偰乽擔岦偼栧巌乿偺斾掕棟桼偑惓偟偐偭偨偙偲傪朤徹偟偰偄傞丅
乽妢嵐偺屼慜乮偐偝偝偺傒偝偒丄婰乯丄妢嫹偺嶈丄婭乿傕乽擔岦揤崀傝埲慜乮懳攏偺妢嵐乯乿偲乽崙扵偟埲屻乮撿嬨廈乯乿偺擇孮偑偁傞丅屻幰偑抧柤堏怉偱偁傠偆丅乽墦惇抧偱偺抧柤曄峏丒杮崙偺抧柤堏怉偼惇暈偺媀幃偺堦偮乿偲峫偊傜傟偰偄傞丅
丂
仠丂恄晲搶惇偲僯僯僊宯墹懓乛拞恇巵偺堦晹巆棷
偟偐偟丄嬬搝崙愴傕媥愴偵廔傢偭偨傛偆偱丄僯僯僊堦懓偺撿惇偼栚揑傪壥偨偣側偐偭偨丅恄晲傜偼栚昗傪曄偊丄娭栧奀嫭乮懍媧柤栧乯傪弌棫抧偲偟偰搶惇偵弌傞偙偲偵側偭偨丅恄晲傪慶偲偡傞戝榓墹尃偑偙偺抧偵偙偩傢傞棟桼偺戞嶰偱偁傞丅
偦偺搶惇偺嵺丄嵳帠宯僯僯僊堦懓偺堦晹傪娭栧奀嫭堟偵巆偟偨傛偆偩丅乽僗僒僲儝宯惌帠惃椡乮弌塤埲墦乯偵懳偡傞娚徴栶乿偩傠偆丅偦偺崻嫆偼丄僯僯僊偵嫙曭偟偰揤崀傝偟偨嵳帠丒恄媉巌偺巕懛乽拞恇巵乿偺擇暘偵偁傞丅偦偺庡懱偼恄晲搶惇偵廬偭偨偱偁傠偆丅側偤側傜丄戝榓墹尃偵偦偺巕懛偺乽拞恇乿偑尰傟傞偐傜偩乮恄晲婭丒悅恗婭側偳乯丅偟偐偟丄偦偺堦晹偼嬨廈偵巆偭偨偺偱偁傠偆丅偦偺巕懛偑榒崙戝恇偲偟偰尰傟傞偐傜偩丅懄偪乽榒崙墹偵攑暓傪憈忋偡傞拞恇巵乿偑嫃傞乮嬙柧婭552擭丄榒崙墹偱偁傞偙偲偼慜挊偱榑徹偟偨乯丅拞恇巵偑榒崙偵嫃傞偐傜丄偦偺庡嬝偺僯僯僊宯墹懓偺堦晹傕榒崙偵嫃偨偙偲傪朤徹偟偰偄傞丅懄偪丄榒崙偵巆偭偨僯僯僊宯墹懓偼拞恇巵傪廬偊丄儂傾僇儕宯榒崙墹乛僯僯僊宯嵳帠墹懓偺乽惌嵳擇廳峔憿乿偑懕偄偨偲巚傢傟傞乮嵳惌偱偼側偄乯丅
仠丂墳恄揤峜偼榒崙撪僯僯僊宯墹懓
墳恄偺懛堯嫳乮偄傫偓傚偆乯婭偵傕拞恇乮僯僯僊宯乯偺柤偑尰傟傞乮拞恇塆懐捗楢乮側偐偲傒偺偄偐偮傓傜偠乯丄拠垼丒恄岟婭偺嬨廈婰帠偵弶弌乯丅偦偺戝恇偺懡偔偼恗摽偑嬨廈偐傜壨撪偵堷偒楢傟偰峴偭偨幰払偺巕懛偱丄偙偺拞恇傕嬨廈宯丄懄偪榒崙拞恇宯偲巚傢傟傞丅偦偆偱偁傟偽丄偦偺庡嬝偺慶墳恄傕榒崙墹懓丄懄偪乽墳恄偼榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偱偁偭偨丄懄偪恄晲宯偱側偐偭偨偲偄偆壜擻惈偑崅偄丅偙傟傪専摙偡傞偺偑杮愡偺栚揑偱偁傞丅
(1) 丂恄岟峜岪偺怴梾恊惇乮369擭丄昅幰悇掕乯偼惉壥偑偁偭偨傕偺偺丄墹摑偑棎傟偰恄岟偼婱崙乮搶崙孯暫鈰婎抧偐乯傪嫀傝乮372擭崰丄摨乯丄屻擟偲偟偰墳恄偑婱崙偺墹偵棫偭偨丅墳恄偼恄岟峜岪偺峜巕偱偼側偄丅墳恄偺婰曵擭偐傜媡嶼偟偨惗擭丄恄岟峜岪偺惗擭廋惓乮擇攞擭楌丒姳巟2弰廋惓朄側偳乯偐傜丄椉幰偼摨悽戙傪帵偟偰偄傞乮慜挊乯丅嬨廈偱惗傑傟丄擄攇乮娭栧奀嫭嬤偔乯戝嬿媨偱曵偠偨乮墳恄婭乯丅師戙偺恗摽傕朙崙擄攇偵廧傫偱偄傞乮擄攇偺壧傪塺傫偱偄傞丄恗摽婰乯丅偙傟偼丄宨峴丒拠垼丒恄岟傜墦惇孯偺堦帪揑懾嵼偲柧傜偐偵堘偆丅乽墳恄偼尦乆嬨廈巵懓偺弌乿偺壜擻惈傪帵嵈偟偰偄傞丅傑偨丄墳恄偼晲撪廻擧傪婱崙偐傜捛偄弌偟偰偄傞乮墳恄婭乯丅墳恄偼僞儔僔宯丒廻擧宯乮恄岟丒晲撪廻擧側偳乯偱偼側偄徹偩丅
(2)丂 墳恄偼擔杮婱崙傪杒旍慜偐傜娭栧奀嫭堟偵堏偟偰偄傞偑丄娭栧奀嫭傪巟攝偟偰偄偨偺偼戝榓墹尃偱偼側偄丅榒崙偩丅崻嫆偺堦偮偼乽拠垼揤峜偑拀巼崄捙媨偵偄傞帪丄恄乮榒崙墹丄昅幰夝庍乯偺尵梩傪揱払偟偨偺偼嵐攇乮嶳岥乯偺導庡偺慶偩偭偨乿偲恄岟婭偵偁傞丅榒崙墹偼嵐攇乮嶳岥乯偵攝壓傪抲偄偰巟攝偟偰偄偨丅拀巼偲偺娫偺娭栧奀嫭傕巟攝偟偰偄偨偲峫偊傞偺偑帺慠偱偁傞丅堦曽丄墳恄偼擔杮婱崙墹偲偟偰朙崙擄攇乮婇媬敿搰搶乯偵媨傪抲偒丄娭栧奀嫭堟傪帺椞偲偟偰偄傞乮墳恄婭偺壧乯丅偙偺廳暋巟攝偼乽榒崙墹偼墳恄揤峜偺娭栧奀嫭巟攝傪嫋壜偟偆傞棫応偵偁偭偨乿偲峫偊傞偙偲偱惍崌偡傞丅
(3) 墳恄偼娭栧奀嫭堟傪搶崙孯偺拞宲婎抧偲偟偰丄榒崙丒戝榓楢崌偺梫乮偐側傔乯傪壥偨偟偨偲峫偊傜傟傞丅偙傟偵偼椉幰偺壦偗嫶偲側傝摼傞乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偑嵟揔偱偁傞丅偦傟偑昐嵪丒怴梾恇柉壔乮峀奐搚墹旇丄391擭乯偺戝愴壥偲側偭偨偲夝庍偱偒傞丅
(4) 偱偼丄側偤婰婭偼戝榓墹尃偵嬤偄榒崙撪僯僯僊宯堦懓偺偙偲傗墳恄偺弌帺傪婰偝側偄偺偐丠丂乽榒崙晄婰嵹乿偺曽恓偵怗傟傞偐傜偱偁傠偆丅乽拠垼偲恄岟偺峜巕亖墳恄乿偲偝傟偰偄傞丅
埲忋偐傜偺寢榑偼乽墳恄揤峜偼榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偱偁傞丅墳恄傪宲偄偩恗摽傕摨偠宯摑偲偟偰娭栧奀嫭堟朙崙擄攇偐傜搶惇偟偰丄壨撪偵墹尃傪妋棫偟偰恄晲宯丒悞恄宯丒恄岟宯傪巟攝偟偰戝榓墹尃傪嵞妋棫偟偨丅墳恄揤峜偼丄恄晲偵懕偔僯僯僊宯戝榓墹尃偺戞擇偺慶丄拞嫽偺慶偱偁傞乮墳恄偼僯僯僊偐傜200擭丄敧悽懛埵偵摉偨傞乯丅娭栧奀嫭偼戞擇偺慶墳恄揤峜偺屘抧偱偁傞丅乽戝榓墹尃偑娭栧奀嫭偵偙偩傢傞棟桼乿偺戞巐偲偟偰嫇偘傞丅
仠丂宲懱揤峜傕榒崙撪僯僯僊宯墹懓偺巕懛
丂戝榓墹尃偺墹摑偑晲楏偱抐愨偟偨偁偲丄墳恄屲悽懛偲偝傟傞宲懱偑梚棫偝傟偨丅墳恄偲摨偠乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偺巕懛偲偄偆偙偲偵側傞乮僯僯僊廫嶰悽懛憡摉乯丅偦傟傪朤徹偡傞偺偑乽宲懱偺巕埨娬揤峜偼拀巼孨斨堜椞傪廂扗偟偰丄榒崙岡嬥嫶乮朙崙岡嬥乯偵慗搒乿乮埨娬婭乯偱偁傞乮慜挊乯丅埨娬偺慶墳恄偼朙崙擄攇偺媨偵嫃偨偐傜丄朙崙傕乽榒崙僯僯僊宯墹懓乿偵強墢乮備偐傝乯偺抧偱偁傠偆丅
仠丂忋媨墹傕榒崙撪僯僯僊宯墹懓
乽忋媨墹乮惞摽懢巕偺晝乯偼榒崙偺拞悤墹懓偩偭偨偑榒崙偐傜撈棫偟偨乿偲慜挊偱専徹偟偨乮惓憅堾屼暔乽朄壺媊慲乮傎偭偗偓偟傚乯幨杮乿側偳乯丅偙偺忋媨墹壠偵傕拞恇巵乮姍懌丄僯僯僊宯乯偑嫃傞乮峜嬌婭乯丅乽忋媨墹偼榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偱偁偭偨偙偲傪帵偟偰偄傞乮僯僯僊廫幍悽懛憡摉乯丅榒崙墹懓偱偁傞偵傕娭傢傜偢丄戝榓墹尃偵嬤偯偒丄嵟廔揑偵戝榓墹尃偲崌懱偟偨偙偲偑偦傟傪徹偟偰偄傞乮壋枻偺曄乯丅
偟偐偟丄忋媨墹偼僯僯僊宯乮嵳帠宯乯偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄暓嫵偵孹搢偟偰偄傞丅榒崙偐傜撈棫偟偰乽朄嫽擭崋乿傪寶偰丄朄峜傪帺徧偟偰偄傞乮朄棽帥庍夀嶰懜憸岝攚柫乯丅榒崙撪嵳帠娗彾傪曻婞偟偰撈棫偟偨偺偩傠偆丅堷偒楢傟偰棃偨拞恇姍懌傕忋媨墹壠撪偱恄媉攲廇擟傪帿戅偟偰偄傞乮峜嬌婭乯丅榒崙撪僯僯僊宯偺嵳帠丒恄媉庡棳攈乮枖偼媽庣攈乯偼榒崙撪偵巆偭偨偺偱偁傠偆丅
仠丂揤晲偼榒崙撪儂傾僇儕宯墹懓偺嫵堢傪庴偗偨
揤晲偺弌帺傕媈栤偑偁偭偨丅戝榓婑傝偺懁柺偲榒崙婑傝偺懁柺偑崿嵼偟偰丄榒崙墹偺掜愢傕偁傞乮戝峜掜丄揤抭婭乯丅忋媨墹壠偺曮峜彈乮峜嬌乛惸柧丄忋媨墹懛乯偼峜巕偺堦恖拞戝孼峜巕傪搶媨偵丄傕偆堦恖戝奀恖峜巕傪晲恖偵堢偰傛偆偲偟偨丅埲壓丄揤晲偺梴堢娐嫬偵偮偄偰専摙偡傞丅
(1) 忋媨墹壠偼嵳帠宯側偺偱丄偦偺傛偆側乽晲恖嫵堢乿偺娐嫬偼柍偐偭偨傛偆偩丅曮峜彈偼偦偺梴堢傪戝奀乮偍偍偁傑乯巵偵棅傫偩乮榒崙撪僯僯僊宯墹懓宱桼偐乯丅戝奀巵偼奀帠丄庩偵奀孯偵挿偗偨巵懓偱丄偦偺慶偼儂傾僇儕偱偁傞乮怴愶惄巵榐乯丅儂傾僇儕宯榒崙墹壠偵嬤偄丅戝奀巵偼戝奀恖峜巕傪乽榒崙撪儂傾僇儕宯墹懓偲偟偰偺梴堢乿傪巤偟偨偱偁傠偆丅偦偺崻嫆偼戝奀乮偍偍偁傑乯巵朸偑揤晲偺憭媀偱恜惗乮傒傇丄梴堢妡傝乯偲偟偰挗帿傪弎傋偰偄傞偐傜丄偲偝傟偰偄傞乮揤晲婭枛旜乯丅
(2) 戝奀恖峜巕偼乽榒崙儂傾僇儕宯墹懓乿偲峫偊傜傟傞傛偆側堢偪曽傪偟偰偄傞丅戝奀恖峜巕偼揤晲揤峜偲側偭偨屻丄乽榒崙偺懳搨懳摍奜岎乿傪宲彸偟傛偆偲偟偰偄傞丅柵朣偟偨榒崙傪戝榓偵嵞嫽偟傛偆偲乽榒乮傗傑偲乯乿乽戝榒乮偍偍傗傑偲乯乿偺怴偨側摉偰帤傪戝榓偱巊傢偣偰偄傞丅
(3)丂偟偐偟丄榒崙撪僯僯僊宯偺塭嬁傕庴偗偰偄傞丅椺偊偽丄戝奀恖峜巕偼恜怽偺棎偺嵺丄埳惃恄媨傪梱攓偟丄揤晲揤峜偵側偭偰偐傜偼崙壠恄摴傪惍旛偟偰偄傞丅懄偪丄戝奀恖峜巕偼忋媨墹壠偺暓嫵巜岦偲堎側傝丄榒崙偺恄媉宯乮僯僯僊宯乯偵栠偭偰偄傞丅榒崙偺恄媉傪巌偭偨偺偼拞恇巵傗杕晹巵偱丄偄偢傟傕僯僯僊宯巵懓偱偁傞丅偦偺庡嬝偺乽僯僯僊宯墹懓乿傕榒崙撪偵巆懚偟偰偄偨壜擻惈傪帵嵈偟偰偄傞丅戝奀恖峜巕偼丄偦傟傜乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偺堦堳偲偟偰傕堢偰傜傟偨壜擻惈偑偁傞乮僯僯僊擇廫悽懛憡摉乯丅
(4)戝榓墹尃偼朙崙岡嬥嫶慗搒乮埨娬婭乯偺寢壥丄奜愂慼変巵偺寣柆偵敍傜傟偰丄幚幙慼変巵偵庢傝崬傑傟偰偟傑偭偨丅忋媨墹壠傕偦偆側傝偮偮偁傞丅榒崙撪僯僯僊宯墹懓偵憲傝崬傫偩戝奀恖峜巕傕婛偵榒崙撪廆憸巵偺斳傪傕傜偭偰偄傞丅偦偺撪丄榒崙墹壠偺斳傗暔晹巵偺斳傪栣偆偐傕偟傟側偄丅戝奀恖峜巕傪忋媨墹壠偵堷偒棷傔傞崶堶惌嶔偑昁梫丄偲曮峜彈偼峫偊偨傛偆偩丅拞戝孼峜巕偺柡4恖傪師乆偵斳偲偟偰憲傝崬傫偩丅偦傟偑昁梫側掱丄榒崙撪僯僯僊宯丒儂傾僇儕宯偺戝奀恖峜巕偵懳偡傞婜懸偑戝偒偐偭偨偺偩傠偆丅
(5)丂榒崙偵偲偭偰丄戝榓墹尃偼嵟嫮偺摨柨崙偱偁傝丄偦傟屘偵戝榓墹尃傪恎嬤偵堷偒晅偗塭嬁椡傪媦傏偡偙偲傕戝愗偱偁傞丅慼変巵偺戜摢偑偦傟傪慾傫偱偒偨偑丄壋枻偺曄偱忬嫷偑曄傢偭偨乮忋媨墹壠偲戝榓墹尃偺崌懱乯丅偩偐傜偲偄偭偰捈偪偵榒崙偑戝榓墹尃傪庡摫偱偒偨栿偱偼側偄丅榒崙丒戝榓憃曽偺婜懸傪扴偭偰搊応偟偨偺偑乽榒崙偲戝榓墹尃傪偮側偖壦偗嫶偲側傝摼傞戝奀恖峜巕乿偩乮岶摽婭乯丅戝榓墹尃懁傕乽峜掜丒戝峜掜乮揤抭婭擇擭忦埲崀乯乿偲帩偪偁偘偰偄傞丅
埲忋丄揤晲偼乽榒崙傪弌偨僯僯僊宯墹懓忋媨墹乿偺慭懛偩偑乽榒崙撪儂傾僇儕宯墹懓乿偺梴堢偲乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偺梴堢偺椉曽傪庴偗丄乽榒崙墹懓乿偲乽戝榓墹懓乿偺椉柺惈傪帩偭偰偄傞丅乽榒崙墹偺掜偱偼側偄乿偲峫偊傞偺偑懨摉偩丅
丂
仠丂戝榓墹尃偼僯僯僊宯偺乽枩悽堦宯乿
丂戝榓墹尃偺墹摑偑棎傟偨帪偵乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偑墳恄揤峜丒宲懱揤峜傪攜弌偟偨丄偲忋弎偟偨丅偦傟偼乽榒崙撪僯僯僊嵳帠墹壠偼戝榓墹尃偺杮壠乿傪堄枴偡傞偺偩傠偆偐丅偟偐偟丄偙傟偼榒崙偲戝榓墹尃乮恄晲乣揤晲乯偺摨柨崙揑娭學乽榒崙墹壠亞戝榓墹尃乿偲柕弬偡傞偐傜丄乽榒崙撪僯僯僊嵳帠墹懓偼戝榓墹尃偺暘壠乮巟懓乯乿偲娤傞傋偒偩傠偆丅暘壠偐傜杮壠偺摉庡偑弌傞偙偲偼彮側偔側偄丅
儂傾僇儕帺恎偼榒崙乮彈墹斱栱屇乯偺彅惌帠墹偺昅摢偩偭偨偲峫偊傜傟傞偑丄偦偺巕懛偼戜梌偺屻乽搶惇60擭乿乽惣惇40擭乿偱榒崙傪摑堦偟丄榒崙墹偲側偭偨丅崻嫆偼丄榒墹晲偺忋昞暥偲婰婭偺懳墳偵偁傞丅堦曽丄僯僯僊偼榒崙墹偲側傞傋偔嵳帠墹偲偟偰揤崀偭偨偑揔傢偢丄搶惇偟偰戝榓墹尃傪妋棫偟偨丅椉幰偼傾儅僥儔僗宯偺孼掜崙偲偟偰偍屳偄偵曗姰偟側偑傜楍搰傪惂偟偨偲夝庍偱偒傞丅偙偺椉幰偺娭學傪400擭娫偵榡偭偰丄堐帩偟丄挷惍偟丄曗嫮偟偨偺偑乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偩偭偨偲峫偊傞丅偙偺娫丄榒崙偺杮嫆偼攷懡乣埰庤孲偲峫偊傜傟丄娭栧奀嫭堟乮朙慜乯偺乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偼掱椙偄嫍棧乮桳傞掱搙偺撈棫惈偲嫤椡娭學乯偲曽岦乮悾屗撪奀偵柺偟丄戝榓偲楢実乯傪曐偭偨偲峫偊傞丅
寢榑偲偟偰丄乽僯僯僊宯戝榓墹尃偼墹摑偑棎傟偨傝抐愨偡傞搙偵榒崙撪僯僯僊宯墹懓偐傜揤峜偑憲傝崬傑傟偰僯僯僊宯墹摑傪偮側偄偩乿偲偄偆堄枴偱丄乽戝榓墹尃偼僯僯僊宯枩悽堦宯乿乮摨懓墹摑乯偲徧偡傞偙偲偑偱偒傞丅扐偟丄擔杮彂婭偼搨偲偺娭學偐傜乽榒崙晄婰嵹乿偲偟丄乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓晄婰嵹乿偲偟偰偄傞偐傜丄乽恄晲宯枩悽堦宯乿偲偟偰偄傞丅乽恄晲捈宯乿偼偲傕偐偔乽恄晲偲偦偺摨懓墹摑乿偲棟夝偡傟偽戝嬝偼漵憿丒婾傝偱偼側偄丅
埲忋偐傜丄乽墳恄丒宲懱丒忋媨墹丒揤晲偺弌帺偺晄徻揰乿偼乽娭栧奀嫭堟傪杮嫆偲偟偨榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿偺夝庍偱奣偹夝徚偱偒丄`崙偲戝榓墹尃偺壦偗嫶苽祩膩u戝榓墹尃偺枩悽堦宯乮撪幚偼僯僯僊宯摨懓堦宯乯乿偺庡挘偺攚宨傪側偡丄偲峫偊傞丅
埲忋娭栧奀嫭偲戝榓墹尃偺娭學偐傜丄慜挊偱晄徻偲偟偨揰傪曗姰偟偰丄榒崙偲擔杮偺娭學捠巎偑尒偊偰偔傞偲峫偊傞丅
[拲1]丂慜挊丂乽榒崙捠巎乿崅嫶捠丂尨彂朳丂2015擭丂丂憹曗斉乮怴撪梕乯傪僱僢僩岞奐拞丂2016丏6乣11丂乽 http://wakoku701.jp 乿丂杮彫榑偺堦晹傕岞奐偵壛偊偨丅
[拲2] 榋搰偺斾掕丂丂惣擔杮傪拞怱偵廫悢岓曗抧傪斾妑専徹偺寢壥丄娭栧奀嫭杒惣偺榋搰傪慖傃丄偙傟傪惛嵏偟偨丅斾掕寢壥偼屆帠婰偺婰嵹弴偵丄
(1) 乽媑旛帣搰乮偒傃偺偙偠傑乯丄枓偺柤寶擔曽暿乮偨偗傂偐偨傢偗乯乿偺岓曗丗丂尰嵼柤乽抾偺巕搰乮偨偗偺偙偠傑乯乿乮壓娭旻搰偺杒惣椬乯丄尦偼乽枓偺柤乿偵桼棃偡傞乽寶帣搰乮偨偗偺偙偠傑乯乿偲峫偊傜傟傞丅
(2) 師乽彫摛搰乮偁偢偒偠傑乯乿偺岓曗丗丂尰嵼柤乽攏搰乮偆傑偟傑乯乿乮惣乯偲乽榋楢搰乮傓偮傟偠傑乯乿乮搶乯偑暲傫偱偄傞丅榋楢搰偼搰宍偑乽偁偢偒宍乿偱偁傝丄墳恄婭偺壧偵乽偁偢偒偟傑丄偄傗傆偨側傜傃乿偲壧傢傟傞偵憡墳偟偄乽擇暲傃乿偱丄擇偮偱堦偮偲悢偊傞丄(1)偺杒惣椬)丅
(3) 師乽戝搰乮偍傎偠傑乯乿偺岓曗丗丂尰嵼柤乽棔搰乮偁偄偺偟傑乯乿乮(2)偺杒惣椬乯丄乽拠垼婭乿偵偁傞乽垻暵乮偁傊乯搰乿傕偙傟偵斾掕偝傟偰偄傞乮乣峕屗婜峫徹乯丅
(4) 師乽彈搰乮傂傔偟傑乯乿偺岓曗丗丂尰嵼柤乽彈搰乮傔偟傑乯乿乮(3)偺杒惣椬乯乿丄摨柤偩偐傜斲掕偺偟傛偆偑側偄丅
(5)丂師乽抦鎑搰乮偪偐偺偟傑乯丄枓偺柤傪揤擵擡抝乮偁傔偺偍偟偍乯乿偺岓曗丗丂尰嵼柤乽抝搰乮偍偟傑乯乿乮(4)偲擇暲傃乯丄乽枓偺柤乿偵桼棃偡傞偲尵偊傞丅
(6) 師乽椉帣搰乮傆偨偙偠傑乯乿偺岓曗丗丂尰嵼柤乽奧堜搰乮傆偨偍偄偟傑乯乿乮(1)偺杒惣乯丄擇偮偺曯傪傕偪丄斾掕抧偲偟偰傆偝傢偟偄[拲3]丅
[拲3]丂乽嶳岥導晽搚帍乿13姫柧帯37擭丂丂暅崗斉丂9姫乽奧堜搰乿偺崁偵乽屆帠婰偺椉帣搰丒揤椉壆乮暿柤乯偼奧堜搰乿偲偁傞丅崻嫆偼愭峴峫徹乮杮嫃愰挿偺峫徹丄乽挿栧崙巙乿側偳乯傪嫇偘丄榋搰偺斾掕傕沀嬋偵帵嵈偟偰偄傞偑帇揰偑恄岟峜岪偵曃傝杮榑偵偲偭偰廩暘偱側偄丅
[拲4] 彫屗旻搰愢丂乽巹峫丒旻搰暔岅 I乣II乿惣堜寬堦榊丂屆揷巎妛夛曬No71崋乮2005乯懠
[拲5] 擔岦彫憅愢丂乽http://koji-mhr.sakura.ne.jp/PDF-1/1-1-4.pdf乿偵帵嵈傪庴偗偨丅
丂丂
屲挊 僽儘僌乽愮擭偺岆撉乿丂岞奐拞 _____________________________
丂
巐挊乽堦恾偱傢偐傞擔杮屆戙巎乿岞奐拞 _____________________________
丂
丂
丂
婑峞暥乽榒崙撪僯僯僊宯墹懓乿乮2017乯 丂丂丂丂
丂
弶挊乽榒崙捠巎乿婛姧丒
丂
俫俷俵俤 丂 擭昞丒抧恾 丂 嶲峫暥專 _____________________
