.
.
.
.
.
�����u�`���ʎj�v�@���p����
�@�����@�ʁ@�����[�@2015�N
�i���쌠���ہj
���p�Y���������o��܂�
���b���҂���������
.
.
.
.
��9�@�`������@�@
�u�E������59�N�ɘ`���ƗF�D�����v�i�O���j�L�A�O�o�j�Ƃ��������A�O���j�L�̋L�q�̗��ꂩ�炱�̘`���͑��k�ߍ��̋߂��̔����`���ł��낤�B�u�E�����͘`���ƈꌳ�I�ȊO�����ł����v�Ƃ́u�`���͓��ꂳ�ꂽ�v���Ӗ�����̂��낤���B�������A����͑O�q�u�`���̘`�z���v�i�㊿��57�N���j�̍�(3)�́u�`���͓���ł��Ă��Ȃ��v�Ɩ�������B���炭�͒P���ł͂Ȃ��A�u�`���͔�������̂ɓ���̉ߒ��ɂ��������`���̋ɓ�E�̘`�z��������I�ɓƗ���錾���ď���ɒ����Ɍ��g�����v�Ȃǂ̑Η��I�W�����������B
���ꂩ��50�N���̂��A�`���͌㊿�Ɍ��g�����A�ƌ㊿���ɂ���B
�㊿���@�`�`107�N���@
�u�`����
[14]
�����i�����j���A�����i���������j160�l����A�������肤�v
�㊿���@����I107�N��
�u�`���g�������킵���v
�u���̍��i�`���j�͖{�i���Ɓj�����j�q���Ȃ��ĉ��ƂȂ��A�Z�i�Ƃǁj�܂邱��7�A80�N�Ȃ�B�`�����ꑊ�U�����邱�Ɨ�N�B���Ȃ킿�ꏗ�q���������ĉ��ƂȂ��B���Â��Ĕږ�ĂƂ����A�A�A�v
�㊿��
�u���E��̊ԁA�`���嗐�A�A�A��N��Ȃ��A�A�A�v
�u�`���͗����O�ɒj�q�̘`���������āA���g���Ē��v���肢�o���v�Ƃ́u�`���͓��ꂳ�ꂽ�v�ƍl������B�����ł͓��ꎞ���̂������A�u�`���嗐�v�ɂ��Ă͌�q����B�㊿����i147�N�`167�N�j�E���i168�N�`189�N�j�̔N�オ�킩���Ă��邩��u���̑O�̒j��������70�`80�N�ԁv����ɓ���N����t�Z���Ă݂� [16]�B���̌��ʂ𗪋L����Ɓu����80�N���A�`���͒j���ɂ���ē��ꂳ��A107�N�ɘ`�������������g�����B�����150�N�`160�N�܂ő��������A���̌�嗐������20�N�O�㑱�����i160�N�`180�N�j�v�ƂȂ�B
[14] �u�`�����v�@�㊿���ł́u�`�����v�����A�w�ˉ��x�Ɉ��p����Ă���㊿���ɂ́u�`�ʏ㍑���v�Ƃ���A���{�ɂ��u�`�ʓy���v�u�`�ʓy�n���v�u�`�ʍ��v�Ȃǂ�����ȂNjc�_���c���Ă���i�u�`�l�`�̗p��̌����v�@�O�ؑ��Y�@����o�Ł@1984�N�j�B�����A�������́u��������`�����ł������v�ƌ��_���Ă���i�u�`���̏o���v�����萶�j�B���ɒ����j���ɏo�Ă���u�`�����v�͑v���́u�`�������v�ł���B
[15] �u鰎u�`�l�`�v�@�����̐��j�w�O���u�x���́u鰏��v�̓��Γ`�`�l���̗��́@280�N-290�N�����̕ҁA�j���ɋ߂��N��ɏ����ꂽ�B
[16] �u����N��v�@�㊿����i147�N�`167�N�j�E���i168�N�`189�N�j�́u����̗Ⴆ�Β�����157�N����嗐���J�n�����v�Ƃ���ƁA���̑O�A70�`80�N�Ԃ��j���̓��ꎞ��������A����N��́A�u157�N��70�`80�N�O�A����77�N�`87�N�v���B�`���������i107�N���g�j�͐����̘`�������B
��50�@�הn�䍑�̌��W�g�H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2012.1�@�@���M�j
�ږ�Č�̂��Ƃ�鰎u�ɋL����Ă���B
鰎u�`�l�`����
�u�ږ�ĈȂ��Ď����i250�N���A�k�j�j�A�傢�ən������A�A�A�X�ɒj���������Ă�������������A�A�A�ږ�Ă̏@����^�i�ʐ��ł͑�^�A�ȉ��ʐ��ɏ]���j�A�N�\�O�𗧂Ăĉ��ƈׂ��A���ɒ�܂��A�A�A��^�A�A�A���i鰎g�����j�����҂�𑗂����ށA�������i���z�j���w��A�A�A�i�����O�\�l�A����Ȃǂ��j�v���v
����A�_���I�ɂ́u�_���c�@�͔ږ�Ė��͑�^�v����������悤�Ȏ��̕ҎҒ����ڂ��Ă���B
�_���I�@
�u�W�̋N�����i�c������j�ɞH���A�w����̑n2�N�i266�N�j�A�A�A�`�̏����A����d�˂čv�������ށx�Ɓv
�������A�u�_���c�@���`�̏����v�Ƃ͏����Ă��Ȃ��B�����łȂ����Ƃ�Ҏ҂͒����j������m���Ă����ƍl������B�ږ�āE��^�i3���I�A��f�̏����͎���I�ɑ�^�ƍl�����Ă���j�Ɛ_���c�@�i400�N���A��l�͎Q�Ɓj�Ƃ͎��オ�Ⴂ������B�_���c�@�̔N���k�点��ׂ̎����Ɏg�����ƍl������B�����ɗ��߂��Ƃ��낪�Ҏ҂̍H�v�ł��낤�B
���̋L���Ɋ֘A���Ē��ڂ����͓̂��N�̕ʂ̎j���A�W������I���B�N�����Ɣ�ׂĂ݂悤�B
�W������I
�u�n2�N�i266�N�j�A�A�A�`�l������ĕ����������v
�_���I�̈����W�̋N����
�u�n2�N�i266�N�j�A�A�A�`�i���j�̏����A�A�A�v�������ށv�i�Čf�j
�_���I�̈��p�Ɠ��N�œ����W�̕���֘A�L��������A�͓��ꎖ�т��Ƃ���̂�������B�������W���͘`�łȂ��u�`�l�v�A���v�Ƃ͈قȂ�u�����v�ł���B�u�����v�ƂȂ��Ă���̂́A�W�Ƃ܂����v�W�������Ă��Ȃ����A���ꂩ�玝�Ƃ��Ƃ���g�߂ƍl������B�����͌֎��̈Ӗ��������č����̐��̒��v�g�ɂ́u�v���A���v���A�v�����v�Ə���������i�u�����v�E�u�v���v�E�u���v�̎g�������ɂ��Ă͑�͂ŏq�ׂ�j�B���Ȃ킿�W���́u�`�l�����������������v�͑�^�́u���v�v���W�g�ł͂Ȃ��B�u���N�̕ʂ̌��g�v���B�ł́u�`���ƕʂ̘`�l���������댯��`���ĕʁX�Ɍ��g�v�����̂��낤���B�����ł͂Ȃ��u���v����`�i���j�����i��^�j�̌��g�v�Ɂu�`���Ƃ͕ʂ́A�������v���Ă��Ȃ��`��̍��̌��g�v���u���s�v�����A�ƍl����������R���B���̍����́A�ږ�Ă�鰂̍c��Ɂu����i�`�j��l���V���i�����ԁj���A�A�A�v�i鰎u�`�l�`�j�ƁA�`�����E�`��̎w���҂Ƃ��Ę`���O�`�l�̖ʓ|�����邱�Ƃ�@����Ă��邩�炾 [10]�B
�`���̎��ӂɂ͘`��̍��͑������A����I�ɋL�������̍��ƂȂ�Ɓu�`��ōő�̐l�����ւ�הn�䍑�v�i鰎u�`�l�`�j�̉\���������B���̐�������������u�����͎הn�䍑�̌��g�ɒ��ڐڂ����v���ƂɂȂ�B��洂��u鰗��v��Ҏ[���Ă���270�N���ȑO�̎��тł���B�u����Ȃ�����ƑO����הn�䍑�̏�����ɓ`����Ă��ĕs�v�c�͖����B����ł���洂�鰗��̋L���Ɏהn�䍑���̗p���Ȃ������B�����O�����w�`���x�Ƃ͕ʁA�ƒm���Ă������炾�B�v�Ɛ��肳���B
���̋L���ɂ��Ắu�O����~���Ƃ̊W�v�����������߂ĐG���B
[10]�@���s�g�@ ��������́u���g��ʂ��鏊�O�\���v�i鰎u�`�l�`�j���낤�B�O�\�����ʁX�Ɍ��g�����Ƃ͍l�����Ȃ��B���s�g�A�A���̌��g�⌣�㕨�ƐM���̗a���Ȃǂ����������A�ƍl������B�@
��5�E7�E8�͂ŏq�ׂ邪�A�`���͌�N���������g�ɗY�����E���Ò��E�F�����̐��s�g�̓��s���������悤���B�W���͂��̚���ƂȂ�L���Ɖ��߂ł���B���̊��e�ȊO���w���͂��`���̒��N�̏@�卑�p���̌����͂��낤�A�ƍl����B
��65�@㕌��̍Վ�����@�_���͑n�n�҂ł͂Ȃ��@�@�@�@�@�@�i2011.10�@���@2013.2�@���M�j
㕌��Վ������͋E���݂̂Ȃ炸���C����g���Ȑ��ɂ܂ŋy�Ԕ͈͂���W�܂����l�����A����������Ηe�n�̎���h�����ꂽ�l�X�ōs���A���̐��ʂł���O����~���Ƃ��̍Վ��`����e�n�Ɏ����A�����A�ƍl�����Ă���B���̂悤�ȍL��Վ������̎哱�҂͂��ꂾ�낤���H[3]�O��
(1)
㕌��Õ��̑n�n���i200�`220�N���j�ɂ͑�a�ɂ̓j�M�n���q�ꑰ�������i�Ƃ݁A����s�A�ޗǖ~�n�̓���j�ɋ����B�_�������ɗ����������̂������a�̑�\�i�̐����e���ł��낤�B���������̐��͌��͑�a�~�n���o�邱�Ƃ͂Ȃ��A�L��̍Վ��I���Ђ������Ă����Ƃ͍l�����Ȃ��B
(2)
�����̖k�̎O�ցi�ޗǖ~�n�̓��쓌�j�ɂ͎O�ցE�啨��_�ꑰ�������B�O�ֈꑰ�͐����e���I�ɂ͎�̂ł��A�j�M�n���q�ɖłڂ���邱�Ƃ��Ȃ��n�_�n�̎O�_�ƃX�T�m���n�̑啨��_�̍Վ����Ђ��ێ����Ă����ƍl������B�啨��_�͗e�n�ɍ�����������������A�ƋL�I�ɂ���A㕌������̎哱�҂̎��i�͂��肻�����B�e�n�̐������B�͂��̍Վ����Ђɏ]���Ĕz����㕌��ɑ��荞�Ǝv����B㕌��Վ�����͎O�։������哱�������̂ł��낤�B
(3) �_���̓j�M�n���q�ꑰ�𐧈����Ē�����D���Ė{���n�Ƃ����i�֗]�j�B�������A�_�����ׂ̎O�ֈꑰ�̒n��D�����ƂȂ��A������{���Ƃ���啨��_�ꑰ�̖����@�Ƃ����B��ʂɁu���鉤���̖����@�E�܂ɂ����v�Ƃ���ꍇ�A�O�̃P�[�X������B�u�����̏ے��i�㉺�̏�j�v�u�����̏i�㉺�̉��j�v�u�e�����J�i�Γ��j�v���B�_���̏ꍇ�͂��̌�̎O�։����Ƃ̊W���݂�Ɓu�e���v�Ǝv����B
(4)
�_������������A�q���p�����V���V�c�ƂȂ����̎O�ւ�{���n�ɂ����B�O�։����̓���ɂ��Ȃ������T�����͕�����Ȃ��B�_���ꑰ�ɂƂ��ĎO�ֈꑰ�Ƃ̘A�g�͐����ʂł̃����b�g���������A�ƍl������B
(5)
���j����Ƃ́A�_���n3�n��4����i��90�N�j�A��9��J���V�c�܂ł̓V�c�Ƃ����B���ʊW�̕��͂���A��������O�։����ƊW���[���Ƃ����i�ϐ��A[2]�O�� �j�B
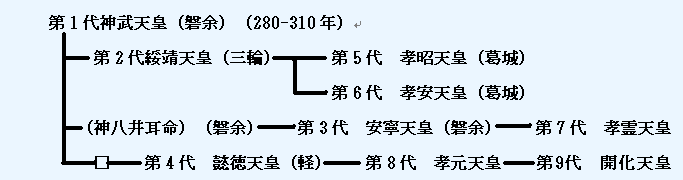
�������A�_�������8��܂ł̓V�c��˂͉~�u�܂��͎R�`�ł����B��B�̓`��������ēV�ƌn���������Ă���悤���B�_���n��260�N���Ɏn�܂����Ƃ�����㕌��̑O����~�������̎哱�҂ł͂Ȃ��ƕM�҂͍l����B
(6) ��9��@�J���V�c�͍F���V�c�̎q�A���j����̍Ō�Ƃ����B�_���n�ŏ��߂Č�˂͑O����~���ł���A�ȍ~����̐��_�`�q�B�V�c�i��31��j�܂ŗ�O�i���N�E�Y���E����j�������Ă��ׂđO����~���ł����B�_���n�Ƃ��čŏ��ɑO����~����������A����̐��_�n�Ɉ����p���ł���`���B
(7)
��10�㐒�_�V�c�͊J���V�c�̎q�Ƃ���邪�A�a���ɃC����������C�������Ƃ��Ă�A�_�����V���n�ƈقȂ鉤���Ƃ�������L�͂�(�}�P����̓n���n�Ƃ�������������j�B�������A�_���n�Ɛ��_�n�Ɉ��ʊW���������͎̂j���̂悤���B�J���V�c�̑�����P�����m�V�c�̍@�ƂȂ����ڏq������i�L�I�j�B
���_�̓A�}�e���X���J���Ă���B�n���n�ƍl�����鐒�_���Ȃ��A�}�e���X���J�����̂��B�w�i�Ɂu�u�a����l�����������v�i���_�I�A�n���n�̂����炵���u�a���j�Ƃ���������������A���_�V�c�͍Վ��ɖv�����A�V�Ƒ�_�E�`�卑���E�啨��_���J�蒼�����i���_�I�j�B���_�V�c�̓A�}�e���X���J�铝���Վ����ƂȂ����Ǝv����B
(8)
��11�㐂�m�V�c���������a���ɃC���������_�̒��n�ƍl������B��͂�V�Ƒ�_���J��ɐ��_�{��n�n�����Ƃ����B㕌��Վ����Ђ͐_�X��Z�����Ȃ���O�n�A�_���n�A���_�n�ւƈ����p���ꂽ�悤���B
(9)
��12��i�s�E�i��13�㐬���j�E��14�㒇���͒��N����ő�a�𗯎�ɂ��Ă��邩��A�Վ����ł͂Ȃ������悤���B�����ł͏Ȃ���q����B
(10)�@�����V�c�̐_���c�@�͋�B���킩���a�ɋA�҂��邪�A���ޏ��̎����������A�Վ��̎哱�҂������A�Ɖ��߂ł���i���́j�B
(11)�@�����V�c�̍c�q�͐_���c�@�ƂƂ��ɋ�B�����a�ɋA�҂��āA���_�����x�z���ɒu�����i���́j�B���R���_���̓V�Ƒ�_���܂߂������Վ������p�������ƍl����B���̒����n�̉����̏�ɏ�����̂���͂��B����A�҂�����a�R�̉��A�m�������i���͎Q�Ɓj�B�m���ƌ�p�҂����R�Վ������p�������ƍl����B㕌��ȗ��̑O����~���ł��鉞�_�V�c�ˁ`�m���V�c�ˁi�ő�j�����̏��B
�ȏ�Վ����̐��ڂ��܂Ƃ߂�ƁA�u�_���V�c��㕌��Õ��̑n�n�҂ł͂Ȃ��B�_���n�͐����I�ɂ͎O�n�ɋ߂Â������A�Վ��I�ɂ͋�B�n���ێ����đO����~�����̗p���Ȃ������B�ނ���A���Ƃ���鐒�_���̕����O����~���ɏے������㕌��̎O�n�Վ����Ɛ_���̓V�ƌn��Z�����čՎ������Ƃ��Ċg�債�A���̍Վ������͐��_�n�E�����n�E�m���n�̑�a�����������Ɍp������Ă����v�B���̗��R�́u��a��㕌��ȗ��̍Վ����y�I�ȓ`���v���낤�B�Վ��𗝉����������ď��߂đ�a�̐��������܂��^�̂��낤�B
��66
���{���I�̔N���C���@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2012.2�@���M�j
�_���I�ȑO�̓��{���I�N���i�c�I�j�ɂ͌֒��⑀�삪����A���̏C���@���x������Ă���B
(1)
�Î��L�̓V�c���N���x�͊C�O�j���Ƃ̐������������M�����������Ƃ����B�u�L���N�v�Ɨ����B�L���N�͐��_�V�c���琄�ÓV�c�܂ł̑����ɋL����Ă���B�������_�Ƃ��Čv�Z���邱�Ƃ�����
[4] �B
(2)
���V�c�Ɉُ�Ȓ����̋L�^������B�u�t�H�ɍ𐔂���2�{�N����v�Ɖ��߂���āA��������N�N��Ɖ��߂��邱�Ƃ����݂���B�Ⴆ�A�_���c�@���N�N��S��50�ɁA���_�V�c�S�\�i�Î��L�͕S�O�\�j��55�i�`65�j�Ƃ���B���̕��������߂̍����̈�Ƃ���Ă���B
鰎u�`�l�`��
�u�y鰗��H�F���̑��A���Ύl�߂�m�炸�A�A�t�k�H�����v���ĔN�I�ƈׂ��z�v
(3)
���x�ŋL�q����Ă���ꍇ�ɂ͂Q��(120�N)�J�艺���Ă݂�B�O���j���Ɛ�������ꍇ�������B�Ⴆ�A�_���I��܌ܔN�́u�S�ϏьÉ��I�v�Ƃ���̂͐�������375�N�ƕS�ώj�����画���Ă���B
�ȏ�ƂĐ�ł͂Ȃ��A�X�ɑ��Ƃ̐����������Ȃ��玎�s���낷�邵���Ȃ��B�������A�{���y�і{�����ˋ����镶���ł͗D�悵�ď�̏��̏C�������݂Ă���B
[4]�@�L���N�@�@�Î��L�̓V�c���N�͋L����Ă��Ȃ����̂ƁA���x�ŋL���ꂽ���̂����L�̂悤�ɂ���i����ŕ\�L�j�B�L���ꂽ���̂͊C�O�j���Ƃ̐������������A�M���ł���Ƃ���Ă���B
1��
�_���V�c
2
�V���V�c
3
���J�V�c
4
�V�c
5
�F���V�c
6
�F���V�c
7
�F��V�c
8
�F���V�c
9
�J���V�c
10 ���_�V�c
318�N
11 ���m�V�c
12 �i�s�V�c
13 �����V�c
355
14 �����V�c
362
15 ���_�V�c
394
16 �m���V�c
427
17 �����V�c
432
18 �����V�c
437
19 �V�c
454
20 ���N�V�c
21 �Y���V�c
489
22 ���J�V�c
23 ���@�V�c
24 �m���V�c
25 ����V�c
26 �p�̓V�c
527
27 ���ՓV�c
535
28 �鉻�V�c
29 �Ԗ��V�c
30 �q�B�V�c
584
31 �p���V�c
587
32 ���s�V�c 592
33 ���ÓV�c 628
��68
���_�V�c�̐���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2011.6�@�lj��j
���_�V�c���Վ����Ƃ��Ď��R�ЊQ�i�O�X��(7)�j����������ƁA�������Ƃ��đ�a����E���̐���ɏ��o�����B
���_�I�\�N
�u�����A�Q�����ق����H���A�A�A�����ɐ_�_���炵�A�ЊQ�͊F�����Ȃ����A�R��ɉ����r�l���͂Ȃ���������A�����𖢂��K���Ă��Ȃ��A����Q����I�юl���Ɍ��킵���̈ӂ�m����ނ����A�A�A�㌎�A��F����k���ɁA���ِ�ʂ𓌊C�ցA�g���ÕF�𐼓��ցA�O�g���喽��O�g���킵�A�A�A�Ⴕ����������҂͕��������Ă���������A���Ɉ�����������R�ƈׂ��A�A�A�\���A�A�A�����ނ��҂������n�����A�E���͕����ɂȂ����A�����C�O�͍r��A�����͖����~�܂��A�l�����R���͍������������A�A�A���R���͋��ɘH�ɔ����v
���_�I�\��N
�u�l���A�l�����R�͏^�炰�����v
�E�O�̐���杂̐��ʂɂ��Ă͂Q�s�̕��ōς܂��Ă���B�\���Ȑ��ʂ����������̂��낤�B���ʂ��o��܂łɐ�����ɂ��j�鎞�ԂƓw�͂��K�v����������A�ƍl������B������ȉ��Ɍ���B
��69
���m�V�c
��11�㐂�m�V�c�i���N331�N��[5]�j�͐��_�Ɠ��l�a���ɃC���������_�n�i�v�P�n�j�B�_���n���x�z���ɒu�����悤���B���̍����́A���m�V�c�͐_���n�̊J���V�c�̑������@�Ƃ������A���̍@�͌Z�ƂƂ��ɍc�ʂ����߂����Ɣ������ĎE����Ă���i����P���Ƌ���F���A�Î��L�ɏڋL����Ă���j�B���m�V�c��2�Ԗڂ̍c�@���t�|�Q�����J���V�c�̌��Ƃ����B�O�q�̂悤�ɔN��I�ɂ͐������Ȃ����A�_���n�̈ꑰ�ł��낤�B���m�V�c�͐_���n�̎x�z����D���A�x�z�̏Ƃ��Đ_���n���@�Ƃ��A��������荞�悤���i�ǂ���̍@�ɂ��c�q������j�B
[5]�@ ���m���N�E�i�s���N�@�@���m�V�c�̋L���N�͎c���Ă��Ȃ��̂ŁA�ꐢ��23�N�Ƃ��đO�㐢��̋L���N����331�N���ƌv�Z�����B�i�s�V�c�̕��N�����㐬���V�c�̋L���N355�N��23�N�O�Ƃ����332�N���Ɛ��肳���B����琄��͋��ɁA���q�p���������p���Ō덷�������邪�A������ł���m���͍����B
��83
�_���c�@�@�V���e��
�{��ɖ߂�B362�N�ɐ_���c�@�͐��폀���ɓ���A��⋊�n���\�z����B364�N�ɂ͎O���j�L�Ɂu�`���勓���P�v�Ƃ���B�`���E�M���̘A�g�̐V������̏��킾�낤�B���̎��͓��{���I�ɓ��i�̋L�ڂ��Ȃ�����c�@�͐e�����Ă��Ȃ����낤�B
������369�N�_���I�ɑ���̐V������L��������i�N�������́A�_���I�̊��x2������̏C������j�B�����I�ɂ݂Đe�����������Ƃ�����̑���̉\�����ł������B�u�V���������j��v�u���������肷�v�Ƃ��邩�炻��Ȃ�̐��ʂƌ��Ȃ��邩�炾�B��q���鎵�x���Ƃ̊W������B�������A���̎����u�V���̕���v�u�V������l���E���v�v�i�_���I362�N���j�Ȃǂ͖��������ƍl������B�������X�Ɍ�N�ƍl������B��q����悤�ɂ����402�N�ŁA�_���c�@����B���������ゾ�B������_���c�@�̐e����369�N�̈��݂̂ƍl������B
���_�Ƃ��āu�O���j�L364�N�̐V������͘`���E�M���̏���B�c�@�́w�V���e���x��369�N�B�w�l���⒩�v�x�͍X�Ɍ�N�v�ƍl������B
��89�@���_�I�@���_�V�c�͒����V�c�̎q�ł͂Ȃ��@�@�@�@�@�@�i2012.2�@���M�j
��15�㉞�_�V�c�̉��_�I�͐_���c�@���N�Ɏn�܂�A41�N�Ԃ��L�^���Ă���B�������A���_�I�͋^�₪�����Ƃ�����B�������܂߂ďC�����߂������B�C���̍����̈�́u�Î��L���N�v�ł���A������M�p�ł��Ȃ��Ƃ��鍪�������Ȃ��B������́u��{�N���C���@�v�ŁA������͍������ア�����̍��́u�V�c���N�N��v�Ɍ����Č����ΎQ�l�ɂȂ�i��O�͂ŏq�ׂ��j�B����ɏ]���ėႦ�u120�ŕ���v�́u60�ŕ���v�Ƃ���B
(1)
�@�L�I�ɂ��A���_�V�c�������V�c�̋L���N362�N�ɐ��܂ꂽ�B����A���_�V�c�̋L���N����ɂ������N��339�N�ƂȂ�[5]�B�@�����L���N����ɂ��Ȃ���A���ꂾ���ł������ł���B�C���@�Ɍ�肪���邩�A�ʐl���B���ꂾ���ł͂킩��Ȃ��B
(2)
�������C���@�ɏ]���A�_���c�@�̕��N�N���50�ŁA���̎����_�V�c��50�`60�ł���
[6] �B��l�͐e�q�ł���������ł���B�]���āu���_�V�c�͐_���c�@�̍c�q�ł͂Ȃ��v�B
(3)
�@�_���I�ɂ��u�_���c�@�ƍc�q�͑�a�A�ҁi372�`382�N�j�����v�B���̌�̉��_�I�i�`394�N�j�̖w�ǂ͋M���L���ȂNj�B�ł���B���_�V�c�͐_���c�@�Ƌ��ɓ��������̂łȂ��A�c���ċM���V�c�ɂȂ��Ă���A�Ƃ���̂��Ó��ȉ��߂��B���̉��߂ɏ]���u���_�V�c�͐_���c�@�̍c�q�ł͂Ȃ��v�Ƃ����\��������B
�L�I�Ҏ҂͐_���c�@�̍c�q�Ɖ��_�V�c��l�����Ă���B���ׂ̈��N���̕s�����������B���̓���l�������A�N�ɂ���Ďn�߂�ꂽ���ɂ��čēx�͖��Ō�������B
[5] �u���_�V�c�̐��N�v�@�@���_�V�c�̋L���N394�N�A���̎��̋L���N�N��S�O�\���u2�{�N��v�ŏC������ƁA65�ł���B�]���āA���N��329�N�ƂȂ�B�I�����N�Ƃ���362�N�ɂ�33�ł���B
[6] �u�_���c�@�̕��N�N��v�@�_���c�@�̕��N��Z��N���u���x2���C���v�ŏC�������389�N���B���̎��̋I���N�N��S���u2�{�N��C���v��50�Ε���Ƃ���B���̔N�̉��_�V�c�̔N��͑O������50�`60���B
��93�@�m���V�c�@�V���l����
��16��m���V�c�����_�V�c���p�����Ƃ����B�p�����͓̂��{�M���̓V�c�ʂ��B�݈ʂ�400�|427�N�i�I�݈̍ʔN���ƋL���N����j�B�m���V�c�͋�B�Ő��܂�i�o��l������B�o�g�j�A���_�V�c�̍c�q�Ƃ���Ă��邪�A�Z���q�Ƃ̊Ԃŕ��G�ȏ��荇���̖��ɑ��ʂ��Ă���B�V�c�ʂ�����肵���̂ł͂Ȃ����B�c�q�łȂ������̈����������Ȃ��B�u��g���Ë{�ő��ʁv�i�m���I400�N�j�Ƃ��邪�A���_�V�c�̕���̒n���u�L����g����{�v�ł��邩��A�u�L����g���Ë{�v�ƍl������B�m���̍c�q�͉��_�V�c�̑����@�ɂ��Ă���i�m���I�j�B
���̔N�u�V����b���Ƃ����`�v�ɑ��A����킪�����Ԃ��Ă����B
�L�J�y���蕶
�u400�N�A�����͕����ƋR��5�������킵�ĐV�����~�����B�V����ɂ͘`�������Ă������ב����A�����ǂ����C�߉����̏]������A���������B�v�i�Čf�j
����ɑ��Ę`���ƋM���͍ēx�V���𐧔e���āA�l���ƒ��v���Ă���B
�O���j�L402�N
�u�V�����`���ƒʍD���A���̎q���z�Ӂi�݂�����j��l���ɏo���v
����́u�V������`���ւ̏��߂ĂŗB��̐l���v�ł���A�Ȍ�`���̐V���x�z�������ɑ���[7]�B�`���̎����I�ȐV�������͂���402�N���炾�B�M���m���V�c�݈ʊ��Ԃ��B
[7] �V���x�z�@�@�O���j�L418�N�Ɂu�l�����z�ӂ��`�����瓦�S�v�Ƃ���A���S�͂��������O�����ς���Ă��Ȃ��B�܂��A�v��438�N���Ɂu�`�������`�E�S�Z�E�V���ȂǘZ�����R���̏̍������߂��v�A�������v��451�N���́u�`�����ς��`�A�V���ȂǘZ�����R���ɏ�����ꂽ�v�Ƃ��邩��A�����͘`���ɐV���̎x�z��F�߂Ă���B
��105 �@�u��̕S�ρv�̌��@
�S�ς̌���杂͎O���j�L�ƒ����j���ňقȂ��Ă���B
�O���j�L
�uBC18�N�A�����̎n�c��ցi��������j�̏��q���N�i���j����̔n�̒n�ɕS�ς����������v
���̕S�ς����Ɂu��S�ρv�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�n��50�]���i�㊿���j�̈�ł��낤�i����ł͔��ρj�B�Ȍ㎟��ɔn�ꂵ�A25�㕐�J���܂ł�500�N�߂����L���Ă���B
��������j���ł́A
�@���S�ϓ`
�u�����i�}�]�̎n�c�A����ł͍����̑c��ցi��������j�Ɠ��ꎋ�j�̌�A�w��Ȃ�҂���A�n�߂č���ѕ��̌̒n�ɗ��A���̗ɓ���������x�i200�N���A���Ɨ��ѕ��S����j�A���i�ނ��߁j������̍ȂƂ������v
������̕S�ς����Ɂu�k�S�ρv�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�P�Ɍ���杂̈ٓ`�ł͂Ȃ��A��q����悤�ɕʂ̍��ł��邱�Ƃ��킩��B�k�S�ςƓ�S�ς��ǂ̂悤�ȊW���������A�@���Ɠ�����Ҏ[�̎�����������������Ă���B
�����S�ϓ`
�u�S�ς́A���̐�͊W���n�̛����A�v�P�̕ʎ�Ȃ�A�w��Ȃ�者�A�������Ɏn�߂�v
�����j���̕S�ρi�k�S�ρj�͑O�q�́u��S�ρv����o�Ă���A�Ƃ���B���̍��̔n�ɂ́u5��ڏьÉ��̕S�ρi��S�ρj�v������i�O���j�L�j�B���̓�S�ς̉����̈�l���Ɨ����ē����̏�������ѕ��Ɍ��Ă��̂��낤�B�k�S�ς͂��̌�k���֔��W���A�y�Q��̂��A�쒩�ɒ��v�����B
�W���S�ϓ`
372�N�u�S�ω��]���q���Ē������R�ƈׂ��y�Q�����̂����ށv
�y�Q����ɏ��ʂ���Ă���B�쒩�̉��ɔ�э���œ쒩�̔˛��Ƃ��Ă̓���I�Ǝv����B�������A427�N�ɍ���킪�y�Q�߂��̕���ɓs���ڂ�������A�k�S�ς͊y�Q�������ꂸ�ѕ��ɓ쉺���A�X�ɍ����Ɉ������ꂽ�i��ď��j�B�k�S�ς͂��ɍ�����w�ォ�猡�����Ă��炤�ׂ��k鰂ɋ��������B
�k鰏��S�ϓ`
�u472�N�A���]�c�n�߂Č��g��\���ĞH���A����킪����j��Őb�Ƃ��Ă̈ӂ�`�����Ȃ��v
����܂Ŗk�S�ς͓쒩�ɒ��v���Ă����A�k���̖k鰂ɏ��߂Ē��v���Ă���B�������A�k鰂͓����������͓쉺�𑱂����B�k�S�ς͍X�ɒǂ��Ă��ɊC��k�サ�ėɐ��i�݊C�ɒ����ɉ͂̐��j�ɑJ�s�����B���̒n�͗ɐ��ɂ������k�S�ς̔�ђn�ł���B
�v���S�ϓ`
�u�S�ύ��A�{�i���ƁA�v�ȑO�ɂ́j��鋂ƂƂ��ɗɓ��̓��痢�ɂ���B�i�v����420�`479�N�ɂ́j��鋂͗ɓ��𗪗L���A�S�ς͗ɐ��𗪗L���B�S�ς��������i�s�����j���͂����W���S�W�����ƈ����v
�ɐ��ɑJ�����k�S�ς́A���x�͖k鰂ƍU�h���邱�ƂɂȂ�i��ď��A488�N�j�B���������k�S�ς��A���̖k鰂Ɠ��̍����ɋ�������A�C��n���čĂѓ�ɓ������B
�����S�ϓ`
502�N�u�j�𐪓����R�ɐi�߂����A����鋂̔j�鏊�A����͗ݔN�A��ؒn�ɑJ�����v
���ꂪ�k�S�ςɊւ��钆���j���̍Ō�̋L�q�ł���B
������̊ԁA�u��S�ρv�͘`���ɜ�������ĉ�����コ����ꂽ��(390�N���A���_�I�A�O�q)�A�`���ƍ����ɑ����ɂ��ꂽ�肵���i400�N���A�L�J�y����j�B475�N�ɂ͍����Ɋ���𗎂Ƃ���21��W�b���i�����남���j�͎E���ꂽ�B�q�̕������i22��j�͓�ɓ���ċv���ߗ��i�F�Áj��s�Ƃ����i�O���j�L�j�B
��106�@��k�S�ς̍��́@�@�i���̂Â��j
�k�S�ς���ؒn�ɑJ������502�N�ɂ͓�ؕS�ςɂ͕��J���i25��j������B�����Ă���̕S�ς͓�ŕ��������̂��낤���B���̋^��͈ȉ��̉��߂ʼn��������B�O�q�����悤�ɁA���J���ȍ~�����j���E���{���L�E�O���j�L�̋L�^�͊T�ˈ�v����B�����e���̋L�ڂ��鉤���́A
�����j���i�]���E�]���i���̎q�Ƃ��j�E�]���E�]��E�]���E�`���j
���{���I�i�z���i���J�Ƃ��j�E�����i�����Ƃ��j�E���i�Г��Ƃ��j�E�`���j
�O���j�L�i���J�E���E���E�b�E�@�E���E�`���j
�����ŁA�]���A�z���A���J�͕��J�˔����i1971�j�̔��@�掏���瓯��l���ł��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���i���N�E�v�N�E�R���̈�v�Ȃǁj�B���J���͓�S�ς̉����ł���i���{���I�E�O���j�L�ɏڋL�j�B�������A�k�S�ς̍����̐��������p���Œ����ɒ��v���Ă���B
�����S�ϓ`
521�N�u���̗]���i���J���j���Ăь��g���Ȃĕ�\���A�w�x�X�����ɔj��ꂽ�����ʍD���n�߂�x�Ə̂����B�����ĕS�ς͉��߂ċ����ƂȂ�B���̔N�A���c�͏قɞH���A�A�A�S�ω��̗]�����A�A�A�X�������̏͒��ɏ]���A�A�A�s�S�Ϗ��R���A�J���囒�R�A�S�ω��Ƃ��ׂ��v�B
�����ŁA502�N�ɖk�S�ς������ɔj����ɑJ�����Ĉȗ�19�N�ԓr�₦�Ă����S�ρi�k�S�ρj�̒��v��S�ρi��S�ρj�̕��J�����ĊJ�����̂Łu�Ăсv�u���̏͒��ɏ]���v�ƌ����Ă���B���̎��A���J���͖k�S�ς̉��̐��i�]�A�Ⴆ�Ζk�S�ς̉��͗]��E�]�f�E�]毗�E�]�c�Ȃǁj�𖼏���ė]���Ƃ��Ē��v���Ă���B�ȏォ��A�k�S�ς͓�S�ςƍ��̂����ƍl������B
��107�@�u��̕S�ρv�̎��ԁ@�M�Ґ���
���̑O�̗��҂̊W�͂悭�킩��Ȃ��B�ȉ��͕M�҉��߂̎��Ăł���B
�ɐ��ɗ���ė����������i�������̌�j�����̒n�̕}�]���̈ꕔ�������A��Ĕn�ɕS�ς����������i�����A���́u�`�l�͌��̑����̌��Ⴉ�H�v�Q�Ɓj�B����w�����Ď���ɔn�ꂵ�Ă������B����A�����̈�l�͖k���w�����đѕ��ɕ��������Ă�(200�N��)�B�`���̉��ł������������ɒ��v���āu�S�ω��v�ɏ�����ꂽ�B�ꎞ�ɐ��ɑJ�s���Č������̂���ȂǁA���̖���̈ӎ����������悤���i���́u�ɐ������v�Q�Ɓj�B�Ȍ㍑�ۓI�ɂ͖k�S�ς͕S�ς̏@���B���̕S�ρi��S�ρj�͂��̈ꕔ�����S�ω����̏@�ƂƂ��ēƗ��I�ɐV���E�`���ƌ𗬂����悤���B�����A�}�]�̕ʎ�Ƃ��č�����k�S�ςɑ��Ă͈����ڂ̈ӎ����������悤���B���ꂼ��ɐ���������A���S�ς��Փ˂��邱�Ƃ͖��������B�ނ���A���ՂȂǂŌ𗬂��[�������悤���i���͎Q�Ɓj�B�`���^���{���𗬂����S�ς͎ア��S�ρi�_���I�j�ƍ��̌�̋����S�ρi��S�όn�j���i�p�̋I�ȍ~�j�B���̌�̕S�ρi��S�όn�j�̗��j���i�S�ώO���j�ɂ͍��̑O�ɂ��ē�S�ς̉����Ǝ��т����ڂ��Ă��Ȃ��i�k�S�ϕs�L�ځj�B���������ւ̒��v�L���͐����Ȃ��ŋL�ڂ��Ă���i�k�S�ϕs�����j�B���̌��ʁA���v�͓�S�ς̎��тƌ�ǂ���Ă���B
�i�ŋ߂̍X�V�@2014.8�@�u��̌��v�lj��@�@�@2012�D2�@�ĕ҂ƒlj��j
�{�̗͂v�|
���{���I�́u�S�ώj�����p���v�������ɁA�u�`���͑�a���삾�v�Ƃ������ɑ��āA�u�������͂��w��`�����{�x�w�`���V�������{�V�c�x�ł��邱�ƂL���Ă���v�Ƃ�������m�F�����B�X�Ɂu�v���̘`�̌܉��v�̕��͂���u�`�����͐��ނ̉��v�ł���A���{���I�̎����u���X����Y���V�c�v�ł͂��蓾�Ȃ��Ɖ��߂����B
�`���Ɠ��{�̊W�͋��ɃA�}�e���X���J��Γ��I�F�M�ł���ƂƂ��ɁA�`�����@�卑�Ƃ���`�����̕M���Ƃ��āu�`�������{�v�ƕ\�������悤�ȊW�ƍl����B
�u�l�����x�b�i�킩������j�剤�v�̖��̂���S�����F�{���̍]�c�D�R�Õ��ƍ�ʌ��̈�R�Õ�����o�y���u�̓���̏v�Ƃ���A���̓��ꉤ���Y���V�c���`�������Ř_��������B�������u�`�������x�z�����B�̒��ɁA�Y���V�c�̏��R�̕悪���݂���\���ȗ��R������B���{�M���̌���ł���}���N�����v�Ƃ̉��߂��Ă���B
��108�@�`�̌܉�
�`���͕S�ρE�V���̎����x�z�ɐ������A���������������Ɓi�O�́j�A�`���͂�������ێЉ�ɔF�߂Ă��炨���ƁA�����Ɍ��g���ď��F�����߂��B�������j�ł���W���`�v��
[1] �̒��Ɂu�`�̌܉��v�i�]�E���E�ρE���E���j�Ɋւ���L�q������B���o�̘`���]�ɂ��ẮA
�W�����Γ`�@�u413�N�A�W����̎��A�`���]�L��A���g���v�� [2] �v
�v���Δؓ`�@�u421�N�A�`�]���v�̕���Ɍ��g�C�v�����B425�N�A�]���i�n���B�����g�����v
�Ƃ���A�O�㐔�g���v���������̗l�ȁu�`�E�S�ρE�V���̌R�������F�̗v���v�u�`�������ʂ̗v���v�������B���F�̌����݂��܂��Ȃ������̂��낤�B���̂��u�`���v�ł���B
���ɁA�`�����ɂ��āB
�v���Δؓ`�@�u425�N�A�`�]�����ɁA�����������A���g�v���A�A�A�`�A�S�Z�A�V���A�C�߁A�`�A��ؘZ�����R���A�����囒�R�A�`���������̂��A���������߂��B�������R�A�`�����ɏ����v
�]�̒풿�̑�Łu�`�����v�����̂��A���߂āu�`�����v���ʂ��B�S�ρE�V�����������A���߂Ę`���ꂵ���ƔF�߂�ꂽ�̂��B�ȗ��A���̍ρE�����u�`�����v�ɏ����ꂽ�B�R�����ɂ��Ă͗v���̈ꕔ�������F�߂�ꂽ�B
�v���Δؓ`�@�u443�N�A�`�����ς����g�B�������R�E�`�����ƂȂ��B
451�N�A�����Ďg�����A�A�A�`�A�V���A�C�߁A�����A�`�A��ؘZ�����R���A�������R�����B�����A���q�����g�v�فB
462�N�A�`�����q�����������R�E�`�����Ƃ��ׂ��v
���ɁA�`���ς́u�`�����v�u�`�E�V�����̑��̌R�����v��F�߂��Ă���B�S�ς����O����Ă���̂́A�S�ς��`���ɐ�đv�ɒ��v���Ă������߂Ƃ�����B�ς̎��ɋ����u�`�����v��F�߂��Ă���B
���̎��ɘ`�����������A��\���i��q�j����Ƃ���B
�v���Δؓ`�@462�N�i�Â��j�u�������i477�N���H�j�B��̕��������A�g���߁A�s�A�`�A�S�ρA�V���A�A�A�������R���A�����囒�R�A�`�����������B
478�N�A�������g��\���ĞH���A�A�A�i��\�����@��f�j�A�����g���߁A�s�A�`�A�V���A�C�߁A�����A�`�A��ؘZ�����R���A�����囒�R�A�`���ɏ����v
[1]
�u �v���v�@503�N����ɂ���Ċ����B�v��479�N�܂ł�����A������I�j���B
[2]
�u�`�]�v
�`�̌܉��̏��o�B�`�͐��A�]�͖��ƌ�����B�����̐����Ӗ�����u�v�v�̕���������̂ɁA���Ԃ�̏��ʂ͖��������B�u�S�ω��v�����łɁu�����叫�R�v�ɔC����ꂽ����i����I�j�ł��邩��A�o�x��̊��������B
��117�@�u����v�̌��Ɓu��`�����{�v�̏ؖ��@
��q�����悤�ɗY���I�ܔN���́u����v�������Ƃ��āu��`�����{�v��������������B�������A���̏��ꎩ�̂��u�͓���ł͂Ȃ��v���ƁA�]���Ē���Ƃ͋t�́u��`�����{�v���ؖ����Ă���A�ƍ�c���������u���{�̍����v [8] �̒��œW�J���Ă���B�����ƍL���F�������ׂ��A�ɂ߂ďd�v�Ȏj�����߂Ȃ̂ŏЉ��B
���_���ɋL���ƁA�u�W�����E���x�N�i�����{���N�j�E�R�N�͎O�Z���v�Ƃ����A�V���Ȕ����Ƃ��̓W�J���B���̍�����
����I�l�N��
�u�S�ϐV��ɉ]���A�A�A���J�����z������恁i���j���B���ꍬ�����q�̎q�Ȃ�v�i�O�f�j
�ɂ���B�����A����Ɛ�̓����킹�ǂނƁi�������j�A
�Y���I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���Z�@���{���N�@���@���N�i�����������J���j�@�@
����@�R�N�@�@���{�̓V�c�Ɏd����@�@�@�@
�S�ϐV��
���Z�@�W�b���@
����@�����N�i���������q�j���@���J�����z�����i�������j
��`�̓V���Ɏd����
�@����u���{���N�������N�i���������q�j�v���ǂ߂Ă���B����͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B
���Z�@�W�b��
����i���Z�j�����N�i�����{���N�j���@�z�����i�������j�����J��
���@�@�@�@�@�@�@�@��`�̓V���Ɏd����
������@�R�N�@�@�@���{�̓V�c�Ɏd����
��c�̌��_�́u�S�ω��͎O�Z�킾�����B�Z�W�b���͒�����x�N���`�̓V���Ɏd�������A�������x�N�i�����{���N�j�͖���̌R�N����{�̓V�c�Ɏd���������v�ƌ����A�ɂ߂Ė����ȋL�q�A�Ƃ���B���Ȃ킿�A�u��`�����{�v�ł���A�u�V�����V�c�v���B����́A���{���I�i���p�̕S�ϐV����܂ށj�����œǂݎ���_���ł����āu�����v�ł͂Ȃ��B
����ɂ���āu��`�����{�v�ƒf��ł���B�u����v�Ƃ��Č���i�߂Ă������A�����Łu�j���v�Ɗm�F�ł����B
[8]
�u���{�̍����v��c���@�|�� 1993 �N
��123�@�v���u�`�����̏�\���v�͕S�ς̖͕�
�`�������ꂵ�āA�`�E�S�ρE�V���̎x�z�����F�����߂Ę`�����ɏ�����ꂽ���A���̊Ԃ̘`�����̐��̐��Ƃ��āA�v���̒��ɘ`�����̏�\��������B�v�Ō�̍c��8�㏇��ɑ������݂��Ƃ��w�U�́i�ׂ�ꂢ�����j�̊i�����������ŁA�l�̐S��ł��X������e�ŏ�����Ă����\�����B�v���Ҏ҂��Ȃ��Ȃ��ƈ��p���Ă��邱�Ƃ�����������Ă���B���������������ň��p����B
�@�v���`���`478�N��
�u�����͕Ή��ɂ��āA�˂��O���삷�B�̂��c�H�Z(�݂�����)�b�h���(���)���A�R���H���A�J��(�˂�����)�ɖH(���Ƃ�)���炸�B���͖ѐl�𐪂��邱��55���A���͏O���邱��66���A�n�����C�k����������95���B�����Z�ׂɂ��āA�y���f���E��篂ɂ��B
�ݗt���@�i���N���v���āj���čɔK�i�������j�炸�B�b�A�����Ȃ��嫂��A�Y�i���������j�Ȃ����描�������A���Ԃ鏊���엦���A�V�Ɂi�v�c��j�ɋA�����A���S�ς��y���A�D�����B������ɋ��(�����)�����ɂ��āA�}���Č��ۂ��~���A�ӗ�(�ւ�ꂢ)�𗩏�(��Ⴍ���傤)���A�c�����ě�(��)�܂��B��(��)�Ɍm��(��������)��v���A�ȂėǕ��������A�H�ɐi�ނƓ�(��)�ǂ��A���邢�͒ʂ����邢�͕s�����B�b���S�l�ρA���Ɍ��Q�̓V�H���Ǎǂ�����K���A�T���S���A�`���Ɋ������A���܂��j�ɑ勓����Ɨ~���������A���i�ɂ�j���ɕ��Z��r���A�����̌������Ĉ�ǁi��ЂƑ��j���l�������ށB���i�ނȁj�����ȈŁi�r���j�ɂ���A���b�������B�������Ȃċ͑����i�����Ђ��߁j��������(��)�����肫�B���Ɏ������A�b�����蕺�����߁A���Z�̎u��\�ׂ���~���B�`�m�Րӕ������������A���n�O�Ɍ����Ƃ��܂��ڂ݂��鏊�Ȃ�B�����铿�̕��ڂ��ȂāA���̋��G��F�i�����j�������������i�₷�j�A�O����ւ��邱���Ȃ����B�ށi�Ђ��j���Ɏ���J�{�V���O�i�������A���̗]�͉������āA�ȂĒ��߂������v�ƁB�i����j�ق��������g���ߓs�`�E�V���E�C�߁E�����E�`�E���6�����R���A�����叫�R�A�`���ɏ����v�@
�܂��A�����̗��j�I�Ȕw�i��������N�����A���ӂ̔O��\�����Ă���B�����Č��݁A����̒u����Ă��鍢��ȏ����������ŁA�������������M�ӂ���l���A�ʂ�������蒉�߂��ށA�Ƃ��������𖾂炩�ɂ��āA���̂J�ɂ��肢���Ă���B���a�̎�ꂽ���h�ȍ����ł���B�܂��A����͘`������ɂ��Ę`��������q�ׂ�ꂽ�B��̎������B���̋L�q���e����A���ɐ��ɐ�����J��Ԃ���������͂��łɊ������A�s���̐��𐮂��i�J�{�j�A�㉺�𐮂��i�����j�A�ꂵ���ߒ����\�����������B�`�������u���X����剤�v�Ƃ��ėY���V�c[13] �ɔ�肳��鏊�Ȃ��B
�������A�u��������������ނ̘`���v�̏�\���Ƃ��ēǂނƁA����́u����킪�N�����č���B�Ȃ�Ƃ����Ă���v�Ƃ����������ɂ��݂���B���́A�S�ω������l�̓��X�����\���i400�����j���s���Ėk���̖k鰂ɏo���Ă���(472�N)�A�k鰏��Ɉ��p����Ă���B���e���u����킪����j��Őb�Ƃ��Ă̈ӂ�`�����Ȃ��v�Ƃ������̂��B����ɑ��Ėk鰌�����́u�\�ĔV���A�A�A鰂̖�ɐ��������ċA�i���j����A�ӉÁi���́j�ӂɎ���v���ق�������B
�S�ςƖk鰂̊Ԃ�����킪�j��ł���͎̂������i�S�Ϗ�\���j�B�������A�`���Ƒv�̊Ԃɂ͕S�ρE�����E�k鰂�����A����킾�����j��ł����ł͂Ȃ��B����킾���������o���͕̂S�Ϗ�\���̖͕�ł���ƊŘ�Ղ��B���ہA���v�g�͂��߂��C�H�����A�����E�k鰂�ʂ闤�H�łȂ������ƍl�����Ă���B
���̏�\�̗��N479�N�A�쒩�v�͖ŖS�����B���������k�����v�ɓ]�������S�ςɔ�ׂ�Ƙ`�����̏�\���i478�N�j�͎j���Ƃ��ċM�d�Ȃ��獑�ۊ��o���x��Ă���B�u�`�����͐��ނ̌�����쒩�Ƌ��L���Ă����v�Ǝv�������Ȃ�ł���B
[13]
�u�Y���V�c�v�@�剤�Ə̂��i�F�{�]�c�D�R�Õ��S�����E��ʈ�R�Õ��S�����j�A���V���ɂ��i�������×��j�A���t�W�̖`���̂���̂ŏ���A�����ɔh���i���{���I�j���s�����X����p�Y�ł������B
��129�@�Y���I�u�������g�v�͘`�����v�g�̐��s�g���H
�@�`���ƗY�����͗F�M����������Ƃ��āA���l�Z�H�̏��َ��Ƃɉ����闼�҂̋��͂�������B�Y���I�ɂ͌����Ƃ̌�杂������B
�Y���I
462�N�u���������g�v�������v
464�N�u�g������i�ނ��̂����肠���j�A�w�G���g�����i�Ђ̂��܂̂��݂̂����͂��Ƃ��j�������Ɍ��킷�v
466�N�u�g��������A���̌������H���@�i���A�����傤�j�������Ē}���ɓ���v
468�N�u�g������ƞw�G���g���������Ɏg�킷�v
470�N�u�g��������A�����g�Ƌ��Ɍ��̌�����薖�̍ˊ�A���D�E���D�y�шߖD�̌Z�Q�E��Q�����Ђ����ďZ�g�Âɔ��܂�v
�����ŁA�u�����v�͒���E��B�������Ƃ��u�����쒩�v�v�Ƃ���B����ł́u�Y���I�S�U�Q�N���̋����I�\���i�v����a�ɒ��v�j�͕ʂƂ��ē��e�͑v�ւ̒��v�g�L�^杂ł����āA�v���`�̌܉��̋L�^�Ƃ悭�Ή�����B�Y���V�c���`�����̏؋��v�Ƃ��Ă���B����A��B�������ł́u�����쒩�v�ɒ��v�����̂͘`�����B�`������462�N�ɘ`�����ɏ������Ă���i�O�q�j�B���̓`�B�g�̋L���i462�N���j�A����ɑ�������g(464�N��)�A����g�̋A���L���i466�N���j�A����炷�ׂĂ�Y���I�͓��p���Ă���v�Ɖ��߂���B
�������A�u�����͘`���̌��v�g�ɐ��s�����Y�����̎��тŁA�Y���I�͎j���v�Ƃ������߂����肤��B���̍����́A
(1)�@�Y�����̊��l�Z�H����杂͏�q�̂悤�ɏڍׂɘj��A�j���ƍl������i����470�N���j�B
(2) �����u���l�̏��فv�Ř`���ƗY�����͋��͂��Ă����B
�Y���I
�u�S�ς̌��サ���薖�ˊꂪ�哈�ɗ����A�A�A�`���̌���i���ƁA����숢�l�H�j�Ɉ��u���A�A�A�V�c�A�唺��A�������ق����������d�i�������m�g��̎q�A�s���i���j�g��j�ɖ����ĐV���i�����i���܂��j�̊��l�j�̓����A�A�A�����������A�������A�^�_���̎O���ɑJ�����炵�ށv
�����ŏ㓍���A�������A�^�_���͔�O�̘`���̂ł���i��B�`�������̂ł��邱�Ƃ��܂ށB�̂��Ɍp�̗̂��o�đh��̂ƂȂ�A�攪�́u�ߋE�v�Ɓu��O�v�̍��Q�Ɓj�B���Ȃ킿�A�Y�����͍����̊��l�𓌊��i��O�̊��l���Z�n�A�`���́j�ɏZ�܂킹�Ă���B���̌�A�Y���I470�N���̂悤�Ɋ��l�Z�H��ےÓ�g�ɘA��Ă��Ă���B�`���̋��͂����������A�ނ���`����̂̊��l���َ��ƂɗY�������֏悵���ƍl������B
(3) �Y�������P�ƂŌ����g�����v�g�𑗂����Ƃ͍l�����Ȃ��i468�N���j�B�v�ɒ��v����@�卑�`��������Ȃ���A�P�Ƃőv�ƌ𗬂��邱�Ƃ͒ʏ킠�肦�Ȃ��B�O���ł͂Ȃ����ՂȂ�P�Ƃ����蓾�邪�A�`���������Ό��v�g�𑗂��Ă��鎞���ł���B�C��X�N���������Ƃ��l����ƗY�����̌��v�g�Ƃ͘`���̌��v�g�ւ̐��s�g�ł���\���͂���B
(4) �u���s�g�v�̕ʂ̍����́A�`���͊O�������蒆���Ɍ��g���鎞�`�����̎g�𐏍s�������Ⴊ�ȉ��̂悤�ɏ��Ȃ��Ȃ����炾�i�������܂ށj�B
266�N�A�`����^�̌��W�g�ɂ́u���v���Ă��Ȃ����̘`�l�v�����s�����Ǝv����i���͎Q�Ɓj�B
464�N�A468�N�̘`�����v�g�ɐ��s�����Y�����̎g�i��q�j�B
607�N�A俀�i�����A��Á��`�j�����@�g�ɐ��s�������Ò��̏��얅�q�i�掵�͎Q�Ɓj�B
631�N�A654�N�̘`�������g�ɐ��s�����F�����̎g�i�V�������{�`�A�攪�͎Q�Ɓj
�ȏ�A���Ȃ����`���ƗY�����͊��l�Z�H���َ��Ƃŋ��͂��Ă���B�����Y�����́u�`���̌��v�g�ւ̐��s�g�v�Ƃ����`�Ŏ��������\���͂���B
��140�@���������u�}���N�ֈ�v�͑�a�n��B�����ł����i2014.9�@�X�V�@2012.1�@���M�j
�u�`�������ֈ�v�i��B�������j�ɂ͓����B���̍���(1)�`(11)����������ŕM�ҐV���߂������B
(1�j ��B�������́u�}���N���`�����v�͐������Ȃ��B��������͉����邪�i70�N��j�A�u�@��俀�i��Áj���`�v�̈�߂Ɂu�|�z�i�������j�� [3] ��俀�i��Áj���i�`���j�ɕ��f���v�Ƃ���l�ɁA�u�}�������`���v�ł���B�]���Ē}���N�ֈ�͘`�����łȂ��B
(2�j�`�����Ƃ̑c�͓V���n�A���̐�̓A�}�e���X�A���̐�͊C���`�l�ƍl����B����A�}���N�̑c�͑�F���A���̐�͔����n�A���̐�͒����n�ƍl����B�����A
�F���I�i���j����j
�u��F���A�A�A�}�������A�z�����A�A�A�}�������̎n�c�Ȃ�v
���_�I
�u��F����k�����A���ِ�ʂ𓌊C�ցA�g���ÕF�𐼓��ցA�O�g���喽��O�g���킷�A���R�ׂ̈Ɉ���������i�l�����R�j�v
��F�͐_���n�Ɏd������A���_�V�c�̎l�����R�̈�l�Ƃ��Ėk���z�̍��肵���B�����ɂ͏h�H�n�i���l�n�V���l�����l�j�������B��F���g���h�H�n���^���V�n�A���Ȃ����n���n���낤�B���̈ꑰ�����h�H��͐_���c�@�i�h�H�n�j�E�����V�c�i�^���V�n�j�̉����}�����F�P�����E���{�M���̌����Ɍg������B�����āA�_���c�@���ߋE�ɋA�҂�������ꕔ�͎c���Ē}���i�}��j�̍����ƂȂ����悤���B���ꂪ�}���N�i�}�������j���낤�B�u�����v�Ƃ���悤�ɁA���ʂł͂Ȃ����������B��F��c�Ƃ��Ă���B�ނ��u�`�������}���N�v���B
(3�j�u�}���N�v�͍s���E�ł͂Ȃ��A���P�I���Ђ̖��ł��낤�B�}���N�Ƃ����Ă��}���S�y���x�z���Ă����̂ł͂Ȃ��A�L�O�E��O�E���E�}��ɓ_�݂���̒n�������Ę`�����ƂɎd���Ă����������낤�i�����I�ȐΑ��̕��z�Ȃǂ���A(5)���Q�Ɓj�B�㐢�̋��ɏ]���u�}��N�v�ł����Ę`���������_�Ƃ����u�}�O�v�ł͂Ȃ��B�ֈ�ɂ��Ă̏ڋL���u�}�㍑���y�L�v�ɂ��邩�炾�B�`���ɋ��͂������{�M���i�_���E���_�E�m���j���x���������Ƃ��āA�`�����ő����̌��Ђ��ێ����Ă����ƍl����B�����ɂ͓��R�u�`�������}���N�ֈ�v���������B
(4)�@ �Ȃ��i���̒}���N�ֈ䂪�`�����ɔ��t�����̂��낤���B�@�`�����Ƃ̗͓͂쒩�̍����̐��ŏ��ʂ��ꂽ���ۓI�ȊO��͂ƌ��Ђ������B���̓쒩���������A��������쒩���炷��u���ނ̘`���v�������������i�O�́j�A���̌��Ђ͍����̐����E�Ŋ��S�Ɏ���ꂽ�B�ł́A���͂ł͂ǂ����B�`�����Ƃ͒}�O�𒆐S�ɂ��Ȃ���e�n�ɑ����̗̒n�������Ă����Ƒz������邪�A���͂ł͊e�n�ɓ����i�����j�����}���N�̕����L����������������Ȃ��B���̍����͒}���N�ֈ�̎���i���O�z���j�Ƃ�����ˎR�Õ�����B�ő�ŖL�x�ȕ����Ă��邩�炾�B���̔ɉh�͗��ߐ��ƊW�����邩������Ȃ��B
(5)�@ ��ˎR�Õ��i�}��j�ɂ���q���i���Ƃ��A�����j�Ƃ����ʋ�i�ׂ����j�ɗl�X�ȐΑ��������Ă��āu�ٔ��̗l�q��͂��Ă���v�Ƃ����B�ֈ�͗��߁E�i�@�ɊS�������Ă��邱�Ƃ������Ă���B
��B�������ł͂���������Ɂu�ֈ�͐����ŗ��߁E�i�@�߂������l�B���߂߂ł���̂͑v���珖�ʂ��ꂽ�`�������B�]���Ē}���N�ֈ�͘`�����B�ֈ�͂�����ւ�Ƃ��Ď������Ɏc�����B�v�Ƃ��Ă���B
(6)�@�ֈ�͒������k���o�g�̏h�H�n�Ƌ߂���F�̎q���ł��邩��k���ɐe�ߊ������͂����B�����k鰂̈ꕔ�ɂȂ��Ă����ɐ������Ƃ��𗬂��������Ǝv����B���̍����͒}���N�ƗY�����Ƃ͋߂��W������A���̗Y�����͕S�ς�ʂ��A���邢�͒��ڗɐ��̌����Ɍ��g���Ă����i�O�́u��̌��v�j�B�}���N�ֈ�����l�ɗɐ�������ʂ��Ėk���̏��Ă����\��������B�k鰂͋ϓc���ȂǂŐ�s���Ă���A�ֈ�͗��ߐ��̏���k鰂��瑊�����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�q���̗��߂͓쒩�n�łȂ��A�k���n���Ƃ肢�ꂽ�\�������邾�낤�B
(7)�@�ֈ�͘`�����Ɂu�ŖS�����v�̑���ɖk鰂֒��v���ׂ��B���߂�����Ȃ�쒩���͖k鰂���v�Ƌ����i�������̂ł͂Ȃ����B�������A�`�����͊�Ȃɂ�������B���Ђ������A���͂��������݁A���v����������i�I�ƂȂ����k鰂ɂ����ۂ������A����Ș`����������A�ֈ�͌p�̖̂��������҂��āu�����ĂΘ`�����Ƃɑ����ė哱���������B�v�ƌ��Ĕ����ƂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
(8�j �}���N�ֈ�́u���{�M�����R�̌���v�A�p�̓V�c���u���{�M��������v�i���_�V�c�ܐ��j������A���g�ޑf�n���������Ƃ��l������B�ֈ�͌p�̂���������Ɗ��҂�����������Ȃ��B�������u�p�̌R�͓����l�q�����������A���鎞�_�œˑR�i�\��ʂ�j�`�����Ƒ��ɗ������v���ꂪ�}�㍑���y�L�핶�̕\���u�₩�ɂ��Ċ��R�i�p�̌R�Ƙ`�����̘A���R�j����������ďP���Ƃ���v�Ƃ����\���ɂȂ����A�Ƃ��l������i�O�� [2] �j�B�ܐ��O�̉��_�V�c�͕����h�H�i��F�̈ꑰ�Ƃ����A�L�I�j���M������ǂ��o�����i��l�́A���_�I�R�W�X�N�j�B�p�̓V�c�i���_�ܐ��j�͂��̌̎��ɕ�i�Ȃ�j���đ�F�̖���ł���ֈ�����̂�������Ȃ��B
(9�j�p�̓V�c�̌��t�́u���������x�z�v�ł͂Ȃ��u�D�����ֈ�̂̓��������x�z�v�ƍl����B�u����ȓ��i�̔ֈ�́i�Ɠ����̑�F�����̗́j�j�͒��V�𐧂��B�}���Ȑ��i�̔ֈ�́j�͓�V�������A�A�A�v�Ɗ��ʂ����ĉ��߂��ׂ����B���̍����́A����Ȍ�̑�a�����̓ԑq�ݒu����B�݂̂Ȃ炸�A�Z���ɔd���`�����A�x�͂ɂ܂Ŋg�傳��Ă��邩��A����ȓ��Ƃ͂����ֈ�́^��F�����̂��w�����ƍl�����邩�炾�B�����āA�����̕������́u�p�̂̑c���_�V�c�́w���̓��{�M���x�Ɛm���V�c�̎x�z�����w���̓��{�x�i�ߋE�����j�v�܂����\���ł��낤�B
(10)�@�����A�u�p�̓V�c�͑�F������łڂ����̂ł͂Ȃ��A�ԑq�������o�������v�����肪�Ó��Ȑ������낤�B���̗��R�́A�F���I�Ɂu�����̑c�Ȃ�v�Ƃ���A���{���I�Ҏ[���Ɏ������������Ă��邱�Ƃ���������Ă��邩�炾�B�m���ɁA�}���N���犮�S�ɖłڂ��ꂽ�̂łȂ��V�q�I�Ɂu�}���N�F��ԁv���o�Ă���B�`���s�L�ڂ̌����̒��ŁA�`���b���̒}���N���L���̂́u���{�M���̖���Ƃ��ē��ʈ����v�����炾�낤�B�}���N�ֈ���L���Ă���̂��������R���l������B
(11)�@�����A��B�������u�}���N�ֈ䁁�`�����ֈ�v���������Ƃ�����A���{���I�́u�`���s�L�ځv�̌��������������͖����ɗ�O�Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B�����Ř`���������ꂾ�������ɋL�q����Ȃ�A�Ȃ�����s�L�ڂƂ���̂��B��B�������u�}���N�ֈ䁁�`�����v���̏����ʖ������B
��145�@�`���̔����P��
�ŖS�͂��Ȃ��������`���ɂƂ��āu�ֈ�̗��v�͏Ռ��������ɈႢ�Ȃ��B��������ɘ`���͔���������e���ɈςˁA�����̓����d���֓]�������悤���i�@���@�Ɂu���L���嫁i�����ǁj������Ȃ��v�Ƃ���i���͎Q�Ɓj�B
�`��/���{�i��a�j�̘A�g�����ꂽ���Ƃʼn���(����)�����͘A���̐������߂ĐV���ɑR���悤�Ƃ������A���̍������I�݂ɗ��p���ĐV���͐��͂��L���A532�N�i���j�C���������A562�N�ɂ͎c��̉��������������B
�O���j�L�@�V���i���j
532�N�u��������������ƉƑ��Ƌ��ɗ��~�������̖��q���V���Ɏd����i�����͉���A���̖���Ƃ̐����j�v
536�N�u���߂ĔN����p����i�������N�@�쒩�N������̗��E�j�v
�����e���͔ֈ�̗��̌�A�����헪�̘`�����R�i�ߏ��R�ƂȂ����Ǝv����B�܂��і�b�N�����암�Ɉ�킵�A���N�����̎x�z�҂��`�����畨���e���ɑ��������Ƃ����������悤�Ƃ����B�������`�������h�����Ă����C�ߓ��{�{�i�`���{�H�j�̊����͖і�b���C�ߓ��{�{�ɓ��邱�Ƃ����ۂ����B�і�b�͖�ڂ��ʂ������Ƃ��ł����ɋA������r���Ŏ�������B�����e���̒��N�����헪�͑��X�Ɏ��s�ɏI���B���̌�Ԗ����͕S�ς̗͂���Ē��N�������x�z���悤�Ƃ���B�u�C�ߕ����v�ł���i��q�j�B
��146�@��a�����̋�B�J�s�@�@�@�@�i2012�D3�@�lj��j
27����ՓV�c�i528-535�L���N�j�́A�ֈ�̗��̌�Ɍp�̓V�c���������̂Ōp�̂̒��q�Ƃ��đ��ʂ����i�p�̂̋L���N527�N�j�B��q�̂悤���e���͔C�ߒD��Ɏ��s�������A��B�̒}���N�ֈ�̏��̂𒅁X���D���đ�a�����̓ԑq�Ƃ����B
���ՋI535�N�@
�u�}���̕�g�ԑq�E���ԑq�A�L���̖���ԑq�E�K���ԑq�E�̓��ԑq.�唲�ԑq�E�䎭�ԑq�A���̏t�����ԑq�A�A�A�i�ȉ��d���E����E���g�E�I�E�O�g�E�ߍ]�E�����E��і�E�x�͂̊e�����ɂP�`�Q�̓ԑq��L�j��݂����v
��B�ł͖L������ł���B�L���͉��_�V�c�̖{������������i��q�j������肪��������������Ȃ��B�ֈ�̖{���n�Ǝv�����O�E�}��͎�Ƃ��Ę`�����Ǝ��g�A���邢�͋�B�������E�h�䎁�����D��i�߂��̂��낤�B����A���ՋI�̐V�ݓԑq����B�݂̂Ȃ炸�e�n�ɋy��ł��邱�Ƃ́A�}���N���̂��e�n�ɂ������\�����������A�}���N�̓����i��F��c�Ƃ���z�����Ȃǎ����A�F���I�j�ɓԑq�������o�������̂�������Ȃ��B
�X�ɁA���ՓV�c�͋�B�N���Ƃ͕ʂ̔N�������Ă��悤��[5]�B���̔N�A�O�q�����u���{�V�c�ꑰ���I�v�̎���������A���N���u���V�����N�v�Ƃ����B������������e�����u��a�����v���������ĂĘ`���ɕ��ڂ��ƍ��r�����悤���B
���ՓV�c�͂��̂���J�s���Ă���B
���ՋI534�N
�u��`���̌������i�܂���̂��Ȃ͂��j���J�s���A�������{���ƈׂ��v
�u��`���v�͗Y���I�ɂ���悤�ɋ�B�`���̎��̍����ł���B�������͖L�O�����i���������c��S���t�������j���B���̍����͈��ՋI�Ɂu�L���ɍő��̓ԑq���v�Ƃ���i���ՋI�A��f�A���߈ȉ��Ō��j�B�����̂��鍁�t���ɂ́u�͓����̕�v������{�����Ǘ��A���ՓV�c�˂Ƃ̓`��������Ƃ������A�~�������炱��͌�`���낤�B
�u��a��������B�`���ɑJ�s�v�ƋL���Ă���B�����Ȃ�d�厖�т����A�]�����ł���B�������ł��̌n�I�Ɍ�����Ă��Ȃ������B���������߂����ƁA���̌�̏��܂�Ŕ���Ȃ��Ȃ�B�����ł܂��A���̑J�s�����Ȃ�����B�ł��鍪�������߈ȉ��Ō�����B
[5] ��B�N���Ƃ͕ʂ̔N���@�@�@��B�N���́u�u��(531-535)�E�m��(536-540)�E���v(541-551)�v�Ƃ͕ʂ́u��a�i531�|537�j�E��F�i538-543)�E���m�i544-548�j�j�ŁA�ꏑ�u�a���N�_�v�݂̂ɂ���B���̎����A�`���̋�B�N���ȊO�ɔN���𗧂Ă���̂́u���V���v�i532�N�`538�N�`�j����������a���������Ȃ��B�������A��a�V�c�̑��ʔN�ƘA�����Ă��Ȃ��B����ƂāA�e���̖v�N�i356�N�j�Ƃ��A�����Ă��Ȃ��B
��147�@���ՓV�c�̓�܂̓ԑq�͌�ɑh�䎁�̖{���u��O�v�@�@�_�@
���ՓV�c�͑J�s����Ƒ�a�̍c�@�i�m���V�c�̏��i�ނ��߁j�j�Ƃ͕ʂɎO�܂𗧂Ă��Ƃ����B�O�܂Ƃ͋����j�l��b�i�����̂��ЂƁj�̏��ю�Q�i���ĂЂ߁j�A���̖������L�Q�i������Ђ߁j�A�����ؘ@�q�i�����сA�͓��������n���j��A�̏���Q�i�₩�Ђ߁j��ŁA���ꂼ��ɓԑq��^�����A�Ƃ����B
���ՋI534�N
�u�唺��A�����A�t�����A�A�A�����c�i���͂肾�j�ԑq�ƍ����̓c���Ƃ��ȂĎю�Q�ɁA����ԑq�ƍ����̎R���Ƃ��Ȃč����L�Q�ɁA��g�ԑq�ƌS����������ڂ�i�c���H�j���Q�ɋ����v
�����ŁA��܂̏����c�E����̔��n����������i��g�ԑq�ɂ��Ă͌�q�j�B�ю�Q�ɗ^����ꂽ�����c�͎��̎j������u�����i�ނ��͂�j�v�ɋ߂��B
�Ԗ��I552�N
�u�S�ϐ������A�A�A�߉ޕ����������������A�A�A�i�V�c�j�i�h��j��ڏh�H�Ɏ��݂ɗ�q�����ށB��b�삢�ĎA�x��������c���Ɉ��u���A�A�A�����̉������ƈׂ��v
552�N���A�����c�E�����E�������͋߂��ɂ��苤�ɑh���ڂ̖{���n�ɂȂ��Ă���B
����A�ȉ��̎j������u�����L�Q�ɗ^����ꂽ����͌�̐��s�I�ɂ�����䎛�̒n�ƍl�����A���䎛�͕ʖ��������E�L�Y���Ƃ����A�����ɂ������h��n�q�̖{���ɋ߂��v�Ƃ킩��B
���s�I590�N
�u�i�h��n�q�����킵���j�w���P�M���A�S�ς��҂�A���䎛�ɏZ�ށv
���������N�u���v���i�ނ��͂�j�a���A�A�A���䓹��ɍ��v
��a�u�i�]�ˎ���j
�u���䎛�͕ʖ��������E�L�Y���ł���v
����E�����E�L�Y�͓����n����ƍl������B�u�h��ڈ��L�Y��b�ƌĂꂽ�v�i�Ė��I�j�ƍ��킹�l����ƁA�����̒n���͑h�䎁�̖{���ƂȂ��Ă���B
�����{�I751�N�u����(��������)���b�^�l�������A�֗]�ʕ�{(�p�̓V�c)�E�����{(���ՓV�c)��F��c�̌䐢�A�������b�j�l�͑�b�ƂȂ�A������(���Ă܂�)��A����Ɍ���ċ����j�l�b�ƋL���A�A�A�]�ݐ����A������b�����߂Đ�����b�ƈׂ��A������ɗ��i���j���A�h��������Ɏ������Ƃ��A�Ƃ����A��[���]��ʋ������b�A�A�A���̎����ؖ����v�@
�܂��A�p�̋I529�N�Ɂu�����j�l��b�I���v�Ƃ���A���ՓV�c�i534-�j�Ɏd���������j�l�͕ʐl�ł��낤�B�����͔�O�̍����ƌ�����B
��148�@�h�䎁�{���͔�O
�ł́A�h�䎁�̖{���͂ǂ��ɂ��������B�ȉ��̕������炻�ꂪ�킩��B
���s�I591�N
�u�I�̒j���C�h�H�A�����̋���Ǖv�A�A�A����̉G�ޗǐb��叫�R�Ƃ��A���P�̌R��́i�Ђ��j���Ē}���ɏo�������v
���s�I592�N
�u�i�h��j�n�q�A�A�A�V�c�i���s�j��U�i�����j���A�A�A�w�n�i�͂�܁j��}���̏��R�Ɍ��킵�����ɂ��O����ӂ�Ȃ���A�Ƃ����v
��q����悤�ɁA�����̎����͏�{���i�`�����ƒ����̉����j�̓Ɨ����x������h��n�q�̌R���s���ł���B
591�N������A���̒n��Ƃ́u�I�v�u�����v�u����v�̒n���̂���Ƃ��낾�낤�B��B�ł����̒n���������͔�O����S����i�����j�E��O���ÌS�����E��O�O���S���ł���i���������������O�n���j�B
592�N������A�u�h��n�q�̖{���͒}���ȊO�̋�B�v�ƍl������B���̍����́u�n�q�����s�V�c���E���i��q�j�A�}�����������R�����H�w�n��h���ł���n��͒}���ȊO�̋�B���v������ł���i592�N���j�B
�ȏォ��A�u�h��n�q�̖{���͔�O�v������B
��152 �Ԗ��V�c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2012�D3�@�lj��j
29��Ԗ��V�c�i539�|571�N�j�͌p�̓V�c�̒��q�A��b�͑唺������A�E�������`��A�i�i4�j���Q�Ɓj�E�h���ڏh�H��b�Ƃ����i�Ԗ��I�C���L���j�B�Ԗ��I�͕��G�ł���B
�i1�j�Ԗ��V�c�͑�a�̌p�̓V�c�̒��q�Ƃ��đ�a��铇���h�{�ő��ʂ����Ƃ����B���̌�A��g�j�Ë{�i�Ȃɂ�̂͂ӂ�݂̂�A��B�j�Ɍ�K���Ă���B��B���̂����X�����A�����̔�d�����܂������牼�{�������K�����̂��낤�B���̑�a�Ƌ�B�̓�ʐ����j�Ƃ�f�킹�Ă����B
�i2�j�`���͔����o������������i���L��Ƃ����ǂ�����Ȃ��A�@���j�A�Ƃ��������j�̗�������Ė������a�ɉ����t�����B�`���ɑ����Ĕ����o���ɒ��͂����̂͑�a�����A�����p�́^�����e���`�Ԗ��V�c�ł���B�Ԗ��V�c�̓o�ꂷ�镑��͋�B�������B
�i3�j�Ԗ����̎�v��b�͑唺������A�i�͓��A��ɔ����j�E�������`��A�i�v�����e���̑���A�}���Ǝ�S�j�E�h���ڏh�H��b�i�{���͔�O�����c�j�Ƃ����B�唺�����͋Ԗ����}���ɑJ��������ɔC�ߖ��Ŏ��r���Ă���B�Ԗ��I�̑唼�͔C�ߕ��������ł��邪�A���ʂ͂Ȃ������悤���B�㔼�̋L�q�́u�r���h�Ɛ����h�̘_���v����ł���A��q����悤�ɘ`��������̘_���ł���B
�i4�j�u�������`�͘`������̑�A�v����������L�q������B���ՋI�̂��铐���杂Ɂu��b�C���L���������̂ɕ������`����A�Ƃ��ēo�ꂷ��v�i���ՋI���N534�N�A���`�̏��o�j�B�����������`�́u��a�����A�Ƃ��ēo�ꂷ��O�ɕʂ̒���̑�A�A�����`������̑�A�ł������v�Ɖ������B
�i5�j�u�`������̑�b���`�v���u�鉻�E�Ԗ�����̑�b�ɔC���v�ł͊i�������Ӗ�����B���`�̊���͍l���ɂ����A�������B������͕ʂ̉��߁u�Ԗ��V�c�͔��`��b�̂���`������ɎQ�悵���v�Ƃ�������������������B�����u�@�卑�ł���`������ɂ͕K�v�ɉ����Ę`�����̉����͏��R���Q�悵���v�Ƃ����펯�I�ȗ����ł���B�Ԗ��V�c�i�剤�j�̋�B�؍݂��l������ƁA�Ԗ��V�c�͎����̋�B���{�Ŏ����i�剤�j�̒���i�����R�̐����̐��j��������A�K�v�ɉ����Ę`���i�V���j����ɎQ�悵���\���������B�u�`���͏@�卑�A��a�͘`�����̕M���A�Ԗ��V�c�͕S�ϔC�ߖ���C���ꂽ�`�����R�̑�\�A�Ƃ�������v�Ɖ������B
�Ԗ����́u�ֈ�̗���A��a����B�ɋ��_�Ə��̂Ċg�傷��D�@�v�����������A��a�ȗ��̑�b�����Ȃ��Ȃ�u��B�ɔ�d�����߂����ʁA�`���Ɏ�荞�܂�Ă��܂��낤���v�������Ă����i���͎Q�Ɓj�B
��153 �����`���@�O��ނ̓`���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2012�D4�@�lj��@�j�@�@�@�@
�@�Ԗ��I�`�q�B�I�ɂ͕����_��杂������B����𐳂����������邱�Ƃ́A�`���Ƒ�a�̊W�𗝉������ŋɂ߂ďd�v�ł���B�]���A�����`���̔N���ɂ��Ă͎O��₠��A�ǂꂪ�^���ŋc�_����Ă����B
�@ �@����ł͋Ԗ��I552�N�Ɂu�S�ω�����̕����E�o�T�Ȃǂ̑��蕨�ɋԖ��V�c���w����قǂ̖��@�͕��������Ƃ������x�Ɗ���x���v�Ƃ���̂��u�������`�v�Ƃ���Ă���B�u���`�v�Ƃ���̂́u����ȑO�ɂ����I�ȓ����͂�������������Ȃ��v�ƁA�ʐ��ɑR����\�h�����Ă���B
�A �@�ʐ��Ƃ́u���������N538�N���Ɂw���@�n�߂ēn��x�Ƃ���v�Ƃ�����̂����A�㐢�̉��M�Ȃǂ���悤�ŁA�M�����ŋ^�₪����A�Ƃ���Ă���B
�B �@�X�ɁA�u��B�N���Ɂw�m���x�i536�N�`�j�����邩��536�N�ȑO���v�Ƃ���������邪�A��B�N�����ꎩ�g�̌㐢�U������������肵�ċc�_�������B
�����c�_�ɑ��A�M�҂́u�O���Ƃ�����Ӗ��Ő������B�������e�Ɠ����҂��قȂ�v�Ɖ��߂���B�ȉ���������B
(1) �������`�͋�B�N���u�m���v�i536-549�j�ȑO�ƍl������B��B�N���͘`���̔N���ŁA�`���͓쒩�ɒ��v���Ă����B�]���āA���̕����͓쒩�����ł��낤�B
(2) �`���ɖk�����������`�����̂�538�N�ł���B
�������������N���тɗ��L���ޒ��i�Čf�j
�u��`�����@�A�n�i�͂��j�߂��A�A�A�i�鉻�j�V�c�̌䐢�A�h���b��ڏh�H�d�����Ƃ��A���V�����N�Ύ�����߁i538�N�j�\���x�i�킽�j������A�S�ύ��������̎��A���q�����тɟ̊���y�ѐ����N���ꊪ⸁i�͂��j��n���A�A�A�v
�S�ς�472�N�ȗ��k鰂ɒ��v���Ă��邩��A���̕����͖k�������ƍl������B�S�ω������サ�������̑����u��`���v�͘`�����̖��ł���i�Y���I�ɓ����A�O�́j�B�`���ɂ͊��ɕ��@���`����Ă��邩�琳�����́u�k�����@���`�v�ł��邪�u�n�߂��{���̕��@�i�k�������j���n�����v�Ƃ����������̗���̕\���ł��낤�B�u�i�鉻�j�V�c�̌䐢�v�Ƃ���͔̂N����\�������ŁA���e�͘`������̘b�ł���B�h���ڂ͘`������̑�b�ł���B���̍����́A�����ʼn���悤�ɂ��̎��_�ł͑�a����͕��@�ɊS�������Ă͂��Ȃ��B�鉻�V�c�͂قƂ�Nj�B�ɂ͗����A�����e���Ό�p�҂��㗝�Ƃ��ĕS�ςƌ��ɓ�����A�S�ω��̑��蕨��`�����ɒ�����̂��낤�i�O�X�ߎQ�Ɓj�B
�`�������쒩�������m���Ă������A�V���k�������ɂ͐T�d�������悤���B�����L�q��v��ƁA
�������������N���тɗ��L���ޒ��@�Â��i�v��j
�u�V�c���Q�b�Ɏ������Ƃ����P�b���_���h�������A�Ƃ�h���ڂ����߂��̂ŁA�V�c�͎��݂Ƃ��Ĉ�ڂɂ����������������B���̌�A�r���h��������Ɛ����h�h�䎁�̘_���������B�j�ڑ�b�������i570�N�j������P�b���͓V�c�̋����ē��ɂ������A�����E�o�����g�]�i�}�O�j�ɗ������v
�Ƒ����B������ċ������̂����������Ƃ����B�`�����ɂ͓쒩�����h�i���ށj�E�_���h�i��������A���͔҉�j�E�h���ڂ�k�����������h�i�V���j���������ƍl������B
538�N�̎��_�ŕ����e�����S�ϕ����̒���͂��Ă��A��a�͂܂������ɖ��S�������悤���B����A570�N�i�������g�]�ɗ����j���_�ł͎����̂悤�ɑ�a�͖k�������`���E�����ゾ����A�r���h�ł͂Ȃ��B�r�����������͓̂쒩�����̘`�����ł���B�]���āA�����́u�V�c�v�͘`�����̂��Ƃł���B��f���ޒ��́u�V�c�v�͓��{���I�ɍ��킹�ď����������̂��낤�A���{���I�Ɛ�������B
(3) ��a����ɕ����i�k�������j�����`�����̂�552�N�ł���B
�Ԗ��I552�N
�u�S�ϐ������A�A�A�߉ޕ����������A���W��E�o�_������������A�A�A�V�c���������A����x�A�g�҂��ق����]���A���͐̂��A�����\���Đ��̔@�������̖@�������������A�A�A�R��ǂ������猈�߂��A���Ȃ킿�Q�b�ɗ�₵�ĞH���A�A�A�h���b��ڏh�H�t���ĞH���A�i�ȉ������_�j�A�A�A������A���`�A���b�A���q�A�������t���ĞH���A�i�ȉ��r���_�j�A�A�A�V�c�H���A�X�������l��ڏh�H�ɕt���Ď����ɗ�q�����ށv
�q�B�I585�N
�u�A�A�A���̌㍑�ɉu�C���s���A�A�A������A���`�E���b�A���q�A�t���ĞH���A�A�A�V�c�H���A�t����ʂ�ɂ�����A�A�A�������g�̖x�]�ɗ������A�����ɉ��������v
�Ԗ��V�c�͔C�ߍċ����w�����邽�߂�����B�ɗ����i�Ⴆ�u��g�j�Ë{���K���v�Ԗ��I540�N�j�B�S�ω��̌���i�i552�N�j��538�N�ƈ���ċԖ��V�c���ł��낤�B�Ԗ��V�c�́u����x��v�����B�Ԗ��V�c�͕������a�Ɏ����A���Ă���B���ꂪ��a�̕������`�Ɠ`�����Ă���B�O�f���̑O���u��a�ւ̕������`��552�N�v�͎j���ƍl������B
(4)�@�Ԗ��I552�N�̌㔼�u�V�c���h���ڂɌ����Đ����������i�������N�ł�538�N���j�v�A�q�B�I585�N�́u�V�c�͕������`���̔r����t�������i�������N�ł�570�N���j�v�͑O�X���̉������N�Ɠ����ŁA�`������̎����ł���B�u�`��������̑h�䎁�i�k�������j�E�������i�_���j�̎哱�������Ƃ��̏�ɂ��`�����i�쒩�����j�̎O�b�̘_���v�Ɨ�������Ɣ[�����s���B�`�����͓쒩�����h�ł����Ėk�������Ɂu����x��v����͂����Ȃ��B��N�i590�N���j�̑����v�k�ǂ��{���ł���쒩�������x���������Ă���i��{���͌�ɖk�������ɓ]���A�攪�́j�B�`���͌��ǖk������������Ȃ������悤���B�q�B�I�́u�V�c���h���ڂɌ����Đ����������v�u�V�c�͕������`���̔r����t�������v�́u�V�c�v�́u�`�����v�ƍl������B���̂��Ƃ��u�h���ڑ�b�A�������`���܂��`�������b�v�̖T�Ƃ��Ȃ��Ă���B
(5) �ł́A�Ȃ����{���I�́u�`������̕����_���v���a����̘_���̂��Ƃ��L�q���Ă���̂��B����͋L�q�̖ړI���u�����_���v�ł͂Ȃ��A�u�������E�h�䎁�̑����v�����炾�B���̊ϓ_�ł́u�`�����v�Ɓu��a�V�c�v�͋��ʂ̗��ꂾ�B�u�������̐ꉡ��j�~���ׂ��h�䎁���������Ă�`�����v�ƁA�u�`������ɎQ�悵�����ʁA�͓��������i�e���Όn�j����B�������i�{���j�Ɏ�荞�܂�āA�R��h�䎁�ɋ߂Â���a�V�c�v�̗��ꂪ�߂����߁A�`�����Ƒ�a�V�c���������Ă���B�u�`������Q�b�̕����牮�����ɕq�B�̍c�q�B���Q���v����̗Ⴞ�B����ɂ�����Ƃ��āu�q�B�E���ÁE�F��������S���h�䎁�̗����v�i���́j�ւƑ����B�����Ř`���j�����ꕔ���p���ē��{���I�ɍڂ��Ă���悤���B�s���ł�����ł��Ȃ��B�����A�u�V���i�`�����j�v�Ɓu�V�c�i�܂��͑剤�A��a�j�v�𗼕��u�V�c�v�ƕ\�L���Ă���B
���{���I�́u�`���s�L�ځv�������Ƃ��Ă���A�Əq�ׂ��B����ɂ�������炸���������u�V���i�`�����j�v�̌������u�V�c�v�Ƃ��ĕ`����Ă���A�Ƃ���̂͂��s����`�̉��߁A�Ɣ��ꂻ�����B�������A���������`������Ƒ�a���삪���̎���ɂ��܂�ɐڋ߂������ߓ��ꗧ��̖��Ɍ����āu�`�����v���u�V�c�v�ƕ\�L���āu�`���s�L�ځv�ɖڂ��Ԃ������{���I�̋���̕ҏW�Ǝv���A���ՋI�`�q�B�I�œ��ɕp�o����B����ɂ��Ă͎��͂ŏڏq����B �u�`���s�L�ځv�͕K�R�I�Ɂu��B�������s�L�ځv���B�Ȃ���O�I�ɕ������`�`�����牮���L�ڂ���Ă��邩�A�͓������R�ƍl������B
��158�@�V����V�c�ƕ\�L
�X�ɍ������������q�B�I���u�`�����i�V���j����a�V�c�i�剤�j�������w�V�c�x�ƋL���Ă���v�ɂ���A�ƍl����i�O�͂ŐG�ꂽ�j�B�L�I�́u�`���s�L�ځv�������Ƃ��Ă��邩��A�{���͘`�������L�q���Ȃ��B�������A�����e���Έȍ~�̑�a�V�c����B�Ŋ��A�`������Ƌ߂Â������ʁA�`�����̋L�ڂ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���ʂ��������B�����ŋI�Ҏ҂́u�`�����i�V���j�Ƒ�a�V�c�i�剤�j���w�V�c�x�ƕ\�L���邱�Ƃɂ���āA�L�ڂ��Ȃ���L�ڂ��Ă��Ȃ��`�v��_�����悤���B�u�V���E�V�c�E�剤�Ȃlj����N���X���������������̂Łw�V�c�x�\�L�ɓ��ꂵ���A�ƌ�����ł���B����ɂ���āu�`��������a�V�c�A�Ƃ�����ǂ������邩������Ȃ����A���̂悤�ȋ��U�L�ڂ͂��Ă��Ȃ��v�Ǝ咣���邱�Ƃ��ł���B�Y���I�́u����v���u���L�͂������A����Ƃ͌����Ă��Ȃ��v�ƌ�����ł���B��ǂ����̂͏��m�̏�A�u�q�B�I������w�V�c�x�Ƃ���Εq�B�V�c�̂��Ɓv�Ǝv���͓̂ǎ҂̏���A�Ƃ������ꂾ�B
���̂悤�ȕҏW���Ԗ��I�i�`����b���o��j�E�q�B�I�i�牮�E�n�q�_��杁j�E�p���I�i���j�E���s�I�i�`������Q�b�ɂ��牮�����j�Ƒ����B���O��̎���͕q�B�E�p���E���s�����A����͘`������ł���B���̎����̋L�I�ɂ͑�a�V�c�Ƙ`�����i�V�c�j�̗����̋L�������݂��Ă���B�Ⴆ�A�����q�L���͋Ԗ��I�\�ܔN�i554�N�j�ƕq�B�O�L568�N�i�Ԗ���\��N)�ɓ��L����Ă���B�q�B�Ƙ`�����̗����q�L���̗��������݂��Ă���悤���B
���̂悤�ȕ\�L�������ʂɁA�܂����{���I�S�ʂɌ�����ł͂Ȃ��B��L�̂悤�ȕK�v�ŏ����ł����āA�����p�ӏo���鎞�Ɏg����悤���B
�q�B�I������Ɓu��a�剤�i�������݁j�Ƃ��đ��ʂ�����A�`������̑�b�����牮��A�Ƒh��n�q��b���㌩���ƂȂ�w�`�����M���̑�a�剤�x�Ƃ��Ę`������ɎQ�悵���B��a�ȗ��̑�b�͋��Ȃ��Ȃ�A��a�����͘`������ɔ��Ύ�荞�܂ꂽ�v�Ɖ��߂���B
�@
��159 �@�`���ƕ������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2014.9�@���M�@�@2012.3�@�V�j�@
��������300�`400�N�Ԙ`�������ɁA�x���͑�a�����ɐb�]�����ƍl������B��O�͂ł́u�������͍��V���Ńj�M�n���q�E�z�A�J���E�j�j�M�ȂǃA�}�e���X�ꑰ�ɐb�]���������B���g���̓V�~��ɏ]���Ċe�n�ɕ����ꂽ���A���������̒��S�}�����p������B�`���i�z�A�J���n�j�̊O�ʂƂȂ�����B���������������@�ƂƂȂ����v�Ɛ��������B��]�̊W�͗͊W�ł͂Ȃ��A���j�I�ɗR�����錈�莖�ƍl�����Ă����悤���B��B����������m���Ƌ��ɉ͓��ɕ����ꂽ�����e���͋�B�ɖ߂��ď@�Ƃ����ł̂��オ���������v�B�����e���̗����������p�����������`���������@�Ɠ���ɂȂ����B���̌�A�`���̖{��������쒆���̈Ǝ�Ɉړ������̂́A���������O�ʂƂ��Ę`���c�q���@�܂̗��Ɉ͂����݁A�{�܂Œ�������ƁA�Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���B�u�S�ϏьÉ�����`���ɑ���ꂽ���x�����������_�ł���Ώ�_�Ђɕ�[����Ă���v�Ƃ����j���́u�����n�`���������Ƃƕ������ꎋ�i���������j���Ă����v�Ƃ����\�����玦�����Ă���B�A���A������u���������v�Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A�����牮����杁i���߁j�������Ă���B�b����������z����Ɖ��ƁE��������v���Ă����j�~���Ă���B
��160�@�����牮���������@�`�������̕���
�����牮�i�}����g�j�͕������`�̎q�Ř`���̑�A�i��q�����j�B�����e���̐��ʂ������p���Ő��͂��g�債�A����ɘ`��������Őꉡ�����B�`�����Ƃ�����ɔ��������B���s�I587�N�ɕ����牮����杂�����B
���s�I587�N
�u�h��n�q�h�H��b�A���c�q�ƌQ�b�Ɋ��߁A�����牮��A��łڂ����Ƃ�d��A�������c�q�A�|�c�c�q�A���ˍc�q�A��g�c�q�A�t���c�q�h��n�q�h�H��b�A�i��11�Q�b���j�A�A�A�Ƃ��ɌR���𗦂��A�A�A�v�i�Čf�j
���̎����ɂ���ĕ����牮�Ƃ��̎q��͎E���ꂽ�B�]���A���̎����́u�������Ƒh�䎁����b�Ƃ��Ē��荇���āA�h�䎁�����菟�����v�Ɖ��߂���Ă���B�������A�������͂��̌���`�����Ƒ�b�Ƃ��Ă̒n�ʂ�ۂ��A�h��n��b���嗬�ƂȂ邱�Ƃ͖��������B�������ɑ����Ď������������̂͑h�䎁�ł͂Ȃ��A�`�������g�������B���̂��Ƃ͑����v�k�ǁi600�`608�N�j�̗Ⴉ�画���i�@���A���͂ŏڏq����j�B
�@�`���͑�a�̗͂���Ĕֈ�̗����������A�h�䎁�̗͂���ĕ����̗͂����E�����B�`�������͕��������悤���B
��161��161 �@��a�����i��B�j�̂��̌�@�@�p���E���s�E���Á@�@�@�@2013.7
�q�B�V�c�̎��A�p���E���s�E���Â̊e�V�c�͑�a�����i��B�j�Ƃ͂����A�`����b�������E�h�䎁�̑����ɖ|�M����A���S������A��B������āA���L�̂悤�ɉe�������B
(1) �@�������Ƒh�䎁�͗p���V�c���ʂɂ�������đ����Ă���B�Ⴆ�u�h��n�p���V�c���ʌ�A���䕔�c�q�����ʂɈق������A�����牮��������x�������v�i�p���I�j�B�X�ɁA�u�����牮�Ƃ̑Η��őh��n�q�����䕔�c�q���E�����v�i���s�I�j�A�Ȃǂ�����B�����A��a�����i��B�j�̌p�����ɕ����e���i��a��b�j�̐��ʂ������p������������������Ă���B����ł��h�䎁���p�����ʂ��哱�ł����̂́A�q�B�̍c�@���h��n�̐��Â�����A�ƍl������B
(2)�@�@��a��������S�������h�䎁�͑�a�����Ƃ̊W���Ȑ��s�V�c�ʂ����A���̐��s�V�c��U�i�����j���đ���ɑh��n�̐��Â𗧂ĂĂ���B�q�B�V�c�̌p�k�̉���F�l��Z�c�q�������u���āA�ł���B
(3)�@��a�����i��B�j�͑�����B������A�h�䉻����đ�a�̓`��������ꂽ���Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�Ⴆ�A�p���`�F���̌�˂͋�B���̉~���E�����ŁA�q�B�̑O����~���ƈ�����悷��i��q�j�B
(4) ��q����悤�ɁA��a�����͐��ÓV�c�̎��ɑ�a�A�ґJ�s���邪�A���ꂪ�\���������Ƃ́u��a�����i��B�j����B������h�䉻���ꂽ�Ƃ͂����A��a�̍�������������邱�Ƃł��鉤���A������a�����ł��������Ɓv�������Ă���B �@
��162�@�u�@�������w���̏�{�@�c�������v�k�ǁv��
����4�߂͋�B�ɑn�����ꂽ�V���������u��{���Ɓv�ɂ��Ăł���B
�@�����̎߉ގO�����́A�������q���J�������̂ƌ����Ă��邪�A���̗R�����L�^�������w���ɂ́A�������q�̎��ւƖ���������e�����邱�Ƃ��_�c���Ă�ł���[2] �B
�@�����߉ގO�������w��
�u�@��31�N�i621�N�j�A�S�O���@�����A�A�A���N�A�A�A��{�@�c���a�]�i��j���炸�@�A�A�A���H���@���i���j���Ȃ��ę��������������A�A�A���ŎO��i����ۂ��j�Ɉ˂�A���i�܂��j�Ɏߑ���ׂ��A�A�A2��21���A�A�A���@�������A�A�A�����@�c�o码i2��22���j���A�A�A�i623�N�j�߉ޑ����A�A�A�h������i����j��A�A�A�g�i�n�Ǝ�~���Ŏt���v�@
�@���̒����ȑ��́A�@�����̈ڒz�Č����i708�N�ڒz���A���厛�N�\�j�Ɉړ����u���ꂽ�ƍl�����邪�i��\�͎Q�Ɓj�A�������q�̂��߂ɍ��ꂽ���̂łȂ����Ƃ́A�ȉ��̈Ⴂ����m���߂���B
(1)
�v�N�̈Ⴂ�B���w���̑Ώۂ́A�@��32�N�i622�N�j2��22���v�B�������q�́A����29�N�i621�N�j2��5���v�i���ËI�j�B
(2) �o��l���̈ʂ̈Ⴂ�B��{�@�c [3] �E�S�O���@�i���@���c��̕�j�E���H���@�i���@���c��E�V�c�E�剤�̐��ȁj�ȂǁB�������q�̈ʂ͑��q�ŁA�V�c�E�剤�E�@���ł͂Ȃ��B���v�l�͋k��Y���܁i�@�łȂ��j�B
(3) �@�̖v�N�B��{�@�c�v�̑O���ɖv�����@�ɑ��A�������q�̑��v�l�̔܋k��Y���́A���q�v��ɒ��������ēV�����J������点���i638�N�j�B
(4) ��{�@�c�͓o��l����̈ʂ���A�V�q�����̂��u�@���v�N���̌��Ă��ƍl������B
�ȏォ��A���w���̐l����{�@�c�͐������q�ł͂Ȃ��B�i��{�@�c���������q�j
�����ŐV���ȉ��߂Ƃ��āu��{�@�c�������v�k�ǁv�����o���B32�N�Ԗ@�������i��B�N���j���ێ��������V�q�A�@��17�N�Ɍ��@�g�𑗂����u���o���鍑�̓V�q�A�����v�k�ǁv�ƍl����ꂽ�B�����u��{�@�c�������v�k�ǁv���@�O��[2]���B�M�҂����N���̉��߂�M���Ă����B
[2]�@�u�߉ގO�������w���v �u�Ñ�͋P���Ă����V�v�Óc���F�@1985�N�@�����V���Ё@�ɋ������B
[3]�@�u�@�c�v�@�`�n�c��͂���܂ł̍ō��ʂł���O�c�i�V�c�E�n�c�E�l�c�j�̏�ʂƂ��čc������̂����B�@�c�͎O�c�Ɠ����ƍl����ꂪ�A��@�E���@�Ȃǂ̌ď̂���A�V�q�����̂����Ƃ����߂ł���B�@���N���������Ă��邩���{�������ʂ����̂łȂ��A��{�@�c�ƂȂ��čc�ʂ��p���������̂��낤�B
��163�@��{���̓Ɨ��@�@��O�̒n���@�@�@�@�@�@�@�i2011.6�@�lj��j
�������A��B�N���͕ʂɂ���i�[���E���M�E��]�E�����E�苏�E�`���A589�N�`622�N�j�A��{�@�c�͖@���N����ʂɌ��Ă��ʂ̉����A�Ƃ����������シ��B�ώ����u��{�@�c�������v�k���v�� [4] ����������B�ϐ��́u��{�@�c��591�N�ɋ�B�N���Ƃ͕ʂ̖@���N����n�n�����ʉ������B�w��{���Ɓx�Ƃ���B��O���{�{��{���ɂ��Ėk��B�̘`���������ēƗ������v�@�Ƃ��A���̍������u�@�����߉ގO�������w���v�i�O�o�j�y�ю��̋L�^�A�Ƃ��Ă���B
���s�I591�N�u�I�^�E�����^�E����^�A�A�A�����đ叫�R�Ƃ��A���P�̌R��́i�Ђ��j���Ē}���ɏo�������v
���s�I592�N�u�i�h��j�n�q�A�A�A�V�c�i���s�j��U���A�A�A�w�n�i�͂�܁j��}���̏��R�Ɍ��킵�����ɂ��O����ӂ�Ȃ���A�Ƃ����v
���ËI595�N�u���R��}����莊��i�A��j�v
�@�����w�I�^�x�͔�O����S����i�����j�̏��R�A�w�����^�x�͔�O���ÌS�����̏��R�A�w����^�x�͔�O�O���S���̏��R�Ǝv���A���������O�ł���B�w�}���ɏo�āx�Ƃ��邩���O����}���ɏo�Ă��Ă���B���s�I�����琒�s�V�c���R�̎x�z�҂Ǝv���ė������A���s���E����Ă��̌R���͓����Ă��Ȃ����琒�s�R�ł͂Ȃ��B�R�ɖ��߂��Ă���͔̂�O��{���Ƃ���h��n�q���B�w�O���x�Ƃ��邩��w�C�ߕ����R�x�Ɖ��߂���Ă������A�̌R��4�N���}���ɒ����i�����j���Ă��邾���ŔC�߂ɓn���Ă��Ȃ��B�̌R��}���ɑ�����591�N�͏�{�@�c����B�N���Ƃ͕ʂ̖@���N�������Ă��N���i�@�����߉ގO�������w�����j�B����炩��591�N�ɏ�{���i��̏�{�@�c�A��q�j�͑h��n�q�̎x���Ŕ�O�ɐV�����𗧂āA�V�q�����̂��A�N�������āi�V�q�̐ꌠ�j�A�̌R�����Ē}���̘`���i�������Ǝ�S���{���j�Ɏ��Ђ����ēƗ������F�������A�Ɖ��߂����B������w��{�����E��{���Ɓx�Ƃ����B��{���Ƃ͌�ɔ�O�W�{��ɓa�őh������i�n�q�̎q�j�E�ڈ��Ă���i�c�ɋI645�N�A�����̕ρj�B�w��ɓa�x�͓V�q�̐������Ӗ�����B
���{���I�̋L�^������ƁA�h��n�q�͈���Ŕ�O�̑�a�������x�z���Đ��s�V�c���E���A�h��n�̌����̔Z�����Â�V�c�ɂ��Ă���B�����ŐV�����i��{���Ɓj��S���ő�b�ƂȂ�A�̌R��}���ɍ��������Ę`�������������B4�N�Ԃ̒����œƗ���F�߂����A�키���ƂȂ��������m�肵���A�Ɖ��߂ł���B�ȏオ�ϐ����B
�u��{���Ɓv���́A�`���������쒩�̍����̐����痣�E���ēV�q�̐ꌠ�ł���N���i��B�N���j�����Ă����Ƃ��_�@�Ƃ��āA��������h�䎁�������B�ɓƗ������𗧂Ă����A���������͊O�ʂƂ��ĉ�����ꉡ����������悭�����Ă���B
[4]�@��{���Ƃɂ��ā@�@�u�������Ƒh�䎁�Ə�{���Ɓv�@�ώ��@���_�Ё@2004�N
��166�@���ÓV�c�u��a�����c�{�v�ɑJ�i���j��@�@�M�҉��߁@�@�@�@�i2011.7�@�lj��j
��{���Ƃƕ���������a�����i��O�j�͋��ɑh�䎁���Ղ����B�q�B����̂��ƁA�h�䎁�͌p�k����F�l��Z�c�q�i���q�j�������u���đh��n�̗p���E���s�E���Â��a�����i��B�j�̓V�c�ɑ��ʂ������A�ƑO�q�����B
���ÓV�c��592�N�ɖL�Y�i�Ƃ��j�{�ő��ʂ������A603�N�ɏ����c�i���͂肾�j�{�ɑJ�����i�������j�i���ËI�j�B
���ËI603�N
�u�����c�{�ɑJ��v
�L�Y�E�����c�̔��n�ɂ͏�������A�ς͑����̏؋��������āu
�L�Y�͔�O�O���S���ؖL�Y�A�����c���w�����̋ߕӁx�ƋԖ��I�ɂ��邩���O�O���S�����i�����ꌧ�����s���̌�����߂��j�v�Ƃ��Đ����͂�����B
�Ԗ��I552�N�u�S�ϐ������A�A�A�߉ޕ����������������A�A�A�i�V�c�j��ڏh�H�Ɏ��݂ɗ�q�����ށB��b�삢�ĎA�x��ŏ����c�ƂɈ��u���A�A�A�����̉Ƃ����ƈׂ��v
���̌��Łu552�N���_�ł͔�O�ɏ����c�̒n������h���ڂ̗̒n�������v�ƌ�����i�����c�̔�O���A�O�͂Ō������j�B
�������u�����c�{�v�̔��ɂ͂��̐悪�K�v�ŁA�M�҂̉��߂́u603�N�ɂ͐��ÓV�c�͔�O�L�Y�����a�ɑJ��A���̋{��c���̔�O�����c�ɂ��Ȃ�Łw�����c�{�x�Ɩ��t�����B����ȗ��A�w�����c�{�x�͔�O�Ƒ�a���ɂ���B�v�Ƃ���B�ȉ��ɂ��̍����������B
(1) 591�N�`�����Ƃ̉����u��{���v���`�����Ƃ���Ɨ����A�h��n�q�����̐V�����i��O�j�ɒy���Q���Ę`��������������B���̌��ʁA��O�ɓ�̉�����i������킯�ɂ䂩���A��a�̑h��̂Ɂu��a�����c�{�v��A���ÓV�c���u�q�B���p����a�V�c�v�Ƃ��đ�a�ɑ��荞�ƍl������i603�N�j�B
(2) �h��n��a�����̋��Ȃ��Ȃ�����O�ł́A��{�������{�{�Ɂi606�N�j�A��{���Ƃ̍c�ɓV�c����O�����c�{�ɋ���i642�N)�B
���ËI606�N
�u�V�c�i��{���j�A�c���q�i�������q�j�ɐ�����題o���u�����ށA�A�A�c���q�܂��@�،o���i��O�j���{�{�ɉ����ču���A�V�c�����傢�Ɋ�ԁA�d�������c�S�����c���q�Ɏ{���A����Ĕ������ɔ[�߂�v�i�Čf�j
�c�ɋI642�N
�u�i�c�Ɂj�V�c�i��O�j�����c�{�ɑJ���v�@�@�@
(3) ��q����悤�ɁA608�N���ÓV�c���@�g�萴��ےÓ�g�Ƒ�a�Ɍ}���Ă���B���̎��̏����@���́u���r�́i��܂Ɓj�A�A�A����鰎u�̈������̎הn�i�Ȃ���̂Ȃ�v�Ƃ��Ă���B���Â���a�ɋ������Ƃ������d�v�ȏ؋��ł����i�u���r�́���a�v�_�ɂ��Ă͌�q�j�B
(4)�@��a�ɏ����c�{�����������Ƃ������L�q������B
�F���I649�N
�u�i�ےÓ�g�{�ɋ����F���j�V�c�́A�A�A�i槑i�����Œ���Z�ɒǂ��ċ�B���瓦���ė����j�h��q�R�c���C��b���U�߂��B��b�̒��q���u�͐�����`�i��܂Ɓj�ɍ݂��āi�R�c���i�ޗǍ���s�j���������ł��������j�A�A�A���̖�A���u�͋{���Ă����Ƃ�~���A[�{�͏����c�{�ƈ���]�v
��a�ɋ��čF���R�̏P�������h�䋻�u�������Ƃ��ċ߂��́u�����c�{�v���Ă��A�Ƃ������̋{�́u��a�����c�{�v�ł���B���̕�����́A�F�������ÓV�c����p�����u��a�����c�{�v�ɋ������i629�N-645�N�j�A��g�J�s�i645�N�j�̌�649�N���_�ł́A�u��a�����c�{�v��̗L�͂��Ă������A�����ɂ͋��Ȃ������A�Ɖ��߂ł���B�n���łȂ����ł���_�͘_�Ƃ��Ďア���A���̒����u��O�����c�{�v���w���\���͂Ȃ��B�����͑h��q�R�c���C������������̑���̖{���A����642�N�ȗ�����Z�c�q������{���Ƃ̋{������ł���B���̍��A�F���V�c�ƒ���Z�c�q�͊��ɉ������̂ŘA�g���Ă����i���́j�B �@
�ȏォ��h��n��a�����́u�����c�{�v�́u��a�����c�{�v�ł���B�u���J�������v�ɂ��Ă͓��{���I�ł͗B��̋L�^���u603�N�A�����c�{�ɑJ��v�i���ËI�j�ł��邩��A�u603�N�A���ÓV�c�͑�a�����c�{�ɑJ�����v�Ƃ��邵���Ȃ��B
��170�@�`���̉����@俀�i��Áj��
���āA��������͖��܂ł�10���߂��@���ɏo�Ă��錭�@�g�W�ł���B���́u���o���鏈�̓V�q�A���v���鏈�̓V�q�ɏ���v���A��������]�X�v�Ƃ����Γ��O���̓^���ł���B
6���I�A�������ɂ߂��������@�i581�N�`�j�ɂ���ē��ꂳ�ꂽ�B�`���͓쒩�i�v�E�āE���E�j�ɒ��v���Ă������A�쒩���ł��20�N�������Ă���悤�₭�k���n���@�Ɍ��g�����i600�N�j�B���̑O��ɁA�`���́u俀�i��Áj���v�ƍ��������߂��l���B���̋L�����@���ɂ���B
�@����`俀�i��Áj����`��
�u俀�i��Áj���͕S�Z�V���̓���ɍ݂�A�����O�痢�A��C�̒��A�R���Ɉ˂��ċ����A鰎�桂𒆚��ɒʂ��O�\�P���A�F�������i���A�A�A���̍��������܌��s�A��k�O���s�e�C�Ɏ����A�A�A���r�͂��s�� �A����鰎u�̈������̎הn�i�Ȃ���̂Ȃ�B�Âɂ����A�y�Q�S����A�A�A�P���Q�痢�A���m�̓��ɂ���@�A�A�A����̎������g���v���A�V��俀�i��Áj�z���Ƃ����A�A�A鰂��āE���Ɏ���A��X�����Ƒ��ʂ��A�A�A�v
�u俀�i��Áj���́A�̂�俀�i��Áj�z���A鰂���Ɍ��g�������v�ƌ����Ă���B鰂Ɍ��g�����̂́u�`���v�̔ږ�āA���Ɍ��g�����̂́u�`���v�̕��ł��邩��A�u俀�i��Áj���v�Ƃ́u�`���v����̍����ύX���������Ɖ��߂���Ă���B�ߋ��̕ʖ��̍��u�`�z���v�܂Łu俀�i��Áj�z���v�ɕς��Ă��邩��A�u�P�Ȃ鍑���̕ύX�v�Ƃ��l������B7�N��ɍĂсu�`���v�ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��A���̖T�ƂȂ�i��q�j�B
��171 俀�i��Áj�����������v�k�ǁA�a���Œʂ��@
�@��俀�i��Áj�����ɂ͘a��̊����\�������p����Ă���B
�@���@�@�i�����P�j
�u�J�c20�N�i600�N�j�A俀�i��Áj���A���͈����i���܁A���߁H�j�A���͑����v�k�ǁi���肵�ق��A���炵�Ђ��H�j�A����y雞��i�������݁H�j�ƍ����A�g�������킵�āi���v�ƂȂ��Ă��Ȃ��j�A�A�A����雞��i���݁j�ƍ��� �A�A�A���q�𖼂Â��ė��̖푽�����ƂȂ��A�A�A�v
�v����ɂ͘`�̌܉��̐����͘`�]�E�`���̂悤�Ɋ����̈ꎚ���A�ꎚ���������B�������A俀�i��Áj���͘a����p���Ă���B������u�����ς���Ă���B�������ς������炾�B�`�̌܉��̘`���Ƃ͖łт��B�ֈ�`���Ƃ͖łт��v�Ƃ�����߂�����B�������M�҂͉������ς���Ă��Ȃ��A�ƍl����B�u�쒩�ɂ͌h�ӂ�\���Ċ�������p�������A�V�Q�̖k���ɑ��Ă���͛Z�ɂȂ�B�����ɂ͓��X����a���������B�v�Ƃ��Ęa���u�A���m�������^���V�q�R�v�Œʂ����A�Ɖ��߂���̂����R���B�u���o���鍑�̓V�q�v�i��q�j�ƊO���p���ň�v���Ă���B�O�͂łׂ̂��悤�ɁA�`�����Ƃł͕������̊O�ʐ헪�Ŏ嗬�E�T���̌��͂�������������Ȃ����A�`�����Ɓi�A�}�e���X�n�j���̂͌p�����Ă���i�掵�́j�B
��172�@俀�i��Áj�͓����d���ő卑��
�@���͑����āA俀�i��Áj���ɂ��ďڍׂɋL�q���Ă���B�K�`�����@�g�̕��Ɋ�Â����悤���B��������̍��g�͔ږ�Ă̎����鰎g�ȗ��ł���B
�@���@�i����2�j
�u��s�����A����12�������A�A�A�R��i���Ɂj120�L��A�����̖q�ɂ̂��Ƃ��A�A�A�������n�ށA�A�A���L���嫂�����Ȃ��A�A�A�܌��̊y�L���A�A�A���@���h���A�A�A���h�R�����A�A�A�V���E�S�ς͊F俀�i��Áj���Ȃ��đ卑�ƂȂ��A���������A���i�݂ȁj�h���A�A�A�v
�u��s�����v�Ƃ́A���N�ƈ���ď�̓`�����Ȃ������̂����m��Ȃ����u�ֈ�̗��v�i��Z�́j���������ēG���鐨�͂����Ȃ����Ƃ������Ă���B�������x�u����12���v��q�Ɂi�����̒n�����̒����j�Ɏ����n���s�����x�u�R��i���ɁA�u�����v�̂��ƁH�j�v�������悤�� �B�u���L���嫂����햳���v�Ƃ́A�u�`�����̏�\���i�O�o�j�̂悤�Ȑ���̘A���v�Ƒ傢�ɈقȂ�A�����̋��_�����������A������������������i�I������H�j���Ƃ������Ă���B����ŁA�����ɗ͂𒍂��������h���A������卑�ƊŘ�Ă���A�Ƃ���B俀�i��Áj���͓������[�������A���������������邱�Ƃɂ���āA�`�����̋��S�͂������l���B
��173�@���O��
俀�i��Áj���͊O���ł��ϋɍ�ɏo���A���@���ɂ���B
�@���@�i����3�j
�u���3�N�i607�N�j�A���������v��ǁA�g�������킵�����v���B�g�ҞH���A�w�����A�C���̕�F�V�q�d�˂ĕ��@�������ƁA�̂Ɍ��킵�Ē��`���A���i����j���č���ɏ\�l�҂���@���w�ԁx�ƁB���̍����ɞH���A�u���o���鏈�̓V�q�A���v���鏈�̓V�q�ɏ���v���A���������]�X�x��������x���A�A�A�w�؈̏��A����L��́A���i�܂��j�Ȃ��ĕ��i�Ԃ�j����Ȃ���x�ƁB
���N�i���4�N�@608�N�j�A���јY�i�Ԃ���낤�A��E�@�����W�H�j�萴���g���Ƃ���俀�i��Áj���Ɍ��킷�v
�����ŁA�u���v�v�ƋL����Ă���B�V�q�����̂��鑽���v�k�ǂ����v����͂��͂Ȃ��u�����������v�ʂ��Ó������A��q����悤�Ɍ���@�͑����v�k�ǂɁu����͒��v�ł����v�ƌ������̂ŁA�@�͂������u���v�v�ƋL���Ă���B�u�d�˂ĕ��@�������v�Ƃ���̂́u�쒩����������̂ɁA�d�˂Ėk�������������v�̈Ӗ��ŁA�쒩�����̎��҂����F���鑽���v�k�ǂ��V���������u�g�����������Ă��錾�t�v�A�ƕM�҂͉��߂���B�������A����Ƃ͗����ɂ��̌��@�g�ɑ����̊w�ҁE�m�����s���ĐV���̖k���������w�ڂ��Ƃ���ʂ̐��́i�h�䎁�␄�Ò��j���������Ă����ƍl����B
���āA���ڂ́u���o���鏈�̓V�q�]�X�v�Ŏn�܂�u�Γ��O�������v�𑗂������Ƃɑ��āA���邪�{�����A�Ƃ���B��������x���{�������̂́A�����ɒ����c��俀�i��Áj���ɔh�������B�ꍇ�ɂ���Ă͐푈�ɂȂ邩������Ȃ��̂ŁA�G���@�𖽂����Ƃ������߂�����B
��174�@���얅�q�̌��@�g�@���ËI�@
�����@��俀�i��Áj���`�̋L���ɑΉ�����L�������N�̐��ËI�ɂ���B
���ËI15�N�i607�N�j�u��珬��b���q��哂 [7]�Ɍ��킷�v
���ËI16�N�i608�N�j�u�l���A���얅�q�A�哂���A���A�A�A�哂�g�l�萢���A�A�A�}���Ɏ���A���q�ׂ̈ɁA�X�Ɂi�ےÁj��g����قɐV�ق��A�A�A�Z���A�A�A�q���i�ےÁj��g�Âɔ��܂�A�����A���D�O�\�z���Ȃ��ċq�����}���V�قɈ��u���A�A�A�����A�A�A���q�����A�A�A���Ɏg���萢���A�݂����珑�����������x�Ĕq���āA�g���̎|�����サ�ė��A���̏��ɞH���A�w�c��A�`�c�ɖ₤�A�g�l�A�������h�������i���얅�q�j�����āA�A�A�c�i�`�c�̂��Ɓj�A�A�A�������v������������m���A�A�A���Ái��݁j���邠��A�A�A�̂ɍ��e���̏��q�萢�������킵���A�A�A�x�A�A�A�Ɓv
����ł́u�@���Ɛ��ËI�͌����Ɉ�v���A���ꎖ�����L�q�������̂ɊԈႢ�Ȃ��B�@�̎g���w�萴�x�i�@���j�Ɓw�萢���x�i���ËI�j���Q���܂ň�v���A���S�ɑΉ����Ă���B�w�`�c�x�Ƃ͓��R���ÓV�c�̂��ƁA�����v�k�ǂ͒j��������A�ې��̐������q�̂��Ƃ��낤�B�@��607�N�̑����v�k�ǂ́w���v���x�Ƃ����L���Ɛ��ËI���@�鍑���ɂ���w���v�x����v����B���v�����F���ꂽ�̂�����A�w�`�̑�\�x�ƔF�߂��Ă���B������w俀�i��Áj�x�́w�`�x�̌��ő�a����̂��ƁB�Γ��O���͌��ʓI�ɐ��������v�Ƃ���B
���������̒���ɂ����鐄�ƒj�������v�k�ǂ��Ή����Ȃ��Ȃǖ����������B�X�ɑO�͂܂łɏq�ׂ��l�ɁA�`���Ɛ��ÓV�c�̑�a�����͉������قȂ�A�{������B�Ƒ�a�ňقȂ�B�����̍��o�l���قȂ�͂����B���ꎖ�тł͂Ȃ��B�u�ʂ̔N�̕ʂ̎��сv�Ƃ�����߂�����
[8]�B
�M�҂��u�ʂ̎��сv�Ƃ��邪�A�u����N�̎��сv�A�Ɖ��߂���B�Ȃ�����N�ɈقȂ鉤������������ɍ����𑗂��Ă���̂��B�@���̋L�q�Ɠ��{���I�̋L�q�́u���ꎖ�сv�Ɓu����łȂ����сv�̓�ʐ��������Ă��āA�㐢�̎j�Ƃ�f�킵�Ă����B��������߈ȉ��ʼn�͂���B
[7] �@�u�哂�v�@�����ŁA�u�@�v���u�哂�v�ƂȂ��Ă���̂́u���̎n�c���c���@�邩��T�������v�Ƃ��錚�O���瓂�́u�@�͓��̑O�j�v�̗���d��������ł��낤�i�I�̕Ҏ[�͓�����j�B
[8] �u�ʂ̎��сv�@�����v�k�ǂ̌��@�g�Ɛ��Â̌��@�g�͕ʂ̎��сA�Ƃ�����߁B���̂ЂƂɌÓc���F�́u12�N������v������B�u���{���I�̂��̋L�q�ɂ�12�N�̍��낪����A607�N���얅�q�̌��@�g�͎���618�N���@�����ɑ��������619�N�����g���B���ꂪ���ËI�́w�哂�x�̕\���ƂȂ��Ă���B�v�Ƃ���B�Ó��Ǝv����_�_���������A12�N����āu���̌���a�g�v���Ƃ���ƌ��g�̗��R�⒆���j���Ɍ���Ȃ����R���s���ȂǁA����������B��q����悤�ɁA�������ɘ`���͍Ăѓ��ƑΗ������v���~�߂Ă�������u��a���v�v���������璆���j���ɍڂ�Ȃ����R�������B�Ƃ��낪�A���̎��������j�ɂ͘`�������o�Ă��Ȃ��B�u�Ñ�͋P���Ă����v�Óc���F�@�����V���Ё@1985�N�@
��175�@���얅�q��俀�i��Áj�����@�g�̐��s�g
�@���Ɛ��ËI�𐮍���������M�҂̉��߂ɂ��āA���_�����Ɏ����B�u607�N�A俀�i��Áj���͌��@�g�𑗂����B���̍����́w���o���鍑�̓V�q�A�A�A�x�Ŏn�܂�w�Γ��O���x�������B���̌��@�g�ɁA��a���ÓV�c�͏��얅�q�𐏍s�������B�Ő�[�̕����E������ړI�Ř`�����̓��ӂ̉��ɁA���ÓV�c�̐M���ƌ���i���g���ď��얅�q�͎Q�������v�ƍl����B�����܂ł͘`���̌��@�g�Ƃ��Ắu���ꎖ�сv���B
�u���s�v�Əq�ׂ����A���̗��R�̈�͓����O�����������Ă����̂͘`���ł����āA�O����ł͑�a�����͏]�����ɉ߂��Ȃ��B��a����̌������g�͏��߂Ăł���i�V�����j�A�����܂��Ǝ��̌����O�����[�g�������Ă��Ȃ������B�L�͂Ș`�����͐��ÂɌ��炸���s�g�𑗂荞��ł����̂ł͂Ȃ����낤���B��p���S�ƈ��������ɕ����E��������߂āB���ɁA�S�ς���������k�������ɓ]�������̂�m���āA������w�ڂ��Ƃ��鐨�͍͂����ɑ��������悤���i��f�Ɂu�Ŗ@���w�Ԑ��\�l�����s�v�Ƃ���j�B��{���Ƃ̐������q�E��a�����̐��ÓV�c�E�h�䎁�Ȃǂ��i�O�́j�B����琨�͂�俀�i��Áj�̌��@�g�ɐ��s�g�𑗂�傫�ȓ��@�ƂȂ����A�ƍl����i俀�i��Áj���͓쒩�����ɌŎ��j�B
�Ƃ��낪�A��g�ł���俀�i��Áj���g�������{�点�����ʁA�����俀�i��Áj���ɒf����˂��������A���s�����a�g�ɘ`����\���̗U�����������B����́u�����ߍU��v���B�u�@��俀�i��Áj�v�Ɓu�@�Ƒ�a�v�́u�ʂ̎��сv�ɕω������B�@�������u俀�i��Áj����ɂ����A���s�̏��얅�q��`�����v�g�ƔF�߂�v�Ƌ}�ς������A���邢�͐��s�g���얅�q���}篓Ǝ��`����\�i俀�i��Áj���������j�Ƃ��Ē��v��\�����ꂽ���A�ǂ���̉\��������B
��176�@�@�g�萴�̖K�`�@�u�C�݂ɒB���v�͓��C�@�@�@�@�i2013.2�@�`�����C���j
��������x���{�������̂́A�����ɒ����c��俀�i��Áj���ɔh�������B
�@���@�i����4�j
�u���N�i���4�N�@608�N�j�A���јY�i�Ԃ���낤�A��E�@�����W�H�j�萴���g���Ƃ���俀�i��Áj���Ɍ��킷�A�A�A�s�z���i���܁j�����o�đ�C���ɍ݂��A�A�A�|�z�i�������j���Ɏ���A�����`�����Ɏ����A�A�A���\�P���o�āA�C�݂ɒB���B�|�z����蓌�A�F俀�i��Áj�ɕ��f���B俀�i��Áj���A�A�A�Ҍ}���A�A���ɔނ̓s�ɓ����A�A�A�v
�@�g��俀�i��Áj����[����[�܂Œ��������A�Ƃ���B
�����Łu�C�݂ɒB���v�ɂ��āA�]�������X�_��������B����́u�`������a�v���ł́u�@�g�萴����g�ɗ��Ă���i���ËI�A�O�f�j�B������w�|�z���ɓ����A�A�A�\�P�����o�ĊC�݂ɒB���x�Ƃ́A���˓��C���o�ĊC����C�݂ɒB���邱�ƂŁw�ےÓ�g�x�̂��Ƃ��B���̌�̕��͂ɓ�g�ł̊��}��俀�i��Áj���̉��ڋL������������A�@�g�萴�͓�g����㗤���đ�a�ɓ���俀�i��Áj���i���ÓV�c�j�Ɩʐڂ����A�Ɖ��߂ł���B�]���āA�w�`������a�x�ł���A�w�|�z��蓌�́A�F��a�ɕ��f���B�x�����藧�v�Ƃ��Ă���B俀�i��Áj�͘`�̌뎚�Ɖ��߂��Ă���B
����u��B�������v�ł́A�u�w�C�݂ɒB���x�́w���H�ŏ\�P�����o�ċ�B���[�̊C�݁i�L�O�j�ɒB���x�̈Ӗ����B�w�\�P���x�͂��ׂċ�B���ŁA�w�F俀�i��Áj�ɕ��f���x�͋�B����俀�i��Áj���ł��邱�Ƃ������Ă���B���ËI���@�g�萴��������g�Ƃ͒}����g�Â��B�@�g�萢���͑�a�ɍs���Ă��Ȃ��B���ËI�͝s�����B�v�Ƃ���B
�������M�҂́A���́u�C�݂ɒB���v�͋�B���[�ł͂Ȃ��A�܂���a��g�ł��Ȃ��A�X�ɓ��̈ɐ��p�����肠�邢�͓��C���낤�A�ƍl����B���̍����������B
(1)
�܂��A��B�������̖L�O�C�݂ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�}������L�O�͖�50km�A��������2�`3���̓��̂肾�B�c��ɖ������A��������2000km�߂���v�����u�G��@�̑咲�����s�v���A�����l����݂�u�ב��v�������Ȃ��L�O�C�݂Ɏ����Ă��̊C�̌������i���j�������Ɂu���͑S���������v�ƕ��邱�Ƃ͍l�����Ȃ��B�����͋�B�̓��ɑ�a�����邱�Ƃ͒m���Ă���i�Y���I�j�B
(2)
����̑_����俀�i��Áj������������ׂ́u�����ߍU��v�ł���B���̂��Ƃ͏o���O����p�ӂ�����a���ÓV�c�ւ̍������ƂȂ�B�萴�͑�a��俀�i��Áj���ɑR�ł��鍑�Ƃ��ĖK��u鰎��A�A�A���r�́i��܂Ɓj���s�� �A����鰎u�̈������̎הn�i�Ȃ���̂Ȃ�B�v�i�@���`�����A�O�f�j�Ɨ��������A�ƍl������B��a���`���̋��͂ȓ������ł��邱�Ƃ͑v���ȗ��̒����̗������B���얅�q�͒����ł��̗l�ɋ����������낤�B�@�g�͂��̔F�����m���߂钲���g�ł���B
(3)
�������u�C�݂ɒB���v�́u�i�ےÁj��g�v�ł��Ȃ��B�u�C�݂ɒB���v���u��g�v�̂��Ƃł́A��g�́u�����v�����������A��a�́u�����v�����Ȃ��Łu���A�F俀�i��Áj�ɕ��f���v�Ɣ��f�������ƂɂȂ�A����܂��Ӗ��̂������Ƃ�Ȃ��B�@��俀�i��Áj���`�`���Ɂu俀�i��Áj�����A�A�A���̍����͓����܌��s�A��k�O���s�A�e�X�C�Ɏ����v�Ƃ���B������俀�i��Áj����[����[�܂ŁA���Ȃ킿�u�C��n���|�z����`�����i�L�O[9]�j��i��a���܂߂āj�\�P�����o�����Α��̊C�܂��A���[���瓌�[�܂őS�����n�Ɍ����v�Ƃ��������͈͕u�C�݂ɒB���v���Ӗ������B���ꂪ�����ď��߂āu�|�z���i���[�j��蓌�A�F�i���[�܂Łj俀�i��Áj���ɕ��f���v�Ƃ������_������ꂽ�̂��B
(4) ���̑S�̔c���̔���̌�ɁA��̓I�s���u俀�i��Áj���Ɖ�����v�Əq�ׂĂ���B���ۂ̍s���̏����ł͂Ȃ��A�̍������Ɏ��������̗͂l���B�Ȃ��Ȃ�A���{���I�ɂ��A�萴���}���ɒ������̂�608�N4���A�i�ےÁj��g�Âɒ������̂�6���A����2�����Ԓ}����俀�i��Áj���Ɖ���Ă����Ɛ��肳���B�i�ےÁj��g�ɒ����Ă���2�������8�������i��a�����c�j�A���̊ԂɍX�ɓ��[�C�݂܂Œ������Ă����Ɛ��肳���B9���A������q�𐄌ÓV�c�́i�ےÁj��g�ŋ������Ă���i���ËI�A��q�j�B
�@�ȏ㌋�_�Ƃ��āA�u�萴�͒}����俀�i��Áj���ɉ�A���C�̊C�݂ɍs�������a�ɓ��萄�ÓV�c�ɉ���Ă���v�B
[9] �`�����@�`�̖�������̂���n���l�i���ۂ͊��l�n�V���l�������j�̋��Z�n�B�n���E�`���̖L�x�ȖL�O�i���t�x�t�߁j����肳��Ă���B�`����l�Ƌ��ɏ��얅�q�炪�萴�����l���x�̍����L�O�n��Ɉē����āA��a�������ÓV�c�ƖL�O�`���i���l�n�ƐM�����Ă����j�ٖ̋��ȊW�����������\���͂��邾�낤�B�L�O�͔�O��a�����V�c�B�̌̒n�ł���A�������x����̒n���c�����Ă������Ƃ��l������B���f��10�]���̒��ɐ`���������L����Ă���̂́A���������ē����t���������炾�낤�B�L�O�`���E���B�Z�p�E�V�������E�h��n�q�E��O��a�������ÁE��{���ƁE�������q�E�`�͏��Ȃǂ̘A�z�������ԁB
��177�@��g�Â�C�Ξ֎s�i�����j�͘`���ڑҎ{�݁@�@�@�@�@�i2011.7�@�lj��j
��B�������́u�萴����a�ɍs�����A�Ƃ����̂͐��ËI�̝s�����B�Ȃ��Ȃ珑����Ă���̂͘`���̒}���ڑҎ{�݂����炾�B�萴�͑�a�ɂ͍s���Ă��Ȃ��v�Ƃ���B
�������A������@�g�萴�́A�A������`�����@�g�Ƒ�a�̐��s�g���얅�q�Ƌ��ɒ}���ɒ������B��g�Ái�}���j��C�Ξ֎s�i�����j�ȂNj�B�̘`���ڑҎ{�݂ŋq�l�����}���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�o�}�����̂͘`����l�i��g���j�Ƒ�a��l�i���s�g���j���ꏏ���萴�����}���Ă���B���ËI�ɋ�B�`���̐ڑҐݔ��E�s�����łĂ��闝�R�͂���B
�����A��a�͒}���̊O���{�݂Ɠ����̓��l�{�݁i��g�ÁE��g����فj��ےÓ�g�ɍ��A���l�̊��}�s���i����D�A����n�j���ēx��a�ŌJ��Ԃ����B�u�C�Ξ֎s�v�����^�����\��������B������萴�ׁ̈A�Ƃ������͓��������B���̒n����s�����ߋE�Ɏ�������ł����\�����������炾�B������㐢�ǎ҂̍����ƌ�����������悤���B
��178 �u�O�̓�g�v�@�}���E�ےÁE�L���@�@�@�i2014.8�@�L����g��lj��j
�u��g�v�͓������ĕp�o���A�������������������Ă���B�������������B���͎O�����ڂ�����A������܂߂Đ�������B
�u�}����g�v�͒��N��������̊O���g�߂̓����`�ł���i�����s����̑��X�ǐ�͌��t�߂��j�A�}���̐l���Ƌ��ɓ��{���I�ɓo�ꂷ��B
�Ԗ��I540�N�u��g�j�Ë{�ɍK���A�A�A������A���`�i�{���͒}�O�Ǝ�S�A����쒆���j���]���v
�Ԗ�552�N�u��ڏh�H�Ɏ��݂Ɂi�������j��q�������A�A�A��b��낱��ŏ����c�i��O�O���S�A�����s�߂��j�̉ƂɈ��u���A�A�A�����i��O�{���S�A�����s���̌�����߂����j�̉Ƃ���߂Ď��ƈׂ��A�A�A��ɍ��ɉu�C���͂���A�A�A�V�c�i�`�����A�O�͎Q�Ɓj�H���A�A�A�������g�i�}�O�j�̖x�]�ɗ������Ă�v
�q�B�I585�N�u�����牮�i�}�O�Ǝ�S�j���������Ă���g�i�}�O�j�̖x�]�Ɋ��Ă��v
����A�u�ےÓ�g�v�́u�_�������v�u�_���`�m�������v�u�F���J�s�i��g�{�j�v�ɕp�o����B�_���I�ł́u�w�Q���x���a���č��i���{���I�Ҏ[���j�w��g�x�Ƃ����v�Ƃ��Ă���B�u��g�v���_�����㐢�̖��̂Ǝ�������Ă���B�_���c�@������ɒ}����g�̒n����ےÂֈڐA�����Ǝv����B
�O�ڂ́u�L����g�v�ɂ��Ă͑�Z�́u��g�ԑq�͖L���v�Ō������B�u�L���ɎO�ڂ̓�g���������\���������v�Ƃ����̂����̌��_���B���̗v�|���u���_�V�c�̍��A���{�M���͖k��O����L������ɑJ��{�Ƃ����i���_�I�j�B�܂��A��a�Ƃ̘A�g�ɍD�s���̖L���C�݂ɒÂ�݂��A�}����g��n���ڐA���āu�L����g�v�Ƃ����B���̌�ےÓ�g�ɑJ�������{�M���i���{�j�͐m�����`�p�̒��̊ԁA�L����g���Ƃ̎�v���p�n�Ƃ��Ċ��p�����\��������B���̊Ԃ̂����ꂩ�̎��_�ŁA�L���͓��{�M���̗�������ޒ}���N�ֈ�̏��̂ƂȂ����i�L�O�E�L��̓_�ݏ��́j�B���̔ֈ�̏��̂�D�������Ձ^�����e���͖L�O�������ɑJ�s�����B���_�ܐ��p�̂̎q�ł�����ՓV�c�́u�L����g�v��c���_�V�c�䂩��̒n�Ƃ��đ�ɂ����i���ՋI�j�B�v
���{���I�͎O�̓�g������Ȃ������L���邩��A�ٕʂ�����B���{���I�Ҏ[���ɂ��łɖL����g�̋L���E�����ꂽ�\���A�Ӑ}�I�ɋE���ւ̈ڐA�n���������L�q������ȂNj��U�L�ڂƂ͌����Ȃ����A��a�ꌳ����ɉ������ҏW����������B���_�I�`�q�B�I�́u�O�̓�g�̕����v��F�߂ď��߂Ė����̂Ȃ����߂��\�ƂȂ�B
��179�@俀�i��Áj���̑Γ��O���̕���
�{����@���ɖ߂�B�O�q���@���ɑ����L�q�ɂ́A�u�@�g�萴��俀�i��Áj���ɍs���A俀�i��Áj�����͑Γ��O������������������A���v��F�߂��v�Ƃ���B�������ʂɕM�҉��߂�t�L���邪�A�t�L�����킹�ǂނ��ƂŐ����������������ƍl����B
�@���@�i����5�@俀�i��Áj���`�����j
�u���̉��i俀�i��Áj�������v�k�ǁj�͐��i�萴�j�Ƒ��������A�傢�ɉx��ł��킭�A�w���������C���ɑ��@��`�̍�����ƁA�̂Ɍ��킵�����v���i�O��̌��@�g�A����͒��v�ł����A俀�i��Áj�����̓V�q���̂͂Ȃ��������Ƃɂ��Ă��������j�x�@�ƁB�������ĞH���A�w�c��̓��͓�V�i�V�n�j�ɕ����A�A�A���̉��i�������j��炤���Ȃ��āA�̂ɍs�l�����킵�����������ɐ�@���i���v����Ȃ狖���A���̊m�F�ɗ����j�x���A�A�A���̌�A�i�ѕ��S�ɗ��܂�����ɑ����čc��̋����j���́i�ѕ��S����俀�i��Áj�Ɂj�l�����킵�Ă��̉��Ɉ����ĞH���A�w�����͊��ɒB���i�V�q�̎��̂���߂����Ƃ̊m�F�ƕ͏I������j�x�@���A�A�A���i�܁j���i俀�i��Áj�́j�g�҂����āi�����ɋA��j���ɏ]�������i�j�𗈍v�����ށi俀�i��Áj�̎g�҂��萴�ɏ]���Ē����ɍs�����v�����j�B���̌�A��������@�i俀�i��Áj���͍ēx�������Ę`���ɖ߂����A俀�i��Áj���Ƃ��Ă̎g�͓�x�Ɨ��Ȃ������j�v
�����v�k�ǂ͓V�q�����̂������A�����̔�����������1�N�ł����P���B�u�����v�k�ǂ̑Γ��O���̎��݂́A����ɂ���Ēׂ��ꂽ�v�Ɖ��߂ł���B����́u俀�i��Áj���͂������������ׂ����v�Ə����ւ��āA�킴�킴�@���Ɂu俀�i��Áj���`�v�𗧂āA俀�i��Áj���́u����͒��v�ł����v�̌��������607�N�L�����u���v�v�Ƃ����i�O�q�����@���Â��Q�̋^��ւ̓����j�B���̏�Łu��������v�Ƃ��āu俀�i��Áj���v���ׂꂽ�������L�^�Ɏc�����i���ۂ��@���ҏW�͌㐢�����A���̂悤�ȓ����̎j���Ɋ�Â������̂Ǝv����j�B�����āA���������ɖ߂����u�`���v���A2�N��ɒ��v�������Ƃ����̗l�Ɋm�F���Ă���B
�@����I�����i俀�i��Áj���`�̒��łȂ����Ƃɒ��ځj
�u���6�N�i610�N�j�A�`���i俀�i��Áj���ł͂Ȃ����Ƃɒ��ځj�A�g�������킵�ĕ������v���i���v�ĊJ�̊m�F�j�v
��180�@�@�̓�ҊO��
�O�߂��@���ɂ���608�N���萴�͒|�z�ɓ���A俀�i��Áj���̑����v�k�ǂƉ���āu�V�q���́E俀�i��Áj�������̓P��A���v�̎��s�v�������o�����B����ɓ��{���I608�N�����킹�ǂ߂A�萴�͂��̌�ɑ�a��K�ˁA�o���O�ɗp�ӂ������邩�琄�ÓV�c���̍����u�`���̑�\�Ƃ��Ē��v��F�߂�v��`�B�����B���ʓI�ɘ`����\�𑽗��v�k�ǂƐ��ÓV�c�̓�҂ɔF�߂����ƂɂȂ�B�@�g���@���o��O����z�肵�������Ɣ�����̓�ҊO���ƍl������B�@���Ɠ��{���I�ł͎g�҂̐g�����قȂ�B�@���́u���јY�i�Ԃ���낤�j�萴�v�Ƃ���A���{���I�ł́u���e���i�����낶�j�̏��q�i���傤�����j�萢���v�Ƃ���B�@�������Ɣ�����Ŏg�҂̌�������ς��A�����ł̓�҂�������Ƃ��l������B
�萴�͗̐��[�̊C���瓌�[�̊C�݂܂Ŏ��n�������A�|�z����蓌�͊F�i��a���܂߁j俀�i��Áj�ɕ��f���Ă�����Ԃ�c�������B���̌��_�Ƃ��āu����A俀�i��Áj���̑����v�k�ǂ̑���ɐ��ÓV�c��`���̑�\�ɔF�߂�����̍�����n�������A���Ԃ�����Ƒ�a��俀�i��Áj���ɕ��f���Ă���B�����v�k�ǂ����v�����ꂽ�̂ł��邩�瑽���v�k�ǂ��\�ɖ߂��ׂ��A��������ɕ��悤�v�Ƃ����̂ł��낤�B���ꂪ�@���ɂ���悤�Ɂu���̌�A���͐l�����킵���̉��i�����v�k�ǁj�Ɉ����ĞH���A�w�����͊��ɒB���A�A�A�x�v�ƂȂ����ƍl������B
���̊O�𑛂���俀�i��Áj���̏����Ŏ��܂�A�Ȍ�̐��������g�͍Ăј`������ƂȂ�A�����j�́A�`�������g�݂̂��L�^���Ă���B����A���{���I����a�̌����g�݂̂��L�^���Ă���i�@��618�N�ɓ��ɑ������j�B
��181�@���ÓV�c�́u�`�����F��v���ق��ɂ��ꂽ
���ڂ��ׂ��́A�O�߂̐��ËI�ɁA�u���̏��i�����j�ɞH���w�c��A�`�c�ɖ₤�A�A�A�c�A�A�A�������v������������m���A�A�A���Ái��݁j���邠��x�v�Ƃ���_�ł���B���́u�`�c�v�̋L�q����A���얅�q�����Q�����ł��낤���ÓV�c�̏��́i俀�i��Áj�ł͂Ȃ��j�u�`���v�̗�������A�u�V�c�v�Ǝ��̂����Ǝv����i�������u�V�q�v���̂ł͂Ȃ��j�B�܂��A����i�͒��v�i�ł͂Ȃ��B���̎��_�ł͐��Âɒ��v�̌����͂Ȃ����炾�B����ɑ�������́A�u�`�c�̒��v���Â���v�Ƃ��Đ��ÓV�c���u�`���̒��v�̎�A�`����\�ҁv�Ǝ����グ�Ă���B���ÓV�c�́u�`�����v�ƔF�肳�ꂽ�̂��B
�萴���A������ɓ����菬�얅�q���ēx���萄�ÓV�c�͏���������B
���ËI�i608�N�j�u�V�c������فi���Ɓj�ӁB���̎��ɞH���A���̓V�c�A���̍c��Ɍh�����A�A�A�v
�@�ēx�u�V�c�v�����̂��Ă���B�`�̎n�c�邪����܂ł́u�O�c�i�V�c�E�n�c�E�l�c�j�v�̏�Ɂu�c��v��V�݂�������u�V�c�v�́u�c��v�̉��ł���i�j�L�`�n�c�{�I�j�B���̓_�͑O��̂悤�ȁu�V�q�v���̖����N�����Ȃ������悤���B�������A�@���ɂ��萴����a�ɍs�������Ƃ��A���È������̂��Ƃ��L����Ă��Ȃ��B����͌��������ꂽ���A�j���ɍڂ邱�Ƃ͖��������B���ÓV�c�ւ́u�`�����F��v�͂ق��ɂ��ꂽ�̂��B����́A�����v�k�ǂ��������āu俀�i��Áj�����ߘ`���v�Ƃ��āu���v�v���ĊJ�������Ƃɂ��A�Ăсu�`����\�ҁv�ƔF�߂�ꂽ����ł���B��������@���ɋL�ڂ�������j���Ƃ��ꂽ�B����̓�ҊO���̊����ł���B
�@��Ɛ��ÓV�c�̂����͂ǂ���ɂƂ��Ă��u���O���v���B�@�͓�҂̈���������������琄�Ò�Ƃ̂����͖������Ă��Ȃ��B�`���Ƃ̌����O���������L���Ă���B���Ò�ɂƂ��Č��ʂ͎��s���������A�`���ŖS��̓��{���I�͉B���K�v�������B�@��Ɛ��ÓV�c�̗F�D�O���ƕ\������Ă���B�����ǂ���Ɠǎ҂͌�ǁi�����v�k�ǂƐ��Â̍����j�ɗU������Ղ����A�Ȃ��B����Ă��Ȃ�����悭�ǂނƑS�Ă��킩��B
��182 �u�הn�䍑�����r�́i��܂ƁH�j����a�v���@�@�@�i2014.11 ���M�j
�{�̗͂v�|
�@���łѓ��ɑ���ƁA�`���͍Ăё�`�����̂����̉��͍ĂѓV�q�����̂����B�`���������g�������Ă����v�͂��Ȃ������B��{���ƂƑ�a�����͂��ꂼ��e������O����͍������B
�h������͏�{���̒����R�ґ�Z���ꑰ��������ŖŖS�������̂ɑ��A��{���Ƃ̒���Z�c�q��́u�����̕ρv�őh��@�Ƃ�łڂ����B�������h��x���Ƃ̑Ë����炩�A�c�ɓV�c�́u����Z�c�q���c���q�ɂ��邱�Ƃ������ɍF���V�c�ɏ��ʂ���v�ƒ�Ă����B���]�Ȑ܂����������A�F����������ƐĖ��i�c�Ɂj���p���i�d�N�j���āu��a�����^��{���Ƃ̍��́v�����������B���̌�̓������炱��́u��a�����𑶑������Ƃ��闼�����̑Γ����́v�Ɖ��߂ł��A���̐����p������������Z�c�q�����ʂł���Ԑ����������B
�����ł͕S�ς����E�V���ɖłڂ���A�S�ς̈�b�炪�`���ɋ~���v�������Ă����B�S�ς̕ی�҂����F���Ă����`���́A�@�卑�Ƃ��Ę`�����Ɂu�S�ϋ~�ρv�̔h�������߂����B�`���Ƃ̍��̂��\�z����Ė��V�c�͌��ǁu�S�ϋ~�ρv�ɉ�������B
�����]�̐킢�Ř`���E�`�����A���R�͔s�ꂽ�B���̏ƋL�^�͍������ď�������A�Ȃ������̗]�n�������B
��183 �`�����̓V�q���̍ĊJ�ƊO���@�@�@�@�@�i2011.8�@���j
�O�͂ŋ�B�ɎO�������������A���̈��a�����i��B�j����a�ɋA�ґJ�s�������Ƃ��������B�����ł́A�O�����̂��̌��H�邱�Ƃɂ���B
俀�i��Áj���̑����v�k�ǂ��@��̈��͂ɋ����ēV�q���̂�ԏサ�A�������`���ɖ߂����i�O�́j�B�������A�@���łсi618�N�j���̎���ɂȂ�Ƒ����v�k�ǂ́u�V�q���́v���ĊJ���A�������u��`���v�����̂����B�����622�N�v����܂Ōp�������l���B�X�ɂ��̌p���҂��u�V�q�v�����̂����ƍl������B���̂��Ƃ́u631�N�ɁA�`���̉��q�����g�̍��\�m�ƐȎ��𑈂��Ă���v���Ƃ��琄���ł���B
�������`���`631�N�@�u�i�`���j���g���ĕ����������i�u�v���v�u���v�v�ƂȂ��Ă��Ȃ��j�A�A�A�i���́j���\�m�����킵�A�A�A���q�Ɨ�𑈂��A�A�A�v
�`�����@�ɂ͒��v�𐾂������A���ɂȂ�ƒ��v�����A���g���}�����`�̉��q�͐Ȏ����߂����đ����Ă���B�`�����́u�V�q���́v�͌�p�҂��܂߁A600�N�`670�N�i�����]�̐킢�j�܂ł̖�70�N�ԑ������\��������B���݂���ɕ{�i�}���j�Ɂu���ɓa�v�u�����v�u�����a�v�u�k���v�ȂǁA�u�V�q�ɊW����n���v���⑶����Ă���B���̒n�����蒅�����w�i�ɂ́A���̂悤�Ș`����70�N�Ƃ��������Ԃ́u�V�q�̑��݁v���������Ǝv����B�l�Êw��������u��ɕ{�͂���70�N�Ԍ��ݒn�ɍ݂����̂ł͂Ȃ��A�����]�̐�O��ɘ`���̖{���n�i�}�O�Ǝ�S�A����쒆�����j���猻�ݒn�Ɉڂ��ꂽ�v�Ƃ����\��������悤�����A���̏ꍇ�����̂��p���ł���A�ƍl������B
��184 ��{���Ƃ��p���������V�c�@�@�@�@�@�@�@�i�@2012�D12�@�ȉ�4�ߍX�V�@2012.4
�X�V�j
�@��{���Ƃ͏�{�����݈�32�N�̌���䂵�����A���q�i��{�������q�j�͊����I�����Ď��̓V�c���������B���̓V�c���o�ꂷ�鋰�炭�����B��̕���������B���̓V�c���瘮���V�c�ւ̌p���w���̂������������Ă���[1]�B
������������N�L���ޒ�
�u����{�F�V�c�i�����V�c�j�̖����Ɉʂɓo�炴�鎞�����ēc���c�q�Ƃ����A�A�A�c�q�A���ɖO�g�ɎQ�育�a���₤�A�����ɉ����ď�{�c�q���A�c���c�q�Ɉ����ĞH���A�����������ȁA�P�������A��Òj�A���痈�����䂪�a��₤���A�A�A�V�c�A�Օ��̓��ɓc���c�q�������Ĉ��ق��A���a�Ă��A�����Ɉʂɓo��A��ʂ�������{�c�q�ƒ���㯋Î�������A������V�c�ʂɑ����A�A�A�S�ϐ�̑����A�A�A��d�������A�����ĕS�ϑ厛�Ƃ����v
�@���̑O���ɂ́u��{�c�q�i�������q�j���c���c�q�i�̂��̘����V�c�j��Òj�ƌĂv�Ƃ���B�c���c�q��v�Ƃ���͕̂�c���i�̂��̍c�ɓV�c�j�ł���B�㔼�ɓo�ꂷ��V�c�u���v�͏�{�c�q�Ǝ������L����V�c�A��������u��{�c�q���I���i622�N�j�A��{���̕���i623�N�j�̌���p������{���ƓV�c�v�ł���B���ÓV�c�ł͂Ȃ��B���̓V�c���Օ��ɍۂ��c���c�q������V�c�Ɏw�������A�Ƃ���B��̘����V�c�ł���B
[1] ��{�����ځ@�@�u�������Ƒh�䎁�Ə�{���Ɓv�ώ��@���_�Ё@2004�N
��185�@�����V�c�̖{���͔�O
�����V�c�͑��ʂ��ĕS�ϐ�̑����{���Ƃ����Ƃ����B
�����I639�N
�u��{�y�ё厛�����삷�������A�����S�ϐ�̑����Ȃċ{���ƂȂ��v
�{���͒n���Ƃ��Ďc���Ă���B
�a����
�u��O���_��S�@���c�A�O���A�_��A�{���v
��O�����y�L
�u�_��S�@�{�����@�S�̐���ɂ���v
�_��S�̐���ɗ�����͒}���x���̏錴��Ƃ����i�����ꌧ���y���j�B�S�ϐ�Ƃ͌��錴�i���傤��j��Ǝv����B
�c�ɋI���N642�N
�u���ܘA�䗅�v�i�����݂̂ނ炶�Ђ�Ӂj�A�}�������˔n�i�w�n�A�͂�܁j�ɏ�藈���������A�S�ύ��͓V�c�i�����j������ƕ����A���g����A�b�A���g�ɏ]���ċ��ɒ}���ɓ���A����ɐb�A���Ɏd���ނƖ]�݁A�̂ɓƂ��ɗ����v
�����V�c�̑��V�̏ꏊ�Ɂu�}�����瑁�n�ŗ����v�Ƃ���B���V�͖{���ōs��ꂽ�ł��낤����A��������B���Ƃ������Ƃ́u�����̖{���͋�B���v�ł���B
�@��{���Ƃ���a�����ƍ��̂�������́u���ƑΗ�����`�����狗����u�������v�������ƍl������B���̓���K�₵���w�҈ɋg�A�����i�����̂ނ炶�͂��Ƃ��j�̕��ٔ��������E�`�̊W��`���Ă���B
�Ė��I���������ɋg�A������
659�N���u�i�����g�j��g�A�A�A��蔭���A�A�A�i���j�V�q�����Ė�u���w���{���̓V�c�A�����Ȃ��i�V�q������u�V���{���V�c�����ȕs�j�x���A�A�A���|���A���Ɨ��N�K���C���̐��������i�푈�ƂȂ邾�낤�j�A����`�̋q���ɋA�邱�Ɠ�����i�}���j�A���A�A�A�v
661�N���u�i�ɋg�����͋�����č���̖��A�����j���q�̒���̒�i�Ė��V�c�j�ɑ���ꂽ�A�A�A���̐l�̂����H���A��`�̓V�̕A�߂������v
�@�����œ��{���I�́u���{���v�Ɓu�`�v�Ɓu��`�v�����������Ă���B�c�邪�b�������Ă���̂́u���{���i�̋q�j�v���B���K�O��łȂ��u���{���v�́u�q�v�ɍc�鎩�g����A�Ƃ������Ƃ͈ٗ�̂��Ƃ��B�����́u���|�v�̑���͐��K�O��́u�`�i���j�̎g���v���낤�B�����i����j���u�`�̋q�v�Ƃ��āu���ߒu���v�ƌ����Ă���B��a�̑m��w�҂炪�`�������g�D�ɕ֏悵�Ă����̂ł��낤�B���́u�����v���u���ߒu���v�̗��R�͘`�ƒ����̊O����Ǝ�������Ă���B���ߒu���ꂽ�����̋A���͓���̈ӌ��i���{�𖡕��Ɉ�������閧��j��Ė��V�c�ɓ`����ׂɓ��ʂɋA���������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�u��`�v�͋�B�`���̎��́A�����ł͍����ł̒ʏ́B���`�̓V�̕�Ƃ͒����O���̓{�������R�ꕷ�����`���O���ɔᔻ�I�Ȑl�X�i�Ė����j�̌����ł��낤�B
���Ȃ݂Ɂu�V�c�v�Ƃ����̍��͓V���V�c���n�n�����A����܂ł́u�剤�i�������݁j�v�ƌĂꂽ�A�Ƃ����̂�������B�������A��͒� [1] �łׂ̂��悤��[4]�Čf�@�A���{���I�͊C�O�j����C�O�����̔����ɂ��Ă͂��Ƃ��܂������Ǝv����L�q���ނ�݂ɉ��ς��Ȃ��A�Ƃ����������������Ƃ����B���ɂ����ł́u���{���I����̂�����60�N�O�̒��v���荑�̍c��̌��t�v�ł���A�����b �� ����� �� �Ė��I�̈��p����L�q�܂łɈӐ}�I�ȉ��ς��������Ƃ͍l�����Ȃ��B�u���{���V�c�v�Ƃ����Ăт����͉��ϖ����j���ł��낤�B
[4]�@�u��`�v�u�V���v�u���{�v�u�V�c�v�ɂ��ā@�@�u���{���I�̓�������v�X���B�@�����V���@1999�N�@�i162�Łj�ŐX�́u�Y���I�ܔN���i�O�f�j�Łw�䂪�i�V�j�s�߂�w�x�́w�V�x�͐��i����̌�p�ŁA�Ҏҁi�����l���猾�Ƃ��Ă���j�̕��͂ł���������������ł��낤���A���p�����Ƃ��Ă����ĉ��ς��Ă��Ȃ��B�v�Ƃ��āA���{���I�Ҏ҂̉��ς��������Ă��Ȃ��u�����p���v�̗�Ƃ��Ă���B�Y���I�ܔN���ɂ́u��`�v�u�V���v�����邪�A�W�b���̔����ł��邩��A���N���̌��t�̈��p�Ƃ��ĉ��ςȂ���ƍl������B
��206�@�Ė��V�c����Ɣ����]�i�͂������̂��j�̔s��@�@�@�@�@�i2012.12�@���@�z�c���@�lj��j
�@�@�Ė��R��661�N1���ɓ�g�����B�Ė��̂����Ă̊肢�ŁA����w�����邱�ƂɂȂ����ƌ����Ă���B�����R���ɗ\�ɋx�~��������̏o���̉̂����t�W�ɂ���B
���t�W����A���@�z�c���̉�
�u�n�c��(�ɂ�����)�ɑD(�ӂ�)������ނƌ��҂ĂΒ��������Ђʍ��͑����o�łȁv
���̉̂�Ė��ɓ��s�����V���̔܊z�c�P���i�ʂ����̂������݁j�̉́A�Ƃ���ʐ�������B�������A���t�W�̍����Ɂu���ډ̗сi�R�㉯�ǁj�ɂ��A�Ė��V�c�̉̂ł���v�Ƃ���悤�ɁA�u�Ė��V�c�i���z�c���j�̉́v�ł���B���ꂪ������[5]�B�Ė��V�c�̈ӋC���݂�����������o���̍��߂ł���B
������68�̏���̏o�w�͐q��ł͂Ȃ��B�Ė��R�͎��Ԃ������āA4���ɒ}�����q�{�ɒ������B�������A�Ė��͗��̔�ꂩ�炩�A7���ɂ������Ȃ��}�����Ă��܂����A�Ƃ����B
�Ė��I 661�N
�u�����A�V�c�����q�{�ɕ��䂳�ꂽ�v
�u�Ė�����͉����v���ɂ��Ă͎��͂ŏq�ׂ�B���̌�A�c���q����Z�c�q�������������p�����B
�V�q�I
661�N�u�㌎�A�S�ω��q�L�����R�ܐ�]�Ŗ{���ɉq�������v
662�N�u�܌��@�叫�R��紕v�A�����R�D�S���\�z�𗦂��ĖL������S�ύ��ɑ��葴�ʂ��p�������v
663�N�u�O���A�O�E���E��i���{�䗅�v�j����l��h�����V����ł��A�A�A�Z���A�S�ω��L���͕��M�ɖd���̐S���^���A�A�A�a�����A�A�A�V���͕S�ω����Ǐ����a�������Ƃ��Ȃ��Ē����ɓ����A�A�A�����A���R�͌R�D�S���\�z�𔒑��]�ɐw���A�A�A���{�̌R�D���������A�哂�̌R�D�Ɛ�����A�A�A���{�s���ɑނ��A�哂�͌��w�����A���{�����ƕS�ω��͏��ς��A�A�A�i��ő哂�̌��w�̌R��łA�哂�͐i��ō��E����D������ŕ�͐킵���B�����܂����R�͔s����˂��B���ɗ����M������ґ����A�A�A�S�ω��L���͐��l�ƑD�ɏ�荂��֓��������A�A�A�㌎�A�S�ς͓��ɍ~�������v
�@�����Łu���{�v�Ƃ̂L����Ă��邪�A�������u�`���R�v���哱����u�`�����R�i���{�R���܂ށj�v���B�`���R�͑�s�����B���p�����������������Ȃ��̂́A����������ł͂Ȃ��B�������̂����l���̗l�ȏ������ł���B�L�q�ɂ�����l�ɁA�S�ρE�`���A���R�͒t�قȐ킢�������l�� [6] �B
�@�@�M�҂������]��K�ꂽ�ہA���̊������̑傫���̂ɋ������B200�q�k�̐m��i����j�͐��E�ō��N���X�̒��ʍ��i8���j������A�������ɂ͂����������L���ikm�j�����オ��Ƃ����B
�@���̗l�ɁA7���I�ɂ͒��N�����̍��ۊW�Ɍ��I�ȕω����������B�@�������Ƃ̐푈�Ŕ敾������A�@�ɑ��������͍����̔w��̐V���Ǝ��g�݁A�܂��͕S�ς��U�߂Ă����łڂ����B�����ŁA�V���Ƒg��ŕS�ύċ��h�Ƙ`���A���������A�Ō�ɍ�����łڂ��đS�������e�����ɔ[�߂��B
[5]�@�u�z�c���i�ʂ����̂������݁j�v�ƍl�����Ă���l����3�l����B���̈�l���{���̂悤�Ɂu�z�c���i���t�W�j���Ė��V�c�v�ł���B������l�͐Ė������̖��t�W�́u�z�c���v���B������́u�V�q�V�c�̍@�A�`�P���v�̖��t�W�ł̕ʖ��ŁA�V�q�ւ̗��̂��̂��i���l�A�l�����ԁj�A�V������u�l�������v�Ɖ̂��(����A��Z��)�A�V�q�̂�������̂���߂�����i����A��܌ܔԁj�A�u���ډ̗сv���u�䗗�E��́v�Ƒ��̂���B�Ðl��Z�c�q�̖��ł���i���{���I�j�B�����炭�Ė��̕ʖ��u�z�c���v���p�������̂ł��낤�B�O�l�ڂ͓V���V�c�܁u�z�c�P���v�ŁA�����̖��ł���i���{���I�j�B�ʐ��́u�z�c�P�����z�c���v�Ƃ��ēV���E�V�q�Ƃ̎O�p�W����荹������B�������A�u�z�c�P�����z�c���v�̍����͓��{���I�ɂ����t�W�ɂ��Ȃ��A�܂������Ⴄ�ʐl�ł���B�V���̔܂��V�q�̍@�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��B�i�u�l���C�͒N���v��c���@1997�@�V��Ёj
[6]�@�u�w�����]�x�Ȍ�v�@�X�@���́@�u�k�БI�����`�G�@146�o�@�ȂǁB
��209�@���̌��R�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013.7�@�X�V�@�@
�����]�̔s��̔��N��i664�N�j�A�S�ς̒����i�����j���m��i��イ����j�����g�s�����i�����ނ����j��h�����Ă����B
�V�q�I664�N
�u��5���A�S�ϒ������m��͊s�����������킷�A�\���ƌ�����i�ށv
�]���A�폟�������R�g��s�퍑�`���ɔh�����Đ�㏈���̌��ɗ����A�Ɖ��߂���Ă����B�������A�`���͑R�p�����������Ă��Ȃ��B
�V�q�I664�N
�u���A�Δn���E��E�}�������ɖh�i��������A�}�}�j�����i�̂낵�j��u���A�܂��}���ɑ���z���Đ��߂�A���𐅏�Ƃ����v
�V�q�I�ɋL�q������̂́A��a���������͂�������ł��낤�B���͍ēx�g���𑗂�B
�V�q�I665�N
�u9��23�����͗������A�s������ [���Ƃ͉E�^�q�Y���㒌���S�Z�H�R������]�@�@254�l�����킵�Ă����B9��20���ɒ}���ɒ����A22���ɏ�\���̔��������A�A�A12���������܂���A��v
���̌R�g�������������Ē}���ɒ����A2����ɍ������o�����Ƃ����B�����̂��Đ�͒}���̘`�������������Ƃ��Ӗ����A��a�̓V�q�ł͂Ȃ��B����ɑ��A�`���͓��֎g�߂𑗂����B
�V�q�I665�N
�u���A���ю�N��Γ���哂�Ɍ��킷�]�X�q���Ƃ͏��R�⍇���A�ΐρE�召���g�m���E�g�m�j�Ԃ������A�W�����g�l�𑗂��r�v
���g�̋A���ɓ��s�����̂��낤�B������a�����Ɖ��߂���Ă����B
�Ƃ��낪���̕�������A����瓂�g��`���g�߂̖ړI���ʂ��������Ƃ�����B
���������m�O�`665�N
�u�R�ɕ����A�m�O�͐V���E�S�ρE�^���E�`�̎l���U����́i�Ђ��j���ĉ�ɕ����A���@�r���x���A�A�A�v
���c��ɂƂ��čő�̍��J�c���A�`�̎n�c����n��u�R���T�v�ɋߗ��̏U�����Q�����c��͂����x�Ƃ���B���̎��O�����̘`�����o�ȗv���i�V�q�I664�N�j�Ƃ��̌}���i�V�q�I665�N�j�A�����Ę`���g�߂̏o���i665�N�j�������̂��B665�N�̓��g��254�l�Ƃ������l�����������Ƃ́u�c���o�ȗv��������A�Ј��I�s����������v�Ɖ��߂ł���B
�R���T�g�ߒc�̋A���L��������B
�u�S�ς̒������m��A�F�Ái�S�ρj�s�{�F�R�����A�A�A�������킵�A�A�A�ΐϓ���}���s�{�ɑ���v
�����Ɂu�}���s�{�v�����o����B�s�{�͓��̐�̒n�ē̋@�\�ł���A�s�퍑�S�όF�Âɂ�����B���̓s�{���}���ɂ���Ƃ������Ƃ́A�ߋ�3�N�̓��̌c���D��̗Z�a�O������]�����Ƃ������Ƃ��B�k���āA664�N�̌c���o�ȗv���g�͘`���̑R�p�����A���������낤�B665�N�̌}���ɂ͘`�����h�����Ȃ��悤�ɏ��l���Œ��d�ɘ`���g���}�����B�������A�c�����I����667�N�̘`���g�ԑ��ւœ��͈�]���ċ��d�O�������������B�w�i��667�N�ɓ��͍������u���������������i���j�v�i�������j�Ƃ���A�]�T�̏o�Ă������́u�R�p�����ɂ߂Ȃ��`���ɑ��錵�����v���v���������Ɖ��߂ł���B���̋A���L���ɂ�665�N���́u ���і^�v���܂܂�Ă��Ȃ��B���ߒu���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�����A���̒i�K�ł͓s�{�̋K�͂͒}���̍`�p�ɕ����ԓ��̌R�D������������������Ȃ��B���̍����́A�ˑR�Ƃ��Ę`���͑R�p��������Ă��Ȃ������B���N�j�����A�s���ȓ�����`���Ă���B
�O���j�L�V���{�I668�N
�u���́w�`�������x�𗝗R�ɌR�D���C���������w�V�������x�̂��߂Ɖ\���ꂽ�v
�����u�`�������v��������ƌ������Ƃ́A�`�������ւ̑R�p��������Ă��Ȃ������A�Ɖ��߂ł���i�O�́A�Ė��I659�N���ɋg�A�������Q�Ɓj�B
��210�@�V�q���ʁ@
�`�������Ƃ̑Η����p�����钆�A�V�q������ߍ]��Â֑J�s���i667�N�j�A�V�c�ɑ��ʂ����i668�N�j�B�Ȃ��Ė��̖v��6�N���̐��𑱂����ʂł��Ȃ��������A�Ȃ��Ė��̑��������h�ȑ�a���̂Ă��̂��H�@�l�X�ȓ䂪����B�@
�Ė��V�c�͔����]�̐킢�ɏo�������̋�B���q�{�ŕ��䂵���i661�N�j�Ƃ���邪�A�u���͕���͐Ė��R���a�ֈ����グ������Ƃ���ׂ̒���Z�c�q�̉����ŁA�Ė��V�c��������666�N�܂Ő����Ă����v�Ƃ����������i��B�������̈ꕔ�j�B���̍����͉H�g��s�i���{�j�쒆�����ӑ�����́u���{�V�c�a�C�����̐��蕶�v�ł���Ƃ���B
�쒆�����ӑ��������
�u���ДN�i666�N�j�A�A�A���{�V�c���g�J�����܂����A���肵��肵���ӌ䑜��v
���̐��́u666�N�ɓV�q�͏̐��œV�c�ł͂Ȃ��B������V�c�ł��肤��̂͐Ė��V�c�̐������v�Ƃ���B��̉\���ł���B�M�҂͂�����̍��������������B�u�Ė��V�c�͒��c���i�Ȃ����߂�݂��Ɓj�ƌĂ�邱�Ƃ��������B���t�W�̒��c���̉́i���P�|10�`12�j�̒��ɂ͗��ډ̗сi�R�㉯�ǁj�Ɂw�V�c�̌䐻�̂Ȃ�x�Ƃ��邱�ƂȂǂ���Ė��V�c�ł���v�i�܌��M�v����������c�����A�l���C�͒N���@�V��Ё@1997�N�j�Ƃ����B��������M�҂́u666�N�̒��{�V�c�Ƃ͒��c�����Ė��V�c�ł���v�Ƃ�����߂͗L�蓾��ƍl����B���Ȃ킿�u�Ė��V�c��666�N�܂Ő����Ă����v�Ƃ����\���ł���B
��211�@�Ė��V�c�̕���͉������H�@�@�@�@�i2014.10�@�lj��j
�@�u�������Ė�������������Ă܂ŌR���������Ƃ͂��肦�Ȃ��B���N�̗F�M���`���𗠐邱�ƂɂȂ邩�炾�B�v�Ƃ����̂��펯���B�������A���͍��Ƒ��S�ɂ������B�`������Ƃ����{�܂ŖŖS������A�͓��̊��S�Ȏx�z���ɂȂ�B����A���ɂƂ��Ă����N���v������Ă������{��`�����番�f���邱�Ƃ͓`���̉����ߍU��Ɋ����B���{�͕�����X�ɉ��n�ɓ����Ď���Ă����낤�ƍl�����ɈႢ�Ȃ��i��q�u�I�R�掏�v�Q�Ɓj�B����͌����g�ɐ��s�����ɋg������Ɉٗ�ɂ��u���{���̓V�c�A�����Ȃ��v�Ɩ₢�����Ă���i�Ė��I661�N���A�O�͎Q�Ɓj�B��������{�ɕS�ϕ����ɋ��͂��Ȃ��悤���炩�̓����������������Ƃ��Ă����������Ȃ�
�����悤�ȓ��������͉ߋ��F���V�c�ɂ������B�����g�ɐ��s�������{�g�Ɏ��̓��鍂�@�͎���������u�o�����ĐV���������߁i���j�ށv�ƕS�ύU���𖽗߂��Ă���B�Y�F���͕a�ɂ������ĕ��䂵�Ă��܂��i�O�́j�B�Ė��V�c�͍F���V�c�̌�p�҂ł���B����͓������߂��J��Ԃ�����������Ȃ��B�����Ė��V�c��������\��������B�u�Ė��V�c�����q�{�ŕ��䂳��钼�O�A�ɋg������������A�����Ē��q�{�ŐĖ��V�c�Ɂw��`�̓V�̕A�߂������x�Ɠ��̋��d�p������Ă���v�i���Ė��I661�N���j�B���̈ӌ������{�ɂ����炳�ꂽ�Ƃ����炱�̎������Ȃ��B�������Ƃ�����A�Ė��V�c�̋��n�͂����Ȃ�ʂ��̂������ɈႢ�Ȃ��B�����o�����O�ł���B���ɒ��v���肢���������{���A���Ɂu�S�ςāv�Ɩ��߂��ꂽ����ɓ��Ɛ키�̂ł́A���̓{�肪�{������w�M�ƂȂ�B
�����Ė��V�c���A�������S�ɂ���}��������������Ȃ����i�I�j�A����Z�c�q�Ɩd���ĕ�������������\��������B�@������ɂ��Ă��r�ɕ����A�Ė��R�����炵����Q���x�点���肵���悤���B���{�Ƃ��ẮA���肬��̑I�����B����ł����͓{�����B������������Ε�������B�����]�̌��������������Ƃ����́u���{�͓��̔���Ă���v�Ƃ��Ă���i��q�u�I�R�掏�v�Q�Ɓj�B
��212�@�ߍ]��ÑJ�s�@�@�M�҉��߁@�@�@�@�@�@�@�@�@2013.7�@�V�@
�V�q�̋ߍ]�J�s����Ƃ���Ă���B�u���̐N�U������āA��艜�n�̋ߍ]�ɂ̂��ꂽ�ُ�ȉ��a���H�v�Ƃ���Ă���B�����̐l�X������������������Ƃ�������A���炩�Ȑg�ɔ���O�G�̋��Ђ���������ł͂Ȃ��B�m���ɓV�q�̑J�s����667�N�͒}���ɓ��̓s�{���݂���ꂽ�N�����A�܂��`���̑R�p���͑����Ă���B
�M�҂̐����́u�V�q�̋��ꂽ�̂́A���̐N�U���̂��̂ł͂Ȃ��A�`�������ӓ��ɋ�����ƁA���͘`���ɑ�a���U�߂�����A�Ƃ����z�肾�v�ƍl����B�`���͐_���̌����ȗ�400�N�ԑ�a�����Ƃ��A�����G���E�������Ƃ��ĕ��͂��s�g�������͖��������i�ֈ�̗����܂߁j�B�������A�`�������̘��S�ɂȂ�A���̖��߂ő�a�������n�܂�͖̂��炩�������i��q�u�I�R�掏�v�Q�Ɓj�B�`���R�͎�̉����Ă����ɂ��Ă��A�����Ȃ�A���łɑ�a�ɓ����Ă��������̘`���̉����E�M���E�����A����ɑ�C�c�q�h�܂ł������ł��ēV�q�𗠐�`���R�ɐQ�Ԃ鋰�ꂪ�������B
�V�q�͋ߍ]�֑J�s���āu�`���̓������J�s�������B���ׂ̈ɓ����������B�������A���̏����Ƃ͑�C�c�q�ւ̘`�������ʂ��v�Ƙ`���ɒ�Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B���������A�Ė��͉��̂��߂ɘ`�����c��Ƃ��ڂ�����C�c�q����荞�̂��A���̑�C�c�q��4�l���̓V�q�c���𑗂荞�̂��B����́A��C�c�q���a�̗͂Ř`�����ɉ��グ�A�V�q���`�����̊O�ʂƂ��Ę`������ɂ���헪�A���炭����������Ă̒����헪�̎��s���B
����A�`���ɂƂ��Ă������a�J�s�͖��͂̂͂����B���̋��Ђɂ��炳���`��������C�c�q�i�`�����c��H�j�ɏ��ʂ��邱�Ƃ������������ʼn\��������B
�`�������e����a�h�ɑ���Γ������S�Ƃ��Ăł͂Ȃ������̐��Ƃ��Ă̒��v�ɓ��ӂ��邾�낤�B�V���̑O�Ⴊ����B���E�S�ρE�����ƑΗ������V���͓��̉��ɔ�э��ލ����̐������ŁA�ނ��뎖����̓Ɨ����ێ������B
�V�q�ɂƂ��Ċ댯�ȓq�������A���������O�Ⴊ�������B�����̂ڂ��āu�����̕ρv�̎��A��{���ƍc�ɓV�c�͑�a�����̍F���V�c�ɏ��ʂ��ď�{�������a�����Ɉς˂����A�F���V�c�����䂷��ƐĖ��V�c���c�ʂ����߂����B�@���ʓI�ɑ�a��������ɓ��ꂽ�i�攪�́j�B���A��a�����V�q����̉������`�������Ɍ}������A��C�c�q��`�����ɁA���̎q���Ǎc�q�i�V�q�̑��j���c���q�ɂ���A�����`�������ǂ��������A�V�q���O�ʑc���Ƃ��Ę`�����x�z����B�V�q�͂��̐헪�̎��s���}�����悤���B�Ė��V�c�̈⌾��������������Ȃ��B���������ċߍ]���ɑJ�s����ƂƂ��ɁA��g���ӂ̌R���{�݁i������j����������(667�N)�B
��213 ���R�i���Ƙ`���̒��v�@�@�@�@�@�@�@�@
�Ƃ��낪�A�V�q�̋���͈ӊO�ɑ������������āA�헪�͋����Ă��܂����B
�V�q�I�i669�N�j
�u���̊s��悰��2�疼����B�ɔh�����ꂽ�v
���ɘ`���͑R�p�����~�߁A���̍����̐��ɂ͂������B����������j��������B
����v�`���`
�u�������N�i670�N�j3���A�g�������i����j������炮���ꂷ�B����A�p�i�Â��j�Ę҂�����v���v
����܂Œ��N�`���́A���Ƃ������g�𑗂��Ă����v�͂��Ă��Ȃ������B���̂��Ƃ𒆍��j���͌J��Ԃ��m�F���Ă���B�@��610�N�����Ō�Ɂu�v�v�̎����g�킸�u���v�̎��݂̂��L���Ă���B�������A�����̋L�q�ł́u���v�v�ƂȂ��Ă��āA�`���̑R�p���͖����Ȃ��Ă���B�`���͂���܂ł̑Γ��Γ��H�����̂āA���v�H���ɓ]�������B
�V�q�I671�N
�u�Δn���i���}����ɕ{�Ɏg�������킵�āA�s��悰��2�疼���A�ߗ��̒}���N�F��n ��A��Č���v�����Ă������Ƃ�`�����v
�F��n�̑��ɂ������̉����l����ߗ��������Ɏc����Ă��āA�����͂�������ޗ��ɂ��Ē��v�������t�����Ǝv����B
��214 �S�ϐl�I�R�掏�@�@�@�@�@�@2013.7�@�V
�@���̎����̍��ۊW�������j����2011�N�ɒ����Ō��������B�S�ϐl�I�R�i�ł�����A�l���j�掏��{�ł���B�I�R�͒����n�S�ϐl�ŕS�ϒ��썂�������A�Γ���ŕߗ��ƂȂ��������F����Ę��S�S�ϐ����̍��������ƂȂ�A���̑Θ`�����ɂ���������B�V�q�I665�N���i�O�f�j�́u�E�^�q�Y���㒌���S�Z�H�R�v�����̐l�ƍl�����Ă���B678�N����v�����B�掏�̑�{�݂̂�2011�N�ɒ����Ō��������B
�@�S��884���̊W�����������B�����������ڃ������B
�S�ϐl�I�R�掏
�u�A�A�A���錰�c�ܔN�i660�N�j,���R�i���R�j�{�ˁi�S�ρj�炰����A�A�A�����i�Ƃ��Ɂj���{���P噍�i�c�}�j�͕}�K�i�ߋE�j�ɋ���ĈȂ����n�i���j��癁i�̂���j���A�A�A�R���j��A�A�A���z���g�A�A�A�i�ȉ����E�S�ϐ�̕`�ʁj�A�G��͈�U�b���̂��A�A�A���i���Ȃ�j�����]���\�l����́i�Ђ��j���A�������ĉy����A���ɉ���ւ荶�^�q�Y�����َ������A�A�A�v
�@�������ɂ��Ă͓����̒����V���Ȃǂŗl�X�Ȑ������Ȃ��ꂽ�B
(1) �悪���Ă�ꂽ678�N���Ɂu���{�v�Ƃ����������g���Ă���B�ł������Ⴉ�B
(2) �u���{�v�Ƃ͘`���̂��ƁA�`���̎c�}���������}�K�Ƃ͋ߋE�A���̈Ӗ��́u�`�����ߋE�ɑJ�s�����̂ł͂Ȃ����v�i�ꕔ�̋�B�������j�B
(3) �@�`�����́u�V�q�v����u���v����b�v�ɂȂ��Ă��邩��掏�́u�G���U�b���̂��v�Ɉ�v����B�`�����͏o�w���A�킢�߂炦���A�b���̗����炳�ꂽ�̂ł͂Ȃ����B
(4) �@�ߗ��̒}���N�F��n�͓��Łu�����ւ�`�������َ�����v�����荞�܂�Ă����̂ł͂Ȃ����B
��215�@�F��n�͘`�����łȂ��@�@�M�҉��߁@�@�@�@�@�@2013.7�@�V
��216�@�V�q�V�c���u�����`������܂Ɓv���u���{�v�ɉ���
�`�������S�����Ē��v���n�߂Ă��܂����i670�N�j�B�V�q�̒��N�̐헪�������Ă��܂����B�u���ƑΗ�����`���ɑ����Ę`������\�ƔF�߂Ă��炤�v�A���ꂪ���N�̑�a�̐헪�������B�Ƃ��낪�A�`�������v���n�߂ẮA���̉\���������Ȃ����B�c�铹�͘`������Ɨ����邱�Ƃ��B
�O���j�L�@�V���{�I670�N�@
�u�`���A�X�i���j���ē��{�ƍ����B���猾���A�w���̏o���鏊���߂��x�ƁB�Ȃ��Ė��ƈׂ��v
�`�������������ƌ����̂����A���̎j���ȊO�ɂ��̉������L�����͖̂����B�������������ɂ͂��̌���`���͓o�ꂷ��B��������u����͌㐢�̓��{�i�����j�����i701�N�j�̋L�����A���̔N�ɂ͂ߍ��̂��낤�v�ƌ����Ă���B�������A701�N�́u�����v�ł����āu�����v�ł͂Ȃ��i�����{�I�@��q�j�B
�u���{�v�͌Â��͘`���E���N����ߋE(���o�����)���w�����ꑼ�̂Ƃ��āA�܂��p�̓V�c�����玩��O���̏�ʂő�a����̊��ꎩ�̂Ƃ��Ďg��ꂽ�i��͎Q�Ɓj�B���̎����i670�N�j�ɁA�ߋE�E��a�̂����ꂩ�̍������u���{�v�Ɖ����ł���l���͓V�q�V�c�������Ȃ��B�ł͉����̌��́u�`���v�͋�B�`�����낤���B����A�V�q�V�c�ɏ@�卑�̉��������͖����B��̉\�����l������B����͑�a���삪������u�`���i�̈���j�v�Ǝ��̂��Ă������Ƃ��i�V�������{�`�E���ËI�́u�`�c�v�Ȃǁj�B�u�����`���̒��̕����`���v�Ƃ����Ӗ����낤�B�����u�����`���i���ߋE�E��a�j�v���A�V�q�V�c�������`�����Ƃ��āu���{���v�ɉ������邱�Ƃ͘_����\�ł���B�u�����`���̉����v�̑_���́A�u�@���`������̓Ɨ��A���S�`���Ƃ̌��ʁv���낤�B�`���Ǝ���A���ƘA�g����V���ƒʂ����̂��B�V����������������ꂽ�悤���i�O���j�L670�N���j�B����������ɂ��A���̔N���瓂�ƐV���͑Η����n�߂��B
��217�@�p�\�̗��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2013.7�@��
�u�`���Ɠ��{�̑�A�����a���哱����v����C�l�c�q�Ɋ��҂��������������B����ɐ�ē����`������S�����邱�Ƃ�V�q�V�c�͋��ꂽ�B�������A����Ă����ʂ�A�`���͓��̘��S�ƂȂ�i670�N�j�A��a�ɐ�Ē��v����悤�ɂȂ����B�V�q�V�c����C�l�c�q�i�c����j�ɏ��ʂ��闝�R������ꂽ�B�V�q�͎q�̑�F�c�q���d�p���A���ɑ�����b�ɏA�������B���ꂪ�p�\�̗��̈������ɂȂ����B
�V�q10�N�i671�N�j�A�V�q�͕a�C�𗝗R�ɏ��ʂ��Ă��邪�A��C�l�c�q�͗�������Ƃ݂Ď��ނ��A�o�Ƃ��č���R�ɂ��������B���̌�V�q���v���A���N�i672�N�j6���u�p�\�̗��v���n�܂�B
�������͓V�q�R�Ōł߂��Ă��������C�c�q�͔��Z�𗊂����B�u��C�c�q�͘`���𗊂����v�i�Óc���j�͐������Ȃ��B��C�c�q�͓��ւ̑R�ӎ���ۂ��Ă������瓂�̘��S�`���𗊂�͂����Ȃ��B�܂������������V���i�����j�ɖ�������Γ��̓G�ƂȂ邩��^�����Ȃ������ł��낤�i��q�j�B�c�ʌp���푈�̌`��������킢�����A���ۗ͊w�E�V�����́E�ߋE�Βn���ȂǗl�X�ȗv�f�����G�ɗ��ݍ����Ȃ���A���{�Ñ�ɂ�����ő�̓���͒Z���Ԃő�C�l�c�q�����������B��C�l�c�q�͓������ő��ʂ��ēV���V�c�ƂȂ����i672�N�j�B
��218 �V���V�c�́u��`���v�\�z
�V���V�c���Ҏ[���w�������Î��L�i���́j�ɂ́u���{�v����x���o�Ă��Ȃ��B�V�q�V�c�̒���u���{���i����A�����j�v��ے肵���̂��B�ł́A�����͉��ɂ����̂��낤���H�@�V���V�c�́u��`���i�����킱���A����A�����A������܂ƁA�a��A�����j�v�̍\�z�������Ă����Ǝv����B�ߋ��ɂ��������ꍑ���u�`���v�ɑ��āA�u��`�i������j�A����A�����v�͗Y���I��Ė��I�ɂ��o�Ă��邪�����܂Ŏ��́E���̍����ł���B������u�`���v�ɑ������V�����V�������̐������ꍑ���ɂ��悤�Ƃ����̂��낤�B�����v�k�ǂ́u俀�i��Áj�v���u��`�v�ɗR������A�Ƃ������߂��O�q�����B�V���͂��́u��`���v���Č����悤�Ƃ����B���̂��Ƃ́A�V�����Ҏ[���w�������Î��L�̖`�������Ɂu��`�i������܂Ɓj�L�H�Ó��i�����j�v�̓��Ď������邱�Ƃ�����킩��B����̓V�c���̓��ɂ����u��`�i������܂ƁA��܂Ɓj���q�v�̓��Ď����Ҏ[���̓V���̈ӎv�ł͂Ȃ����H�@���̐S�͓��ƑΓ��ɂȂ낤�Ƃ����`���́u��`�v�̐��_�������p�������A�Ƃ����V���̈ӎv�̕\��ƍl������B�����ł���Ȃ�A�V���͐����̓쒩�h�`�����ƍc�q�ł���B
�u�V���̑�`���\�z�v�Ɖ��߂���������̍����́A�V���̕���㑷�̕����V�c���u��`�i����E�a��A�����j�v���u��`�i��܂ƁA�a��A���s���j�v�Ɋi�����������炾�i707�N�Ȍ�̑�a�n���Ɍ����j�B�V�q�́u���{�������v��V�����ے肵�A�V���́u��`���v�����ے肵���������ƂɂȂ�B������������I�Ӑ}�ƍl������B�t�ɂ��ꂪ�u�Î��L�́w��`�x�͓V���̐����I�ӎv�v���������Ƃ��������Ă���B
��220�@�`���̏I���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2013.9�@���M�j
���N�����ł͍�����j�����V�����D���ɂȂ��āA���X�ɓ��ƑR����l�ɂȂ�A���ɓ��R�N��������ǂ��o���Ē��N�ꂵ���i676�N�j�B���R�̔����ދ��ŋ�B�̓��R���k�����ꂽ�ƍl�����Ă���B
���R����돂�Ƃ������S�`���̏����S���������B701�N�̓��{�����܂łɘ`���͏��ł����ƍl�����Ă��邪�A���A�ǂ̗l�ɂ��ď��ł����̂��A�肩�ł͂Ȃ��B���͌����ɂ͘`���̖ŖS�Ɋ֗^�����A�Ƃ͂��Ă��Ȃ��B�������j�̋������`���`�̖����Ɂu�����]�̐킢�v���L���Ă��Ȃ��B����́u�ΕS�ϐ�v�̎c�G������ł����Ę`���͕S�ς̎x�������ɉ߂��Ȃ��B���Ƙ`���͌����ɐ푈������ł͂Ȃ��B�܂��A�������ɂ́u�`���`�v�ɑ����āu���{�`�v�����邪�A�u���{�͘`���Ƃ̊W���]�X���Ă��邪�`���Ɠ��{�͕ʎ킾�B�v�Ƃ��Ă��邾���ŁA�����ɂ́u�`���̖ŖS�̗��R�ɂ͊֒m���Ȃ��v�Ƃ̗���Ɍ�����B
�������A�O�͂ŋ������S�ϐl�I�R�掏
�S�ϐl�I�R�掏
�u�A�A�A���錰�c�ܔN�i660�N�j,���R�i���R�j�{�ˁi�S�ρj�炰����A�A�A�����i�Ƃ��Ɂj���{���P噍�i�c�}�j�͕}�K�i�ߋE�j�ɋ���ĈȂ����n�i���j��癁i�̂���j��v
�@���̕��͂���u�`���͔����Ă���v�Ɠǂݎ���A�ƑO�͂łׂ̂��B�X�Ȃ���߂̉\��������B���̕掏�ɂ́u�S�ρv�Ɓu���{�v�����邪�u�`�v���������B�ނ�665�N�A�g�߂Ƃ��ė�������́u�`���v�ł����āu���{�v�ł͂Ȃ��B���́u�`�v���Ȃ��B���̎����܂Łu�`�v���L�^���Â��������j���A�����u�i660�N�A�S�ςŁj�`�O���тɍ~��v�i�������S�ϓ`�j�A�u�i670�N�j�҂�Ē��v���v�i����v�`���`�j�Ȃǂ��A���̎����Ȍ�o�����Ȃ��B���̂��Ƃɒ��ڂ���A���̕��͂́u���R�͕S�ς炰���B�`���͔����ď��ł����B���{�̎c�}�͋ߋE�ɋ����Ĕ����̂���Ă���v�ƁA�����������ēǂނ̂��Ó����낤�B�掏��678�N�ŁA���R�̓P�ނ̑O��ł���B���̎����Ɂu���R�̔����ď��ł����v�Ƃ͂ǂ�ȏ��l�����邾�낤���B
���R�͕S�ς���P�ނ������ɂ͕����������D���A�{�a��j������A�S�ω��A�c�q�̂ق���1���l��ߗ��Ƃ��ĘA�ꋎ�����ƌ����Ă���i���̌�ɘ��S���� �� ���R���j�B��B�̓��R�͍ő��2000�l������A�����R�ł͂��邪��̌R�ł͂Ȃ��B�������A���R�͘`������S�����A���S�`���ɑ��S�ς��瓦���������M���̈����n���A�ނ炪�S�ς��玝���������̈����n����v���������낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�S�ϐl�݂̂Ȃ炸�A�S�ς��瓦���A�����`���R�̉����⏫�R�����̑ΏۂɂȂ����ł��낤�B�ނ�͎R�����{�i�ߋE�j�ɐg����߁A���R�̈����n���v���͎���ɋ��D�ɂȂ�A���S�`���͂����ٔF���A�X�ɋ��͂�����������Ȃ��B���R�P�ޑO�ɂ͌����Ȃ����D�E�\�s�E���̗�����B�`�����P�������Ƃ��e�Ղɑz�������B�Ȃ��Ȃ�A��B����ߋE�֓��������͑����A��B�Ɏc���ꂽ�M�d�Ȉ�Y�����܂�ɏ��Ȃ��B
�`�����ɂƂ��āA�`���̊O���@�\�������`�����@���ƔF�߂鍪������������A��������������S�`���͂��͂�@�卑�̋z���͖͂����B�`�����̗�����`�������̑�a���ŁA�`���͋}���ɋ��E�k�������āA�����͂�̂悤�ɏ��ł����̂ł͂Ȃ����낤���B
���̍����̈����q�����u�I�R�掏
��221�@��ɓa�@�`�����ł̖T��
��222 �V���V�c�̋L�I�Ҏ[���Ɓ@�@�Î��L�@�@�@�@�@�@�@�i2011.10�@���j
��223�@�Î��L�� �u�`�i��܂Ɓj�v
��224�@�u������n�v
��225 �V���V�c����
���R���P�ނ��A�`���͏��ł����B�V���ɂƂ��āA�܂��ɂ��ꂩ��u������`���v���������悤�Ƃ��鎞���������B��a�̏������̈ʒu�Â������m�ɂ��A���j�̕Ҏ[������Ȃ�ɐi��ł����B���`���́u��`���ւ̋z���v�������i��ł������낤�B
�������A�V���V�c�́u��`���v�̖��̎��������邱�ƂȂ��A686�N�ɕa�v�����B�V�������A�c�@�������̐����Ƃ�690�N�ɑ��ʂ����Ƃ����B�����V�c�͓V���V�c�̘H�����p�����A�ނ��땃�V�q�V�c�̐e���H���ő�a�́u���{�v���S�̐V���ƍ\�z�𐄐i�����B�V�q�V�c�ɂ��̘H�������������̂����������ŁA�����V�c�ɏ��������̂������̑��q�����s�䓙���B���̂Q��ɂ킽��W�ɒ��ڂ������B
���̂悤�ɂ��āA�`���͍Ō�̎x���҂������V���̕���ɂ���āA�p���ƍČ��̓r������ꂽ�B�����V�c�́u��ɓa�v���u�����v�ɖ߂��A���̑������V�c�͍��s�����u��`�i��܂ƁA�a��j�v�ɕς���[5]�B�V���́u��`�i������A����A�����j�v�E�u��`�i������܂Ɓj�A�a��A�����v�v���u��`�i��܂ƁA�a��A���s���j�v�Ɋi���������⏬�������̂��i�O�͖����ŐG�ꂽ�j�B
����ɂ͏]���u�������v�̐헪�����A������I�����ĕ��̐헪���̂����v�Ƃ������߂����邪�A������́u���ƑΗ������`���E��`���𑫉��ɂ������艟�������p�𒆍��Ɏ�������ŁA���߂Ē��v�O���𐿂��v�ƌ����A�����I�ȊO��H�����I�����ꂽ���ʂƍl����B���̎��_�ł́A�V���V�c�̐e�`�E�����H���́A�ŖS�����`���Ɠ����u�낤���ϔO��`�i���z��`�j�v�������ƌ����ׂ����낤�B�������ē��ւ̑R�p����������������A�V���V�c������������u���{�v���A���x�͕����V�c�������u���{�v�Ƃ��Č������A�Ҏ[���̍��j���u���{�I�v�Ƃ��A�O��̓��{�̒��v�����g�ւƑ����B
[5] �u��`�v�@�@701�N�ɑ�a�n����u�`�i��܂Ɓj�v����u��`�i��܂Ɓj�v�ɓ��Ď��ύX�����B������O�̓V���I4�N�i675�N�j�ɔn����u��`�i��܂Ɓj���v�ƌĂԗႪ�o�Ă��邪�A����͓��{���I�̕Ҏ[���̑k�y���ς��낤�Ƃ����B�u��`�i��܂Ɓj�v�͌�Ɂu��a�i��܂Ɓj�v�ɕύX���ꂽ�B�u���{�̍����v��c���@�|�Ё@1993�N
��226
���{�����ƌ����g
�����V�c�̍c���������́A697�N�Ɏ������p���œV�c�ɑ��ʂ������A701�N3���ɉ��߂Č��������B
�����{�I [6] 701�N��
�u3���A�Δn���������v���A�������đ�N�ƈׂ��A�����n�ߊ����ʍ����������B�v
�u�Δn�����v���v�Ƃ́A�u�Δn�Ƃ������`�����n�����i�������@��q�A�u�������v�ł͂Ȃ��_�ɒ��ځj�v���Ƃ̌֎��ł���A�u�����v�Ƃ́u�����v�ƈقȂ��Č�����V���Ɍ��Ă邱�ƂŁA�V�����E�V���Ƃ̎n�܂���Ӗ�����B�ł́A�V���Ƃ͉��ƍ��������H�@�������u���{���v�ł���B�������A���̓��{���́u���{���̌����͐_���ɂ��v�Ƃ��Ă���̂Łi���{���I�j�A701�N�͌��O�㌚���ł͂Ȃ��A����ȑO������{�������݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA�����͑��ʁi697�N�j����Ƃ����ɓ��{�������������A�Ǝv����B����������j��������B
�O���j�L�@698�N�u���{���̎g�A����v
�V�q�V�c�́u���{���i�����j�v�����i670�N�j�́A�V���V�c���p�~���āu��`���i������܂ƁA�����j�v���̂��Ă����A�ƍl�����邩�炾�B�ł́A797�N�����̒���u�����{�I�v�́A720�N�̓��{�I�i���ߓ��{���I�A791�N�j�̗����m��Ȃ���A�Ȃ�701�N�Ɋւ��Č������Ӗ�����u�����v�ƋL�����̂��낤���H
�u�ǂ̍�����̂���̌����_�b�������Ă���B��������͌��O�ŁA���Ԃ�701�N���������v�Ƃ��������i797�N���j�̏펯��f���ɋL���Ă���A�Ɖ��߂ł���B
���O�͌��O�Ƃ��āA701�N�́u�����v�ȑO�̑�a�́u���v�ł͂Ȃ������̂��H�@�@�卑�`���̉��Ŏ��O�̌����������A���j�������A���ʐ��x���蕨�ŁA�O�����[�g�������Ă��Ȃ��A���ۓI�ɂ͂ƂĂ���l�O�̍��Ƃł͂Ȃ������B������A�������č��ۓI�ȏ��F�邱�Ƃ��K�v�������B�����g�h���͌����̎d�グ�̋V���ł��������B
[6] �u�����{�I�v�@797�N�����̒���@��Ґ���^��
��227�@���̔F��u�`���Ɠ��{�͕ʂ̍��v
���N�A�����͌����g��h�����āA�����̍��ۓI���F�����߂��B�����g�͑���160�l�A��\�͈��c�^�l�i���肽�܂ЂƁj�A�ݗt�̐l�Ƃ��ėL���ȎR�㉯�ǂ����s�����B���̌��ʂ́A���̎j���u�������v�ɋL����Ă���B���Γ`�̒��ɁA�����E�S�ρE�V���E�`���ƕ���ŏ��߂ē��{���̏������Ă��Ă���B
�܂��A�]���̘`�����ɂ��ẮA���łɉ��x���L�ڂ����B
��������`���Θ`����
�u�`���͌Â̘`�z���Ȃ��A�A�A���X�����ƒʂ��A�A�A���̉��̐��͈������A���̎��͑����v�k���A�A�A����݂���12�������A�A�A���5�N(631�N)�A�g�������킵�������������A�A�A���\�m�����킵�A�A�A�V���̍˂Ȃ��A���q�Ɨ�𑈂��A�A�A22�N(648�N)�Ɏ���A�܂��V���ɕ����ĕ\����A�ȂċN����ʂ����v
�`�����̍Ō�́A648�N�́u�V���ɑ����ď�`�����v�ŏI����Ă���B�����]�̐킢���A���S�`�����o�Ă��Ȃ��B�O�҂͓��ɂƂ��ĕS�ςƂ̐푈�ł����āA�`���W�̎����ł͂Ȃ��B��҂͓��R�̖��[�̎��s�ł����Ȃ��B�`���͋L�������̂��Ƃ������A���j����������B
����ɑ��āA�V���ȓ��{���̏��́A
��������`�����{��
�u���{���͘`���̕ʎ�Ȃ�B���̍��͓��̕ӂɍ݂���ȂāA�̂ɓ��{���ȂĖ��ƂȂ��B ���͂��킭�A�`���͎��炻�̖��̉낵���炴��������A���߂ē��{�ƂȂ��ƁB ���͉]���A���{�͋������A�`���̒n�������ƁB ���̐l�̓����͑�������ܑ�ɂ��āA�����Ȃđ����A�̂ɒ����͋^���A�A�A���̑�b���b�^�l�A����������v���v
���͓��{�̌����g����A�`���Ɠ��{���̊W�ɂ��ā@�@�ʂ̍��A�A�`���̉����A�B���{���`�̒n�������A�Ɩ�������R�̐��������l���B����������͐����ɋ^���������A�u�̂ɒ����͋^���v�Əq�ׂĂ���B�����āA�@�ʂ̍��@������F�߁A���v��F�߂���ŁA�����J�n�̏Ƃ��ē��{���𗧂Ă��B����ȊO�̓��{�̎咣�A�E�B�ɂ��ẮA�L�������ɗ��߂Ă���B
�������������B
(1) �u���{���͘`���̕ʎ�Ȃ�v�@�@�`�������g�ɐ��s�������Ì��@�g�ȗ��A���{�́u�`���Ƃ͕ʂ̍��v���J��Ԃ��咣��������A��������͔F�߂��B
(2) ���������̉������͎���Ă��Ȃ��B�u�`���͎��炻�̖��̉낵���炴������݁A���߂ē��{�ƂȂ��v�͓V�q�V�c���u�`���i�������A��a�j����{���Ɖ����������̗��R�v�i�O���j�L670�N�A����v670�N�A�O�́j�����A�����͂�������Ă��Ȃ��B�u�`���i�������j����{���Ɖ��������v�Ƃ̎咣�Ǝ��A�u�`���͖ŖS�����B�`���̌p���E�P�Ȃ�����͔F�߂Ȃ��v�Ƌ��₵�Ă���B
(3) �u���{�͋������A�`�����n���v�́u�`�����ł̌�A�`���̋��n���v�̈Ӗ��ł����āA�u�`�����v�łȂ����狕�U�ł͂Ȃ����A�������́u���{�͘`�����z�������v�Ƃ����咣�Ǝ��A������u�`���̌p���v�Ƃ��ċ��₵�Ă���B�u�`���͖ŖS�����v�Ƃ̗��������炾�B
(2)(3)�̂�������A�u�����Ȃ��đ����v�ƌ�����悤�ȋ��U�������Ă����ł͂Ȃ����A�����̗����Ă͂��Ȃ��悤���B
��228�@���{���I�̕ҏW���j�u�`���s�L�ځv�Ɓu���肬��̋L�ځv
��229�@�u��̘`���v�Ɓu�`���s�L�ځv�@�S�ώO�����Q�l�Ɂ@�@�@(2014.8�@�@�lj�)
��230�@���̌�̓��{�@
���{���I�����O�Ɂu�ŋ߂܂ő��݂����`���v����{������r�����邱�Ƃ����d�グ�������B����ɂ́A�`���Ɋւ���L�^���܂����j������肾�����B�����g�A�����708�N�A����͂��������]�܂����Ȃ��������֏��Ƃ��Ėv�������B
�����{�I708�N�u�a�����N�Ƃ��A�A�A���(��������)���s���A�A�A���߈ȉ��A�߂̌y�d�Ɋւ��Ȃ��A�A�A���ׂċ����A�A�A�R��ɓ����A�֏������܂��B���āA�S���o���Ă����Ȃ����̂́A�{���̗l�ɍ߂���v
�@�ǂ̗l�ȏ������֏��ɂȂ������͐����Ēm��ׂ��A���낤�B�@
�������āA���{���I�͂܂��u���{�I�v�Ƃ��Ċ��������B
�����{�I720�N
�u�ɐl�e���A������{�I���C���B�����ɐ����đt�シ�B�I30���n�}1���v
�����̗��N�i721�N�j�ɂ͑������A�{���ɂ����Ĕ��m���M���B�̑O�ōu�`������{�I�u⥁i��������j�����I�ɐ݂���ꂽ�B����́A�J�u����I�u�܂łɐ��N��v���钷���u���ŁA���{�I�̌Îʖ{�̌P�_�i���I�ÌP�j�Ƃ��Ď������ꂽ�ƌ����B�����ł͍��������ɂ͓��{�̐��������ő���ɋ��邵���B�����Ɏア���{�����ɐU�艼����t���āu�_���ȗ��A�R�Ձi��܂Ɓj���`�i��܂Ɓj�ł���A��`�i��܂Ɓj����a�i��܂Ɓj�����{�i��܂Ɓj�ł���v�Ƌ������B���{���I�́u���{�v���o�ɁA�u����{[���A���{�A�����떃���Ɖ]���A�ȉ��F����ɂȂ炦]�L�H�Ó��]�X�v�Ƃ���A�u���{�i��܂Ɓj�v����p����Ă��Ȃ������V�����P�ǂł��邱�Ƃ��ǂݎ���B�������A�C�O�����̈��p�u���{�i�ɂ��ۂ�j�v�ɂ��K�p�����Ă���i���̗��\�Ȓ����ҎҒ��ł���͂����Ȃ��A����Ғ��ł��낤�j�B�C�O�ɒʗp���闝���ł͂Ȃ����A�U�艼���𗘗p���āA���������Ɂu���{�͘`���v���J��Ԃ����荞�̂��B���q����́u�ߓ��{�I�v����́A�u����v�i��́j���m�肵�����߂���u���{����`�v�u�V�c����`�V���v�����ɐ[���Z�����Ă������Ƃ��f����A�Əq�ׂ��B�Ȍ�A���{���͂��̎咣���J��Ԃ��A����ɑ�����������u���{�̎咣�v�Ƃ��ĔF�m���Ă������B
�ʏ�j���͗��܂ł͐G�����̂��B�������A�قڊ����ȁu�`���s�L�ځv����������u�`�������{�v�̋��邪���������B
�������Ę`���͏I�����������łȂ��A������Ă��܂����B
�X�Ɍ�N�A�V�q�n�̌��m�V�c���u���{�I�v�̓��Ɏ����I�ɉ��ς������ēV�q�n�𐳓��Ƃ����u���{���I�v�����߂Č��肵���i791�N�j�B���ꂪ�����́u���{���I�v�Ƃ��ē`����Ă���A�ƌ����Ă���B���̂��Ƃ͖{���u�`���ʎj�v�͈̔͂ł͂Ȃ��̂ŐG��Ȃ��B�{���ŎQ�l�ɂ����͉̂����́u���{���I�v�ł���̂Łu���{���I�v�ƋL�q�����B
��231�@�V�����̗���
��232 �@�����̕ϑJ�@�@�@��a����̏�{���ƌ������@�@�@ �i2013.2�@�lj��j
�Ō�Ɉꕶ��lj��������B���{��������A��a����͌����ɂ́u�_���V�c�ɂ͂��܂�A�q�B�V�c���o�ēV�q�V�c�Ɏ����a�̉����v�ł���B�������r���o�߂Ɂu��B�E��a�̔�`���n���̑Γ����́v�����������Ƃ��������B���̗����ɂ���ď��߂āu��a����̖@�����ւ̓��ʂȎv������v�������������ł���A�ƍl����B�u�@�����̕ϑJ�v�ɂ��Ă܂Ƃ߂�[8][9]�B
(�P) �@���������̎߉ގO�����͏�{�@�c�i�Ė��V�c�̑c���A�攪�͎Q�Ɓj�̕a�C�������F�O���ĂU�Q�Q�N�P�����肳�ꂽ�i�@���������߉ގO�������w���A�掵�͎Q�Ɓj�B�������A�F�O�͊��킸��{�@�c�͈�J����̂Q���ɕ��䂵���B�x��đ��͗��U�Q�R�N�R���Ɋ��������i���j�B
(�Q) �߉ގO�����͎ړx�`�ő����Ă���i�M�҉��́A[�P�O]�j�B���̑������u����@�����̋����E�d���́u��d�i�g�ݐɈ͂܂ꂽ�y��j�v�����Ɠ����ړx�`�ő����Ă���B�@�����͂��̑������u���邽�߂ɓ����ɔ��肳�ꂽ�ƍl������B�ꏊ�͏�{���Ƃ̖{���i��O�O���S���{�{�j�߂��ł��낤�i�掵�́u�j�B
(�R) ����ҁA�����@�����̑n���҂͏�{�@�c�̌p�k�ł��鐹�����q�ƍl�����Ղ����A�������q�͑O�N�̂U�Q�P�N�Q���Ɋ����I�����Ă��邩��Ⴄ�i���{���I�A��ŐĖ��V�c�̏f�����攪�͎Q�Ɓj�B
(�S)�@�����̊�d�i�ړx�`�j�̏�������剮�͎ړx�a�ő����Ă���B�V������d�̏�ɁA������ڒz�����悤���B����҂͏�{�@�c�̕a�C����������ċ}���Ō������悤�Ƃ����̂��낤�B�����Łu�ڒz�v�Ƃ͌�N�́u��O�����a�ւ̈ڒz�v�i��q�j�ł͂Ȃ��u�������̔�O���i����j�ڒz�v�ł���B
(�T) �d�����ʂ̎ړx�b�ő����Ă���B�ʂɂ��������̂��ڒz�����悤���B�d���̐S���͂T�X�S�N���̂ł���i�S���̔N�֔N�㑪�肩��j�B�������Q�O�N�O�Ɍ��Ă��Ă���B���łɂ�����������ڒz�����؋��ł���B�S���i�ړx�b�j�̈ꕔ�͎ړx�`�Œlj��H����Ă���B�ڒz�̍ۂɉ��H�������̂ł��낤�B (�U) �����̉_�`�I�i�Ђ����j�͌d�̓��̂�����Ì`�ł���Ƃ����i���z�j�j�A�����͌d�������X�ɌÂ��B�ڒz�̏؋��ł���B�����E�d���̏֊K�i�������j���ړx�`�ő����Ă���B�ڒz�̍ۂɒlj����ꂽ���̂ł��낤�B�����ɏ]���čׂ������Ƃ������A���E�ŌÂ̌����ؑ����z�͋����ł����Čd���ł͂Ȃ��B
(�V)��{���Ƃ���O�����a�ɑJ�i���j�����̂͂U�T�U�N�ł���B�Ė��I�U�T�U�N�Ɂu�V�c�J��A�����ĞH������{�{�i��a�j�v�Ƃ���B���Ȃ�������ȑO���@��������O�ɂ������ƍl����̂����R���B
(�W) �@��������O���猻�݂̓ޗǔ����Ɉڒz���ꂽ�̂͂V�O�W�N�ƍl������i���厛�N�\�Ɂu�V�O�W�N�A�قɈ˂葾�ɕ{�ϐ������������A���@����������v�Ƃ���j�B�ڒz�̗��R�͔����̎ᑐ�����̏Ď��ł��낤�i�ᑐ�������@�����j�B�u�������ɉЁv�i�V�q�I�U�U�X�N�j�E�u�@�����ɉЁA�ꉮ���]�������v�i�V�q�I�U�V�O�N�j�Ƃ���B�U�V�O�N�̉Ύ��͖@�����ł͂Ȃ��A������������ł��낤�B�������͂U�U�X�N�ɏ��Ђ��������A�U�V�O�N�ɑS�Ă����̂ł��낤�B���������Ď������̂ŁA���̏Ď��Ձi���ۂ͏�������Ă���j�ɖ@�������ڒz���ꂽ�ƍl������i�V�O�W�N�A�u����v�łȂ��u���v�Ǝ��厛�N�\�ɂ���j�B���̗��R�͓�̎��͗��킹�Ȃ�����p���Q�O�x����Ă��āA���������Ƃ͍l�����Ȃ��B���p���k�����Ė@�������ڒz���ꂽ��A�������̋L���͖@�����̑O�j�Ƃ��ċL������A�U�V�O�N�̋L���̂悤�Ɂu�@�����̏Ď��v�ƋL�^���ꂽ���Ď������͔̂������ł��낤�B�ď̂��Ⴄ�̂͏o�T���Ⴄ����ł��낤�B�]���Č����̖@�����ɂ͉Ύ��̐Ղ��������A�T�X�S�N���̂̌d���S�����������Ă���B
(�X) �������͐������q�̎������A���̏Ď��ՂɈڒz���鎛�Ƃ��Ă͐������q�̕��ł����{�@�c�䂩��̖@�������œK�ł���B�����A��B��O�̖@�����͎��Ă����ƍl������B���̍����͖@�����������N�L�������Ɂu�H���O�S���A�A�A�ȉK�N�i�U�V�X�N�j��~�v�Ƃ���B���R�P�ށE���S�`�����ł̍������ł���i�{�͖`���Q�Ɓj�B�����̈ڒz�̑O�ɖ{���i���߉ގO�����j��������B�����a�Ɂi�\�z���ꂽ�헐������āj�ڂ��ꂽ�\���͂���Ǝv�����肩�łȂ��B
(�P�O) �V�O�W�N�Ɂu�@�����ڒz�ُ̏��v���o���������V�c�Ə�{���͎��̂悤�ɂȂ����Ă���B
��{���\�������q�̒�i��{���ƓV�c�j�\�Ė��V�c�i��{�����j�\�V�q�V�c�\�����V�c
��{���͌����V�c�̐�c�ł���B�����V�c����c�̌������ł����O�̖@�������a�����ֈڒz���������R�͏\������B�����V�c�́u�Î��L�v��^�A�u���y�L�v�̕Ҏ[�𖽂��Ă���B���j�ɊS�������B
(�P�P) �������A��a����ɂ͏�{���������Ɍ����ł��Ȃ����R���������悤���B����𐄒肷��B
�@�@��{���͘`�������̉����������ƍl�����A�`���s�L�ڂ̌�������L�q��������B
�A�@��{���i�T�X�P�`�U�Q�R�j�͐��ÓV�c�i�T�X�Q�`�U�Q�W�j�Ǝ������d�Ȃ�̂ŗ����͏o���Ȃ��B
�B�@��a�����i��O�j�����a�����i��a�j�֑J�s�����V�c�Ƃ��Đ��ÓV�c�͌������Ȃ��B
�C�@�L�I�́u�������q�̕��͗p���V�c�v�Ƃ��đh��n��a�����Ə�{���Ƃ��Ȃ��ł���B�u���͏�{�@�c�v�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�C�@�V�q�����̂�����{�@�c�͓��̎�O�͂�����B
�i�P�Q�j�@�Ȍ�A�V�q�n���V�c�͏�{���̌������������ɂ͐������q�̎��Ƃ��Ė@����悤���B
�B
[8]�@�@�����@�u���z����Ñ�������v�@�ēc�ǎO�@�V��Ё@1993�N
[9]�@�u�������Ƒh�䎁�Ə�{���Ɓv�ώ��@���_�Ё@2004�N
[10]�@�ړx�`��27.1�p�@�ړx�a��27.0cm�@�ړx�b��26.85�p�@�`�Ƃa�̈Ⴂ�͂킸�������A���z�w��ʌn���ƌ�����Ƃ����B�@����i�w�@�����̌��z�ړx�x�u�Ñ㕶�����l����v40��
��233�@���̎���̔N�\�@�@�@672�`702
��234�@�`���̎���
��235�@�C�����ƂɏI��@
��236�@����ꂽ���g
�`���ʎj�@��
�v